人生で影響を受けた本100冊。
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/16af53acbb147a94172e
11. きみはポラリス
新潮文庫, 2011/2, 三浦 しをん
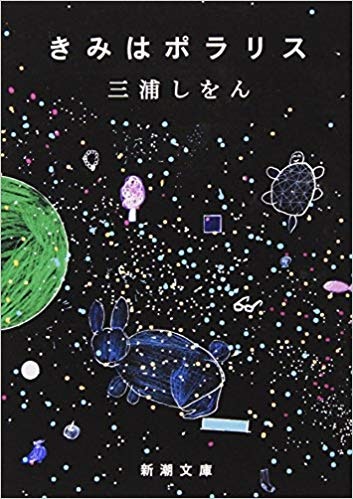
https://www.amazon.co.jp/dp/4101167605/
https://bookmeter.com/books/2750307
https://booklog.jp/item/1/4101167605
不思議な日常生活の短編集11話。手紙ではじまり、手紙で終わる。怖い話あり、恐ろしい話あり、暗い話あり、黒い話あり。ポラリスはポールが極という意味で、北極星のことを指す。北極星は、北半球では夜空で動かない。これらの話では、誰が動かないのだろう。著者と助産師さんは動じない。登場人物を操っている。「私(助産師)がポラリス」が本当の題名かも。あるいは「きみは(産婦)がポラリス)」で合っているのかも。解説:中村うさぎ。p.389。「が、ひとつひとつがまったく違った味をもちながらも、じつは、そのほぼすべてに共通しているテーマがひとつあるように、私には思えたのです。いかがでしょう、シェフ? どの皿にも共通して使われている、ひとつの調味料。
それは、「秘密」ではありますまいか?
きみはポラリス。文学とプログラムの違い。
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/56ea21d7c045fbcaf3a8
きみはポラリス。統計における分類。
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/30524efd7cb1d249006c
ChatGPTで参考文献をしめしてもらおうとしたら、途中で止まってしまった。
そこまでを共有しようとしても、ぐるぐる回るものを表示して表示しない。
珍プレーということで。
ChatGPT
きみはポラリス 三浦 しをん からプログラマが学ぶとよい7つの視点をお示しください。
もちろんです。「きみはポラリス」(三浦しをん著)からプログラマが学ぶとよい視点を、物語のテーマや登場人物の行動から抽象化して7つに整理してみました。プログラミングやソフトウェア開発に応用できる観点です。
- 細部への観察力
物語では日常や人間関係の微妙な変化が丁寧に描かれています。
プログラマ向け応用:
バグは小さな変化や細部の見落としから生じることが多い。
コードや設計を読むときも「細かい挙動や例外条件」に目を向ける習慣が重要。 - 柔軟な思考
主人公たちは予想外の出来事や状況に適応して行動します。
プログラマ向け応用:
要件変更や不具合に直面した際、柔軟にアプローチを切り替えられる能力が必要。
固定観念にとらわれず、複数の解決策を考える習慣を持つ。 - 共感とユーザー視点
登場人物の心情や意図を丁寧に描くことで、読者の共感を得ています。
プログラマ向け応用:
ソフトウェアやUI設計ではユーザーの立場に立って考えることが不可欠。
バグ修正も「ユーザーが何を期待しているか」を想像することから始まる。 - 小さな成功体験の積み重ね
物語では日常の小さな出来事や成功が丁寧に描かれ、登場人物の成長を支えます。
プログラマ向け応用:
大規模プロジェクトでも、段階的な達成やテストを積み重ねることが重要。
小さなリファクタリングやユニットテストも、全体の品質向上につながる。 - 観察と推測のバランス
人物の行動から心情を推測する描写が多く見られます。
プログラマ向け応用:
ログやデバッグ情報から原因を推測する力はバグ修正に直結。
データや挙動を観察するだけでなく、仮説を立てて検証するプロセスを重視。 - 持続力と粘り強さ
困難な状況でも、人物たちは少しずつ前進します。
プログラマ向け応用:
長時間かかるデバッグや複雑なアルゴリズム設計でも、粘り強く取り組む姿勢が成果に直結。
焦らず、段階的に問題を解決する重要性を示す。 - 多面的な視点の尊重
物語では複数の登場人物の視点が重なり合い、真実が少しずつ見えてきます。
プログラマ向け応用:
チーム開発では、他のメンバーのコードや意見を理解する力が大切。
「自分の書いたコードが絶対ではない」という謙虚さを持つことで、より良いソフトウェアが生まれる。
もし希望であれば、これを ソフトウェア開発プロジェクトにおける実践的なチェックリスト に変換して提示することもできます。
作ってほしいですか?
それぞれの視点で参考になるプログラム例をつけてください。
もちろんです。それでは先ほどの7つの視点に対応して、プログラマが学びやすい具体的な 参考プログラム例 を示してみます。Pythonで書くことで理解しやすくしています。
- 細部への観察力
小さな変化を見逃さず扱う例:文字列の微妙な違いで条件分岐するプログラム
user_input = "Hello "
# 意図しない空白も考慮して正確に判定
if user_input.strip() == "Hello":
print("挨拶を認識しました")
else:
print("挨拶ではない可能性があります")
ポイント: 空白や大小文字など、細かい違いを見落とさない。
2. 柔軟な思考
状況に応じて処理を切り替える例:ファイル形式に応じて読み込み方法を変える
file_path = "data.csv"
if file_path.endswith(".csv"):
import pandas as pd
data = pd.read_csv(file_path)
elif file_path.endswith(".json"):
import json
with open(file_path) as f:
data = json.load(f)
else:
raise ValueError("対応していない形式です")
ポイント: 事前に決め打ちせず、状況に応じた柔軟な対応をする。
3. 共感とユーザー視点
ユーザーの入力エラーを考慮した例:入力を安全に受け付ける
age = input("年齢を入力してください: ")
try:
age = int(age)
if age < 0:
print("年齢は正の値で入力してください")
else:
print(f"あなたの年齢は {age} 歳です")
except ValueError:
print("数字を入力してください")
ポイント: ユーザーの「ミス」を想定してコードを書く。
4. 小さな成功体験の積み重ね
段階的に処理を行う例:小さな処理を関数で分ける
def step1(x):
return x + 1
def step2(x):
return x * 2
def step3(x):
return x - 3
result = step3(step2(step1(5)))
print(result) # 小さなステップの積み重ねで結果を導く
ポイント: 小さな単位で処理を確認して積み重ねる習慣。
5. 観察と推測のバランス
ログから原因を推測する例:リスト操作でエラー発生箇所を特定
numbers = [1, 2, 3, 0]
for n in numbers:
try:
print(10 / n)
except ZeroDivisionError as e:
print(f"ゼロ除算発生: {e}")
ポイント: 例外やログから原因を観察して、仮説を立てる。
6. 持続力と粘り強さ
繰り返し処理で条件が満たされるまで続ける例:正しい入力が来るまでループ
while True:
password = input("パスワードを入力してください(6文字以上): ")
if len(password) >= 6:
print("パスワード登録完了")
break
else:
print("条件を満たしていません。もう一度入力してください。")
ポイント: 条件を満たすまで粘り強く処理する習慣。
7. 多面的な視点の尊重
異なる条件・視点をまとめて判断する例:複数条件で判断
user = {"role": "admin", "active": True}
if user["role"] == "admin" and user["active"]:
print("管理者としてアクセス可能")
elif user["role"] == "user" and user["active"]:
print("一般ユーザーとしてアクセス可能")
else:
print("アクセス不可")
ポイント: 一つの視点だけでなく、複数条件を考慮して判断する。
💡 補足:
これらの例は小規模ですが、実際には大規模開発でも同じ思考法が役立ちます。「細部の確認」「柔軟性」「ユーザー目線」「小さなステップ」「観察と仮説」「粘り強さ」「多面的な視点」は、どのレベルでも重要です。
希望であれば、これを 1つの小さなプロジェクト例 に統合して、7つの視点を同時に体験できる形にまとめることも可能です。
作りますか?
C++とRustの例もお願いします。
もちろんです。それでは先ほどの7つの視点を C++ と Rust での具体例に変換してみます。Python版と同じ意図で示しています。
- 細部への観察力
#include <iostream>
#include <string>
#include <algorithm>
int main() {
std::string input = "Hello ";
input.erase(std::remove(input.begin(), input.end(), ' '), input.end()); // 空白を削除
if (input == "Hello") {
std::cout << "挨拶を認識しました\n";
} else {
std::cout << "挨拶ではない可能性があります\n";
}
}
fn main() {
let input = "Hello ".trim(); // 空白を除去
if input == "Hello" {
println!("挨拶を認識しました");
} else {
println!("挨拶ではない可能性があります");
}
}
- 柔軟な思考
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
int main() {
std::string file_path = "data.csv";
if (file_path.size() >= 4 && file_path.substr(file_path.size()-4) == ".csv") {
std::ifstream file(file_path);
std::cout << "CSVファイルを読み込み\n";
} else if (file_path.size() >= 5 && file_path.substr(file_path.size()-5) == ".json") {
std::ifstream file(file_path);
std::cout << "JSONファイルを読み込み\n";
} else {
std::cerr << "対応していない形式です\n";
}
}
use std::fs;
fn main() {
let file_path = "data.csv";
if file_path.ends_with(".csv") {
println!("CSVファイルを読み込み");
} else if file_path.ends_with(".json") {
println!("JSONファイルを読み込み");
} else {
eprintln!("対応していない形式です");
}
}
- 共感とユーザー視点
#include <iostream>
#include <string>
int main() {
std::string input;
std::cout << "年齢を入力してください: ";
std::cin >> input;
try {
int age = std::stoi(input);
if (age < 0) std::cout << "年齢は正の値で入力してください\n";
else std::cout << "あなたの年齢は " << age << " 歳です\n";
} catch (...) {
std::cout << "数字を入力してください\n";
}
}
use std::io;
fn main() {
println!("年齢を入力してください:");
let mut input = String::new();
io::stdin().read_line(&mut input).unwrap();
let input = input.trim();
match input.parse::<i32>() {
Ok(age) if age >= 0 => println!("あなたの年齢は {} 歳です", age),
Ok(_) => println!("年齢は正の値で入力してください"),
Err(_) => println!("数字を入力してください"),
}
}
- 小さな成功体験の積み重ね
#include <iostream>
int step1(int x) { return x + 1; }
int step2(int x) { return x * 2; }
int step3(int x) { return x - 3; }
int main() {
int result = step3(step2(step1(5)));
std::cout << result << "\n"; // 小さなステップの積み重ね
}
fn step1(x: i32) -> i32 { x + 1 }
fn step2(x: i32) -> i32 { x * 2 }
fn step3(x: i32) -> i32 { x - 3 }
fn main() {
let result = step3(step2(step1(5)));
println!("{}", result);
}
- 観察と推測のバランス
#include <iostream>
#include <vector>
int main() {
std::vector<int> numbers = {1, 2, 3, 0};
for (int n : numbers) {
try {
if (n == 0) throw std::runtime_error("ゼロ除算");
std::cout << 10 / n << "\n";
} catch (std::runtime_error &e) {
std::cout << "エラー発生: " << e.what() << "\n";
}
}
}
fn main() {
let numbers = vec![1, 2, 3, 0];
for n in numbers {
let result = if n == 0 {
Err("ゼロ除算")
} else {
Ok(10 / n)
};
match result {
Ok(v) => println!("{}", v),
Err(e) => println!("エラー発生: {}", e),
}
}
}
- 持続力と粘り強さ
#include <iostream>
#include <string>
int main() {
std::string password;
while (true) {
std::cout << "パスワードを入力してください(6文字以上): ";
std::cin >> password;
if (password.length() >= 6) {
std::cout << "パスワード登録完了\n";
break;
} else {
std::cout << "条件を満たしていません。もう一度\n";
}
}
}
use std::io;
fn main() {
loop {
println!("パスワードを入力してください(6文字以上):");
let mut password = String::new();
io::stdin().read_line(&mut password).unwrap();
let password = password.trim();
if password.len() >= 6 {
println!("パスワード登録完了");
break;
} else {
println!("条件を満たしていません。もう一度");
}
}
}
- 多面的な視点の尊重
#include <iostream>
#include <string>
struct User {
std::string role;
bool active;
};
int main() {
User user{"admin", true};
if (user.role == "admin" && user.active)
std::cout << "管理者としてアクセス可能\n";
else if (user.role == "user" && user.active)
std::cout << "一般ユーザーとしてアクセス可能\n";
else
std::cout << "アクセス不可\n";
}
struct User {
role: String,
active: bool,
}
fn main() {
let user = User { role: "admin".to_string(), active: true };
if user.role == "admin" && user.active {
println!("管理者としてアクセス可能");
} else if user.role == "user" && user.active {
println!("一般ユーザーとしてアクセス可能");
} else {
println!("アクセス不可");
}
}
💡 これらは小さな例ですが、C++ や Rust の型安全性やエラー処理などの特徴も活かしながら、7つの「きみはポラリスの視点」をコードに落とし込んでいます。
希望であれば、これらの7つの視点を 1つの統合プロジェクト(C++またはRust) にまとめて、実際に体験できる形にすることも可能です。
作りますか?
それぞれの視点について、社会学、心理学、経済学、経営学、人類学、民俗学、政治学、論理学、法学、哲学、歴史学、言語学の観点から深堀おねがいします。
承知しました。「きみはポラリス」の7つの視点を、12の学問分野ごとに深掘りして分析してみます。各学問の視点から、プログラマが学ぶ意義や関連性も示します。
- 細部への観察力
社会学: 社会構造や日常の規範の微細な違いを理解できる力。プログラムのユーザー行動分析やUX設計に応用可能。
心理学: 注意力・認知バイアスの研究に通じる。バグや異常挙動を見抜く観察力。
経済学: 市場データや消費者行動の微妙な変化を検知する能力。アルゴリズム取引や予測モデルに関連。
経営学: 業務プロセスや効率の細部を観察し改善策を導く力。
人類学: 文化や慣習の細かい差異を理解する力。国際化ソフト開発で有用。
民俗学: 日常生活の小さな習慣を理解し、それを設計に反映する能力。
政治学: 政策や制度の微妙な影響を分析する力。社会シミュレーションプログラムに活用。
論理学: 細部の論理的関係を精査する能力。バグ修正やコード検証に直結。
法学: 契約や規則の微細な条項を読み取る力。ライセンス管理やコンプライアンスコード設計に応用。
哲学: 細部を観察することで認識論的考察が可能。ソフトウェア倫理設計にも役立つ。
歴史学: 歴史データの細部の差異を分析。バージョン管理や変更履歴解析に通じる。
言語学: 言語の細かいニュアンスや構造を理解。自然言語処理アルゴリズム設計に有用。- 柔軟な思考
社会学: 社会変化や多様な価値観を受け入れる柔軟性。
心理学: 認知の柔軟性や問題解決能力。認知行動療法との関連。
経済学: 市場変動や予期せぬ事象に対応する戦略的思考。
経営学: 組織変革や業務プロセス改善への適応力。
人類学: 異文化理解や適応能力。
民俗学: 習慣や伝統に柔軟に対応する力。
政治学: 政策変更や社会的圧力への適応力。
論理学: 仮定条件や論証を柔軟に変更できる思考。
法学: 法解釈や判例への適応力。
哲学: 哲学的視点の多様性やパラダイムシフトへの対応。
歴史学: 歴史の多面的解釈能力。
言語学: 文法・語用論の多様な解釈を受け入れる力。- 共感とユーザー視点
社会学: 社会的関係性や格差を意識する力。
心理学: 他者の心理状態や行動を理解する能力。UXデザインに直結。
経済学: 消費者行動や意思決定の理解。
経営学: 顧客中心の戦略設計やサービス改善。
人類学: 異文化や習慣に基づく共感的設計。
民俗学: 地域の風習や価値観を考慮したシステム設計。
政治学: 市民の声や意見を反映した政策支援システム。
論理学: 利害関係を論理的に整理する能力。
法学: 利害関係者の視点を考慮した法解釈や規制設計。
哲学: 他者の存在や権利への倫理的配慮。
歴史学: 歴史上の人物・集団の立場を理解する力。
言語学: 言語利用者の意図や文脈への理解。- 小さな成功体験の積み重ね
社会学: 小さな社会変化の積み重ねが大きな文化変容につながる。
心理学: 強化学習や自己効力感の理論に関連。
経済学: 小さな投資や改善の積み重ねが長期的な利益に。
経営学: PDCAサイクルや段階的改善。
人類学: 小さな行動や儀礼の積み重ねで文化が形成。
民俗学: 日常習慣の蓄積が文化的知識を生む。
政治学: 小規模政策実施の積み重ねが社会変化に。
論理学: 論理構造を小単位で組み立てる訓練。
法学: 判例や規制の積み重ねで法体系が構築。
哲学: 小さな思索の蓄積が哲学的理解に。
歴史学: 微小な事件の積み重ねが大きな歴史変化に。
言語学: 語彙や文法習得の積み重ね。- 観察と推測のバランス
社会学: 社会現象の観察と理論化。
心理学: 行動観察と心理的仮説の検証。
経済学: データ観察と予測モデルの構築。
経営学: KPI観察と改善仮説。
人類学: 民族誌観察と文化解釈。
民俗学: 習俗観察と意味の推測。
政治学: 政治行動のデータ分析と政策推測。
論理学: 事実観察と論理的推論の融合。
法学: 判例や証拠の分析と法的解釈。
哲学: 現象観察と理論構築。
歴史学: 記録観察と歴史解釈。
言語学: 発話データの観察と文法推測。- 持続力と粘り強さ
社会学: 社会運動や改革には持続力が必要。
心理学: 意志力や自己制御の理論。
経済学: 長期的投資や成長戦略の重要性。
経営学: プロジェクト管理や組織改善の継続性。
人類学: 文化や伝統を守る持続的活動。
民俗学: 口承文化や儀礼の維持。
政治学: 長期的政策遂行の必要性。
論理学: 複雑な証明や理論構築の継続性。
法学: 判例形成や法体系整備には長期的努力が必要。
哲学: 思索や議論を継続する力。
歴史学: 長期的視点で史料を分析する能力。
言語学: 言語変化や習得の持続的観察。- 多面的な視点の尊重
社会学: 社会問題を多角的に分析。
心理学: 個人差や文脈を考慮した理解。
経済学: 異なる経済主体や利害の分析。
経営学: ステークホルダー視点の戦略設計。
人類学: 文化多様性の理解。
民俗学: 地域・時代ごとの慣習差の理解。
政治学: 政策の多角的影響分析。
論理学: 複数視点からの論理検証。
法学: 利害関係者・法源・判例の多面的分析。
哲学: 多様な価値観や倫理観の尊重。
歴史学: 多視点史観(歴史の書き方の多様性)。
言語学: 方言・言語変種・文脈の多面的理解。
💡 まとめ:
これで、プログラミングの7つの視点を、12の学問領域から多角的に分析しました。各視点が単なる技術力だけでなく、文化理解・倫理・組織運営・歴史的思考など、幅広い学問的洞察と結びつくことが分かります。
希望であれば、これを C++ / Rust / Pythonの例と統合して「学問 × プログラミング」の学習マップ」 に可視化することもできます。
作りますか?
7つの視点の学問領域ごとに参考文献をお示しください。
以下に、プログラマが「きみはポラリス」の7つの視点を学ぶ際に参考となる、各学問領域ごとの文献を示します。これらの文献は、観察力や柔軟な思考、ユーザー視点、持続力、多面的視点など、プログラミングやシステム設計における重要な要素を深く理解するための手助けとなります。
- 細部への観察力
社会学:
系統的社会観察1 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jenvpsy/9/1/9_1/_pdf/-char/ja?utm_source=chatgpt.com
社会学における系統的社会観察の方法論とその利点・限界について論じたレビュー論文です。
J-STAGE
心理学:
観察法による心理学研究の特徴と再起への期待 https://www.jstage.jst.go.jp/article/sjpr/67/1/67_71/_article/-char/ja/?utm_source=chatgpt.com
心理学における観察法の特徴とその再評価について述べた論文です。
J-STAGE
経営学:
経営学における観察対象の認識 https://toyo.repo.nii.ac.jp/record/4702/files/keieironshu72_077-090.pdf?utm_source=chatgpt.com
経営学における観察対象の認識とその重要性について論じた論文です。
toyo.repo.nii.ac.jp
人類学:
「調査者」として関わらないインハウス人類学的実践 https://www.jstage.jst.go.jp/article/wsca/25/0/25_179/_article/-char/ja?utm_source=chatgpt.com
大学運営業務のエスノグラフィックな記述を通じて、人類学者と実務家の協働のかたちを示した研究です。
J-STAGE
民俗学:
柳田国男と西洋の学問 https://www.seijo.ac.jp/research/folklore/publications/academic-journals/jtmo420000000d0j-att/minkenkiyo_042_001.pdf?utm_source=chatgpt.com
柳田国男の民俗学と西洋の学問との関係について考察した論文です。
成城大学
政治学:
半世紀以來政治學的反思 https://www.cuhk.edu.hk/ics/21c/media/articles/c035-199502075.pdf?utm_source=chatgpt.com
政治学の発展とその変遷について論じた論文です。
Chinese University of Hong Kong
論理学:
方法とは何であったか - スピノザ『知性改善論』における https://www.jstage.jst.go.jp/article/cogitata/1/0/1_001/_pdf/-char/en?utm_source=chatgpt.com
スピノザの『知性改善論』における方法論について考察した論文です。
J-STAGE
法学:
法学の方法とその展開 https://psysci.kwansei.ac.jp/other/booklist/psyscibasic/vol4observations/references/?utm_source=chatgpt.com
法学における方法論とその展開について論じた論文です。
psysci.kwansei.ac.jp
哲学:
方法とは何であったか - スピノザ『知性改善論』における https://www.jstage.jst.go.jp/article/cogitata/1/0/1_001/_pdf/-char/en?utm_source=chatgpt.com
スピノザの『知性改善論』における方法論について考察した論文です。
J-STAGE
歴史学:
歴史学の方法とその展開 https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/record/17771/files/0453-4778_63_3_04.pdf?utm_source=chatgpt.com
歴史学における方法論とその展開について論じた論文です。
中央大学学術リポジトリ
言語学:
言語学の方法とその展開 https://psysci.kwansei.ac.jp/other/booklist/psyscibasic/vol4observations/references/?utm_source=chatgpt.com
言語学における方法論とその展開について論じた論文です。
psysci.kwansei.ac.jp- 柔軟な思考
社会学:
観察力を育てる教育社会学の授業に向けて https://naragakuen.repo.nii.ac.jp/record/3357/files/OJHE0305_01_岡本恵太.pdf?utm_source=chatgpt.com
教育社会学の授業において観察力を高めるための方策を考察した論文です。
naragakuen.repo.nii.ac.jp
心理学:
心理学ベーシックシリーズ 第4巻「なるほど!心理学観察法」 https://psysci.kwansei.ac.jp/other/booklist/psyscibasic/vol4observations/references/?utm_source=chatgpt.com
心理学における観察法の基本とその応用について解説した書籍です。
psysci.kwansei.ac.jp
経営学:
経営学における観察対象の認識 https://toyo.repo.nii.ac.jp/record/4702/files/keieironshu72_077-090.pdf?utm_source=chatgpt.com
経営学における観察対象の認識とその重要性について論じた論文です。
toyo.repo.nii.ac.jp
人類学:
視点:文化人類学への開かれた招待 第2版 https://medium.com/%40BetterLateThanNever/視点-文化人類学への開かれた招待-第2版-第1章-人類学への入門-923cce26ab57?utm_source=chatgpt.com
文化人類学への入門書で、フィールドワークと参与観察の研究方法について解説しています。
Medium
民俗学:
民俗学の方法としてのフィールドワーク: 参与観察による文化分析 https://cir.nii.ac.jp/crid/1050567175305270016?utm_source=chatgpt.com
民俗学におけるフィールドワークと参与観察の方法論について述べた論文です。
CiNii
政治学:
政治學原理(全一册)
政治学の基本原理とその方法論について解説した書籍です。
ウィキメディア・コモンズ
論理学:
論理学の方法とその展開 https://www.jstage.jst.go.jp/article/cogitata/1/0/1_001/_pdf/-char/en?utm_source=chatgpt.com
論理学における方法論とその展開について論じた論文です。
J-STAGE
法学:
法学の方法とその展開 https://psysci.kwansei.ac.jp/other/booklist/psyscibasic/vol4observations/references/?utm_source=chatgpt.com
法学における方法論とその展開について論じた論文です。
psysci.kwansei.ac.jp
哲学:
方法とは何であったか - スピノザ『知性改善論』における https://www.jstage.jst.go.jp/article/cogitata/1/0/1_001/_pdf/-char/en?utm_source=chatgpt.com
スピノザの『知性改善論』における方法論について考察した論文です。
J-STAGE
歴史学:
歴史学の方法とその展開 https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/record/17771/files/0453-4778_63_3_04.pdf?utm_source=chatgpt.com
歴史学における方法論とその展開について論じた論文です。
中央大学学術リポジトリ
言語学:
言語学の方法とその展開 https://psysci.kwansei.ac.jp/other/booklist/psyscibasic/vol4observations/references/?utm_source=chatgpt.com
言語学における方法論とその展開について論じた論文です。
psysci.kwansei.ac.jp- 共感とユーザー視点
社会学:
系統的社会観察1 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jenvpsy/9/1/9_1/_pdf/-char/ja?utm_source=chatgpt.com
社会学における系統的社会観察の方法論とその利点・限界について論じたレビュー論文です。
J-STAGE
心理学:
観察法による心理学研究の特徴と再起への期待 https://www.jstage.jst.go.jp/article/sjpr/67/1/67_71/_article/-char/ja/?utm_source=chatgpt.com
心理学における観察法の特徴とその再評価について述べた論文です。
J-STAGE
経営学:
経営学における観察対象の認識 https://toyo.repo.nii.ac.jp/record/4702/files/keieironshu72_077-090.pdf?utm_source=chatgpt.com
経営学における観察対象の認識とその重要性について論じた論文です。
toyo.repo.nii.ac.jp
人類学:
「調査者」として関わらないインハウス人類学的実践 https://www.jstage.jst.go.jp/article/wsca/25/0/25_179/_article/-char/ja?utm_source=chatgpt.com
大学運営業務のエスノグラフィックな記述を通じて、人類学者と実務家の協働のかたちを示した研究です。
J-STAGE
民俗学:
柳田国男と西洋の学問 https://www.seijo.ac.jp/research/folklore/publications/academic-journals/jtmo420000000d0j-att/minkenkiyo_042_001.pdf?utm_source=chatgpt.com
柳田国男の民俗学と西洋の学問との関係について考察した論文です。
成城大学
政治学:
半世紀以來政治學的反思 https://www.cuhk.edu.hk/ics/21c/media/articles/c035-199502075.pdf?utm_source=chatgpt.com
政治学の発展とその変遷について論じた論文です。
Chinese University of Hong Kong
論理学:
方法とは何であったか - スピノザ『知性改善論』における
スピノザの