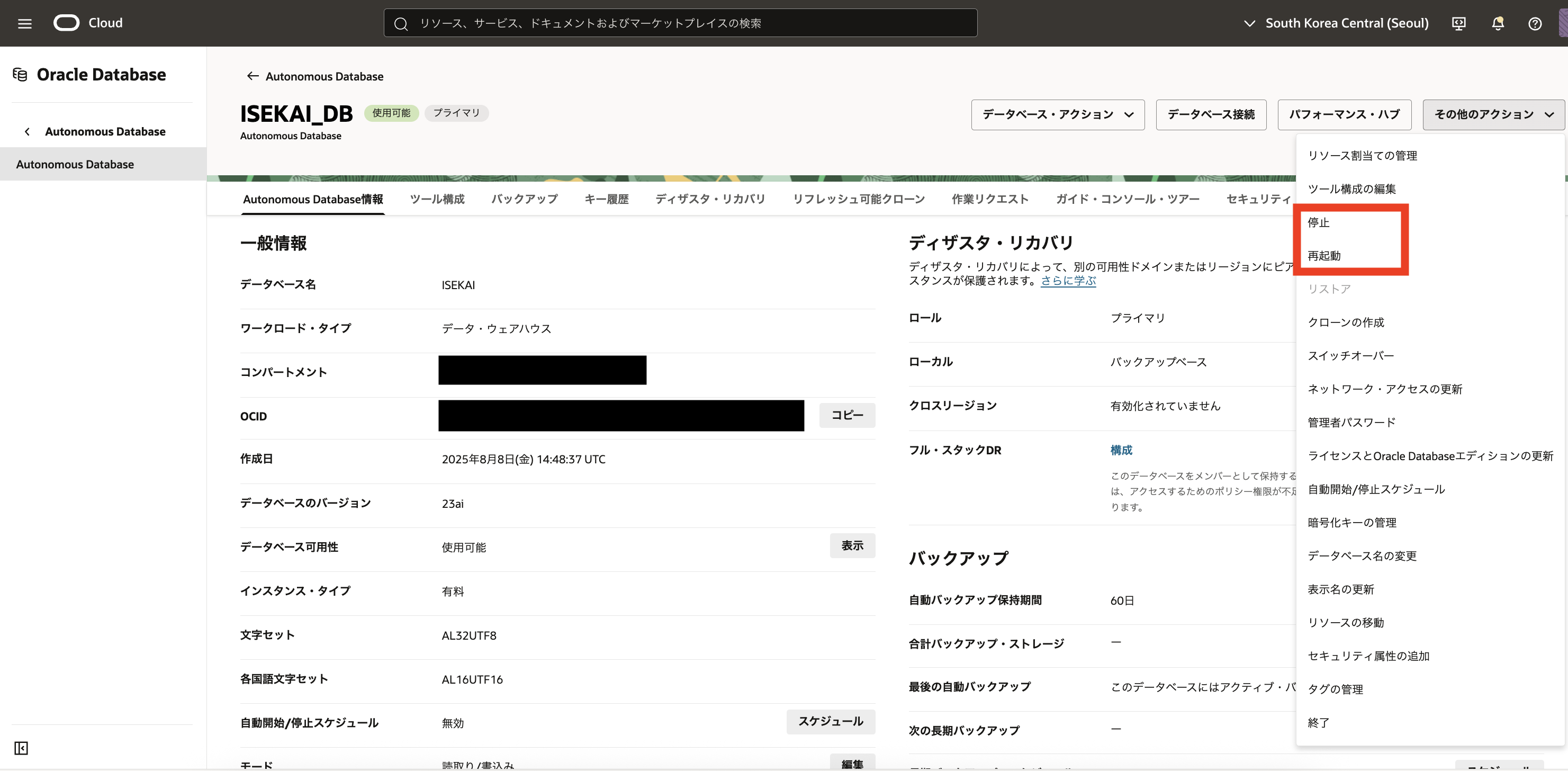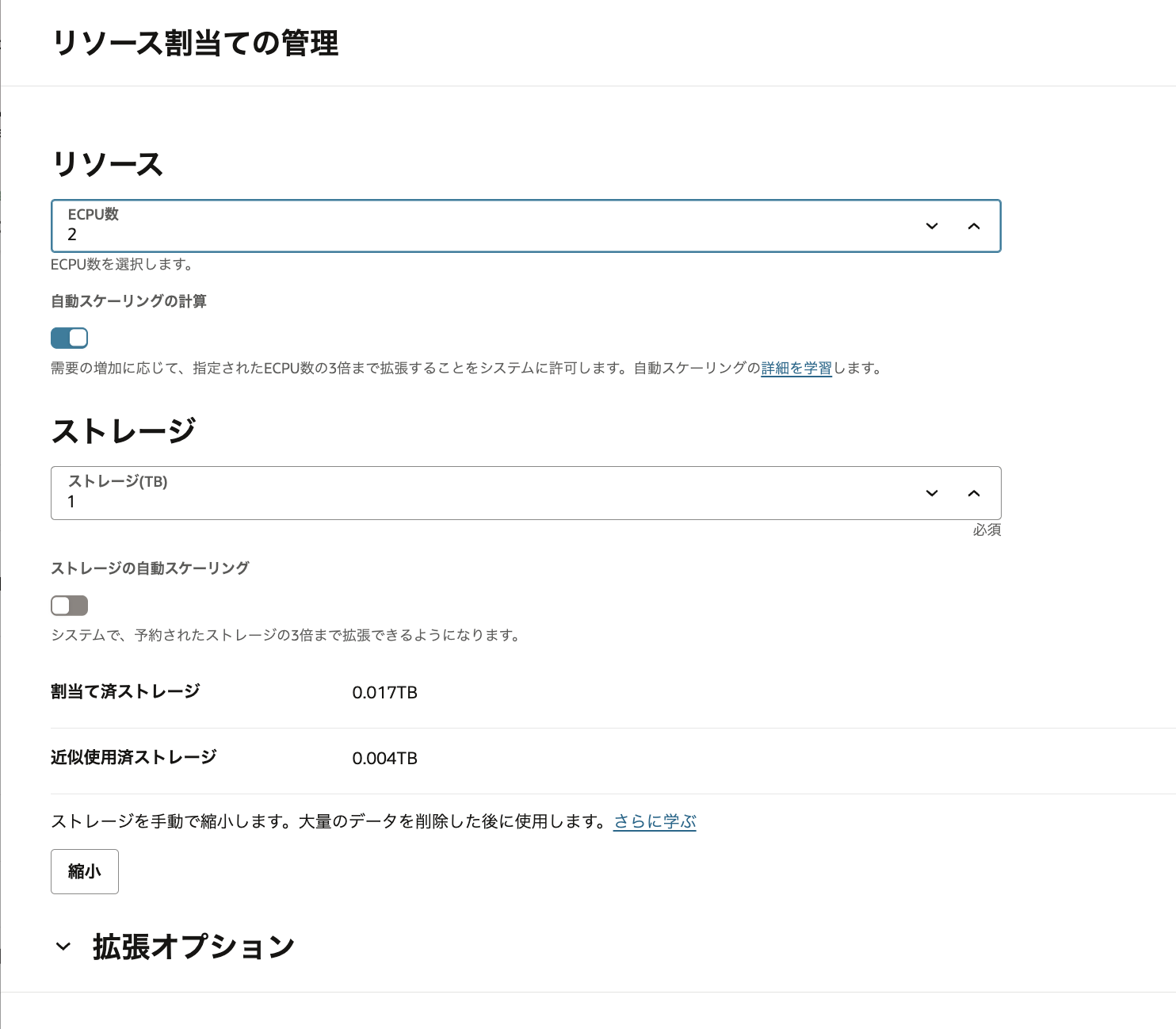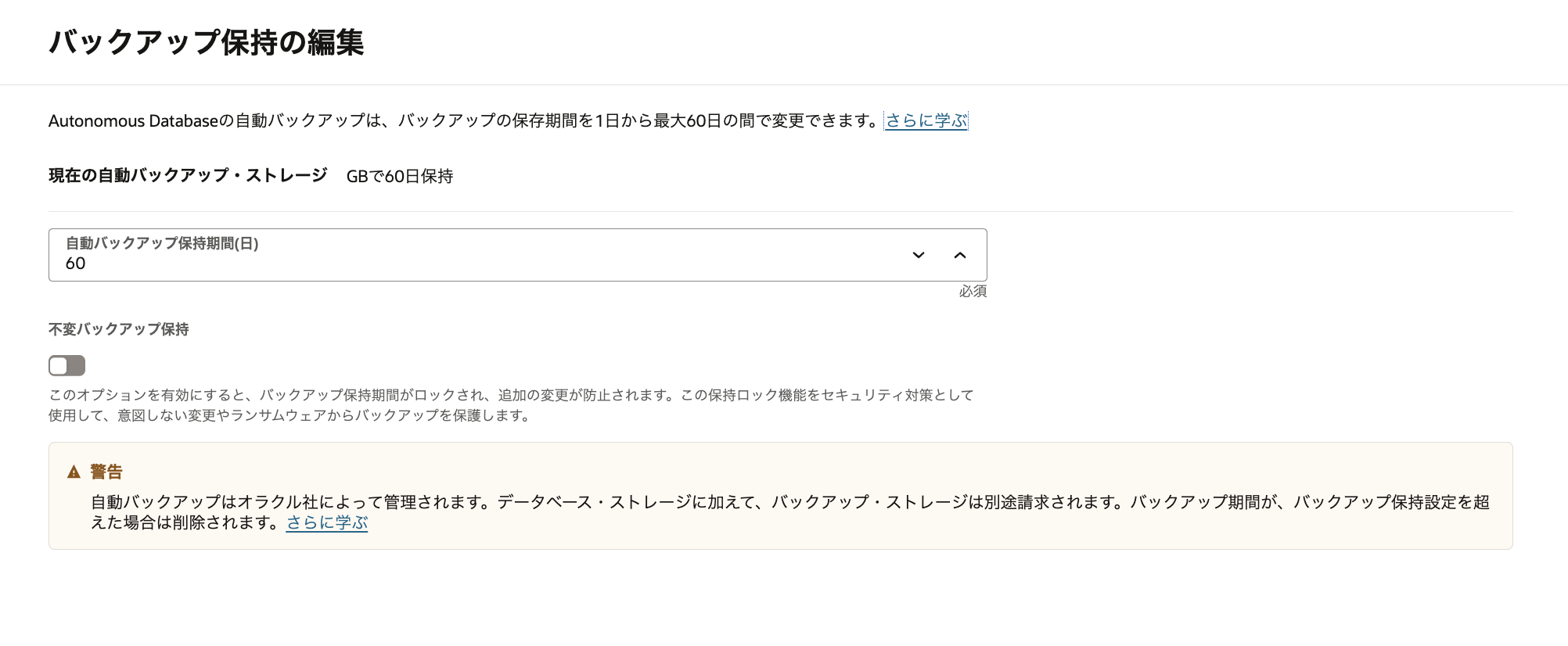俺は見てしまった。全自動で動くデータベースの姿を。
Oracle Cloud Infrastructure(OCI)――通称「異世界」。
そこに、 Autonomous Database(ADB) というチート級の存在があると聞いた俺は、正直信じていなかった。
「勝手にパッチがあたる?監視も自動?それでトラブルが起きないとか夢見すぎじゃない?」
だが、上司は言った。
「触ってみてから文句を言え」
はい、完全論破。
俺は渋々OCIのコンソールにログインした。
そこには、今まで見たことのないGUIの世界が広がっていた。
ADBとは何者なのか?
簡単に言えば、ADBはOracleが提供する「フルマネージド型の自律型データベース」。
オンプレ時代でいうところの「インフラ構築・設定・運用・監視・パッチ・バックアップ」などがすべてOracleが自動でやってくれるという代物だ。
中でも驚いたのが、以下のポイント:
1️⃣ インスタンスの起動・停止がボタン1つ
2️⃣ スケーリングが自動(負荷に応じてCPU増減)
ADBに転生した当初、俺はこう思っていた。
「CPUの単位が"OCPU"というのはわかる。でも"ECPU"って誰?」
その正体は**「Elastic CPU」の略で、従来のOCPUより柔軟なCPU課金単位**だった。
つまりーー
「俺達がADBで使う魔力の単位は、ECPUだったのだ!」
| 単位 | 概要 |
|---|---|
| OCPU(Oracle CPU) | 1OCPUは物理CPUコア1つ分に相当し、2つのハードウェアスレッド(ハイパースレッディングの場合は2vCPUに相当)を提供 |
| ECPU(Elastic CPU) | コンピューティング・リソースの抽象化された単位。コア数に基づいて、共有プールから柔軟に割り当てられる。(物理コアやスレッドと必ずしも同等ではない) |
※価格は1OCPU = 4ECPU ぐらいの換算になっているので 「1OCPU=4ECPU」 と思っておけばOK。
3️⃣ 毎日のバックアップが自動で取られる
4️⃣ SQLチューニングもAI化?!
ADBは、 実行計画・リソース使用状況・オブジェクトへのアクセスパターン などを常時監視し、そのデータを機械学習で解析している。
そして、インデックス作成や統計更新、メモリの並列度や調整まで自動でやってくれる。
つまりーー
人間DBAのチューニング作業を丸ごと引き継いで、日々自己進化するチートDBってわけだ。
正直、信じられなかった
オンプレ時代、こんなことがあり得ただろうか?
パッチを当てるのに、メンテナンス手順を何十ページも作ってた
バックアップスケジュールを組んで、失敗ログを毎朝チェックしてた
SQLが遅ければ、Explain Plan片手にインデックスを研究してた
それらが…
何もせずに動くというのか?
でも、チートには“制限”もある
このとき俺はまだ知らなかった。
ADBは確かに便利だが、制御できないことも多いということを。
それは次回以降の話だ。
ただ、このときの俺は――
「なんだかんだ言って、これは…やばい(良い意味で)」
と、素直に思っていた。
次回予告
第3話|触れない!?OSもファイルも奪われたDBAの初陣
「DBにログインして、構成を直す」ことが許されない世界とは?
ADBが隠している“自動化の裏側”に、俺はついに気づく…。