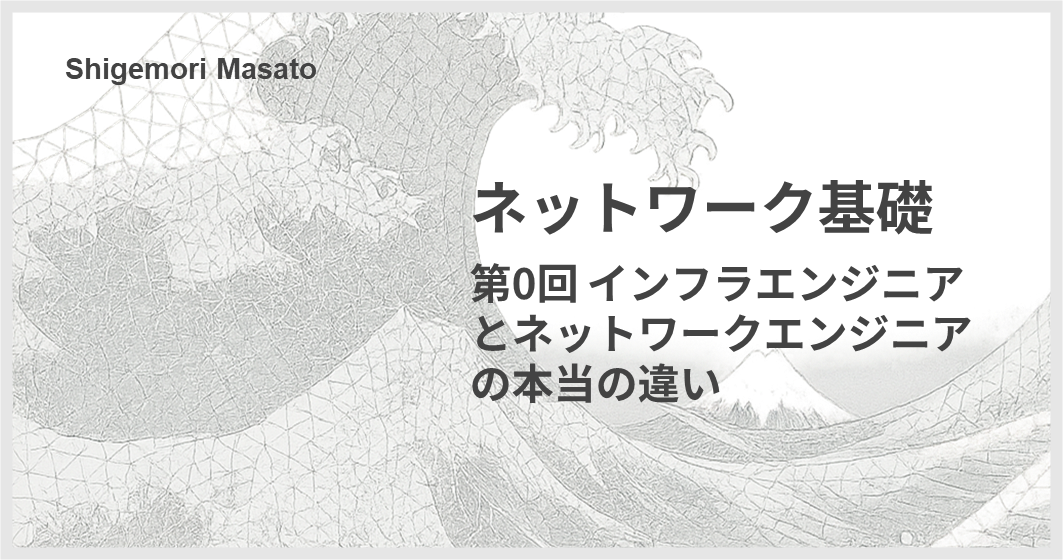最近、SNSを見ていて気になることがあります。「高還元SES インフラエンジニア募集」求人の内容を詳しく見ると、実際にはサーバー構築の仕事だったり、クラウドの設定作業だったり、ネットワークの運用保守だったりと、企業によってまったく異なる業務内容が記載されています。
今回は、連載を始めるにあたり、まず「インフラエンジニア」という曖昧な言葉の解像度を上げ、各エンジニア職種の本当の業務内容について整理していきます。
インフラエンジニアという言葉の曖昧さ
IT業界において「インフラエンジニア」という言葉は、非常に広範囲な意味で使われています。これは、ITインフラストラクチャ1が複数の技術領域から構成されているためです。しかし、この曖昧さが、キャリア形成や採用のミスマッチを生む原因となっています。
プロジェクトの規模によって、インフラエンジニアの役割は大きく変わります。
1億円未満の小規模案件では、少人数で複数の役割を兼任することが一般的です。一人のエンジニアがサーバー構築からネットワーク設定まで幅広く対応し、ジェネラリスト的なスキルが求められます。ある案件ではサーバーエンジニアとして、別の案件ではネットワークエンジニアとして業務を行うこともあるでしょう。
一方、100億円を超える大規模案件になると、状況は一変します。20名近いインフラチームが編成され、各分野の専門家が専任で参画します。その道で名の通った専門企業が参加し、それぞれの分野で高度な専門性と深い知識を持つエンジニアが集結します。
例えば、運用管理ツールのJP1担当には、日立システムズでJP1を長年扱ってきた専門家が参画し、データベース分野では、Oracleを20年以上運用してきたOracle専門のエンジニアが投入されます。このような専門家は、製品の深い知識だけでなく、過去のトラブルシューティング経験や、ベンダーとの太いパイプを持っており、プロジェクトの成功に不可欠な存在となります。
このように、「インフラエンジニア」という肩書きだけでは、実際の業務内容や必要なスキルを正確に表現できないのが現状です。キャリアを考える際は、どの分野の専門性を深めていくかを明確にすることが重要になります。
各エンジニア職種の詳細
サーバーエンジニア
サーバーエンジニア2は、主にOS層より上位のレイヤーを担当します。物理サーバーや仮想サーバーの構築・運用が主な業務です。
主な業務内容
- OSのインストールと設定(Linux、Windows Server)
- ミドルウェアの構築(Apache、Nginx、Docker)
- 仮想化基盤の構築(VMware、Hyper-V、KVM)
- パフォーマンスチューニング
- パッチ適用と脆弱性対応
必要なスキル
ネットワークエンジニア
ネットワークエンジニア3は、OSI参照モデル4の全層にわたる知識が必要ですが、特に下位層(物理層〜ネットワーク層)に強みを持ちます。
主な業務内容
- 物理配線設計・施工
- ネットワーク機器の設定(スイッチ、ルーター、ファイアウォール)
- WAN/LAN設計
- キャリア回線の選定・調整
- トラブルシューティング
必要なスキル(階層別)
深い専門知識の例
ネットワークエンジニアが持つべき物理層の知識は、他のインフラエンジニアには求められない特殊なものです。
配線規格については、Cat5eは100m以内で1Gbpsの通信が可能、Cat6は55m以内であれば10Gbpsに対応、Cat6Aは100m以内で10Gbpsの通信が可能といった、細かな仕様を把握している必要があります。光ファイバーについても、MMF(マルチモードファイバー)は短距離用で約550mまで、SMF(シングルモードファイバー)は長距離用で約40kmまでの通信が可能といった知識が必要です。
キャリア設備に関しては、MDF(主配線盤)やIDF(中間配線盤)の設計、責任分界点(キャリアと利用者の責任境界)の理解、CTF(キャリア端子函)の取り扱いなど、建物内の通信インフラに関する深い知識が求められます。
施工知識としては、共同溝での作業には道路占用許可が必要であること、とう道(通信ケーブル用の地下トンネル)での作業は有資格者のみが可能であること、建築基準法に基づく耐火区画の貫通処理など、法令や安全基準に関する知識も必要不可欠です。
このような物理的な知識は、ネットワークエンジニアが単にネットワーク機器の設定ができるだけでなく、インフラ全体を俯瞰して設計・構築できる専門家であることを示しています。
世代によって異なる物理層の経験
現在の50代のネットワークエンジニアの中には、元々内線工事やNTTでオプトス(光通信関連工事)を担当していた人が多く存在します。また、NTTやその下請けの通信建設会社で架空構造物設計を行っていた人も少なくありません。彼らは現在のネットワークエンジニアとは異なる、より深い物理層の実務経験を持っています。
当時の技術者たちは、アナログモデムでCD信号(キャリア検出信号)を確認したり、ワイヤラップやパンチダウンツールを使って回線開通作業を行っていました。IDF(中間配線盤)からロゼット(壁面の情報コンセント)までの物理的な開通作業を、すべて手作業で行った経験を持っています。
架空構造物設計の経験者は、
- 電柱の強度計算と支線設計(風圧荷重や積雪荷重を考慮)
- 架空ケーブルの弛度計算(温度変化による伸縮を考慮した設計)
- 共架申請の手続き(電力会社との調整)
- 道路占用許可申請(自治体との調整)
といった、通信インフラの物理的な基盤に関する専門知識を持っています。
特筆すべきは、彼らは街中の架空設備を見ただけで、どのキャリアがどのように配線しているかを識別できる能力を持っていることです。ケーブルの太さ、取り付け位置、クロージャー(接続函)の形状などから、NTT、電力系通信会社、CATVなどを見分けることができます。
この能力により、同じ経路で同じ電柱に複数キャリアの回線が集約されている状況を単一障害点として認識できます。例えば、
- メイン回線とバックアップ回線が同じ電柱を通っている
- 異なるキャリアを使っているつもりが、物理的には同じ経路を通っている
- 電柱倒壊や架空ケーブル切断で、複数回線が同時に障害となるリスク
このような物理的なリスクは、論理的な冗長構成だけでは防げません。
このような経験を持つエンジニアは、
- 障害時の物理的な切り分けが直感的にできる(音や手触りで異常を感知)
- 建物内外の配線経路を立体的に把握できる(実際に天井裏や床下、電柱上での作業経験)
- 古い設備との接続にも対応できる(レガシー機器の知識)
- 災害時の復旧計画が立てられる(物理インフラの脆弱性を理解)
- 真の冗長性を確保した設計ができる(物理経路の分離を考慮)
といった、教科書では学べない実践的なスキルを持っています。これらの経験は、現代のネットワークエンジニアリングにおいても、トラブルシューティングや災害対策の際に大きな強みとなっています。
データベースエンジニア
データベースエンジニア5は、データベースの設計・管理・最適化を専門とします。アプリの開発者はデータベースエンジニアがテーブル設計を行うと誤解することがありますが、実際にはデータベースエンジニアは主にDBの管理や最適化に焦点を当てており、テーブル設計は開発者や他の関連職が担当することが一般的です。
主な業務内容
- データベース設計(論理設計・物理設計)
- SQLチューニング
- バックアップ・リカバリ設計
- レプリケーション構築
- 性能監視と最適化
ストレージエンジニア
ストレージエンジニア6は、大容量データの保存・管理を専門とします。
主な業務内容
- SAN/NAS設計
- RAID構成設計
- バックアップシステム構築
- 容量管理
- I/O性能最適化
クラウドエンジニア
クラウドエンジニア7は、パブリッククラウドサービスを活用したインフラ構築を行います。クラウドエンジニアの場合は1人で多くの役割を兼任することが多いです。
主な業務内容
- クラウドアーキテクチャ設計
- IaC(Infrastructure as Code)実装
- クラウドセキュリティ設定
- コスト最適化
- マルチクラウド連携
- ネットワーク
運用オペレーター
運用オペレーター8は、構築されたシステムの日常的な運用を担当する、インフラの最前線で働くエンジニアです。給与水準から下に見られがちですが、システムの安定稼働を支える重要な職種です。
主な業務内容
- 24時間365日の監視業務(シフト勤務)
- 監視システムのアラート対応
- 定型運用作業(バックアップ、ログ確認、定期再起動)
- 障害の一次切り分けとエスカレーション
- 運用手順書に基づいた作業実施
- インシデント記録と報告書作成
必要なスキル
運用オペレーターの真の価値
職業に関わらず優秀な人は優秀であり、運用オペレーター出身で上流工程まで這い上がってきたエンジニアには、他では得られない強みがあります。深夜3時の障害対応を経験した人は、「この設計では深夜に呼び出される」ことを肌で理解しています。
運用を理解しているエンジニアが設計したシステムは、
- エラーメッセージが分かりやすい(深夜の判断ミスを防ぐ)
- 監視しやすいログ設計(何が起きているか一目瞭然)
- 運用手順書が書きやすい構成(複雑な手順を避ける)
- 障害時の切り分けポイントが明確
- メンテナンス時の影響範囲が最小化されている
といった特徴があり、結果として安定稼働するシステムとなります。これは給与や職位では測れない、真の実力と言えるでしょう。
実は更に細分化されている専門職の世界
ここまで各エンジニア職種について説明してきましたが、実際の現場では、これらがさらに細かく専門職化されています。
例えば「サーバーエンジニア」と一括りにしていますが、実際にはx86系のWindowsやLinuxを扱うエンジニアと、IBM AIXやpSeriesを扱うエンジニアでは、必要な知識も経験もまったく異なります。同じ「サーバー」を扱っていても、別の職種と言えるほど専門性が分かれているのが実情です。
ネットワークエンジニアも同様で、Cisco製品に特化したエンジニア、国産ベンダーの製品を扱うエンジニア、無線LANに特化したエンジニアなど、扱う機器やベンダーによって専門が分かれています。「ネットワークができます」では通用せず、「どのベンダーの、どの製品群の、どのバージョンの経験があるか」まで問われる世界です。
監視系の設計においても、JP1を使った監視システムの設計ができるエンジニアと、Zabbixを使った監視システムの設計ができるエンジニアは、それぞれ別の専門職として扱われます。同じ「監視」という機能を実現するにも関わらず、製品が違えば設計思想から運用方法まですべて異なるためです。
このような細分化は、それぞれの製品やプラットフォームが独自の進化を遂げ、深い専門知識を要求するようになったことが背景にあります。企業側も既存システムへの投資を無駄にできないため、特定の製品やバージョンに精通したスペシャリストを求めます。結果として、「インフラエンジニア」という大きな括りの中に、無数の専門職が存在する非常に細かい世界となっているのです。
工程による役割の違い
さらに重要なのは、同じ職種でも担当工程によって求められるスキルがまったく異なることです。
上流工程(要件定義・基本設計)
上流工程を担当するエンジニアは、技術的な実作業はほぼ行いません。求められるのは、ビジネス要件を理解し、それを技術的な設計に落とし込む能力です。文書作成能力やプレゼンテーション能力が重要で、顧客との折衝も多くなります。年収レンジは800-1500万円と高く、キャリアパスとしてはコンサルタントやアーキテクトへの道が開けています。
中流工程(詳細設計・構築・試験)
中流工程は、実際に手を動かして構築作業を行うフェーズです。高い技術力とトラブルシューティング能力が求められ、手順書の作成なども重要な業務となります。年収レンジは400-800万円程度で、スペシャリストやリードエンジニアとしてのキャリアパスがあります。この工程の経験を積むことで、技術的な深い知識を身につけることができます。
下流工程(運用・保守)
下流工程では、構築されたシステムの日常的な運用と保守を担当します。定型作業を正確にこなす能力や、障害発生時の迅速な対応力が求められます。顧客やベンダーとのコミュニケーション能力も重要です。年収レンジは300-600万円程度ですが、ここで経験を積んで中流工程へステップアップしたり、運用リーダーとして管理職を目指すキャリアパスがあります。
このように、同じ「ネットワークエンジニア」でも、担当する工程によって業務内容も求められるスキルも、そして年収も大きく異なります。自分がどの工程で強みを発揮できるか、どのようなキャリアを目指すかを考えることが重要です。
なぜネットワークエンジニアは特殊なのか
ネットワークエンジニアが他のインフラエンジニアと大きく異なる点は、物理的な作業から論理的な設計まで、非常に幅広い領域をカバーする必要があることです。
物理層の深い知識が必要な理由
サーバーエンジニアであれば「ネットワークに繋がらない」という問題は、ネットワークエンジニアに投げれば済みます。しかし、ネットワークエンジニアは最終的な責任を負うため、物理層から順番にすべての層を確認する必要があります。
キャリア設備の知識が必要な理由
企業のネットワークは、必ず外部(インターネットや他拠点)と接続する必要があります。この接続点で必要になるのが、キャリア9に関する深い知識です。
キャリア関連で必要な知識
回線種別の理解
| 回線種別 | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|
| 専用線 | 帯域保証100%、高額 | ミッションクリティカルな通信 |
| 広域イーサネット | 柔軟性高い、VLAN対応 | 複数拠点の接続 |
| インターネットVPN | 安価、品質は不安定 | コスト重視の拠点間通信 |
| IP-VPN | 閉域網、セキュア | セキュリティ重視の企業ネットワーク |
物理的な接続に関する知識
ネットワークエンジニアは、以下のような物理的な設備についても理解している必要があります。
- 局舎:キャリアの設備がある建物で、ここから各ビルへ回線が引き込まれる
- MDF(主配線盤):建物内の主配線盤で、キャリア回線の引き込み点となる
- 責任分界点:キャリアと利用者の責任境界。障害時の切り分けで重要
- 引き込み経路:局舎から建物までの物理経路。工事可否の判断に必要
必要な調整業務
キャリアとの調整では、技術的な知識だけでなく、プロジェクト管理能力も求められます。
- 工事日程:キャリア側と利用者側の調整が必要。双方の作業員の手配も含む
- 仕様確認:インターフェース規格、VLAN設定、ルーティング情報などの技術仕様のすり合わせ
- 障害切り分け:障害発生時にどちらの責任範囲かを明確にし、迅速な復旧を行う
これらの知識は、サーバーエンジニアやクラウドエンジニアには通常求められない、ネットワークエンジニア特有の専門知識です。
キャリアパスの違い
各エンジニアのキャリアパスも大きく異なります。
おわりに
「インフラエンジニア」という言葉の曖昧さを理解し、各職種の専門性を正しく認識することは、キャリア形成において非常に重要です。特にネットワークエンジニアは、物理的な配線作業からキャリアとの調整、高度なルーティング設計まで、非常に幅広い知識と経験が要求される職種です。
また、運用オペレーターを含めたすべての職種には、それぞれの重要性と専門性があります。給与や職位に関わらず、各職種で培った経験と知識は、インフラエンジニアとしての総合的な実力につながります。
次回からは、ネットワークエンジニアが実際に行う「ネットワーク設計」について、その全体像と各フェーズの詳細を体系的に解説していきます。
もしこの記事が「面白かった!」「勉強になった!」と思ったら、ぜひ LGTM(いいね!) で応援してくださると嬉しいです。
-
ITインフラストラクチャ - 企業の情報システムを支える基盤となるハードウェア、ソフトウェア、ネットワークなどの総称。 ↩
-
サーバーエンジニア - サーバーの構築・運用・保守を専門とするエンジニア。OS層より上位のレイヤーを主に担当する。 ↩
-
ネットワークエンジニア - ネットワークの設計・構築・運用を専門とするエンジニア。物理層から応用層まで幅広い知識が必要。 ↩
-
OSI参照モデル - ネットワークプロトコルを7つの階層に分けたモデル。物理層からアプリケーション層まで、各層の役割を定義している。 ↩
-
データベースエンジニア - データベースの設計・構築・運用・最適化を専門とするエンジニア。 ↩
-
ストレージエンジニア - 大容量データの保存・管理システムを専門とするエンジニア。SAN/NAS等の技術に精通。 ↩
-
クラウドエンジニア - AWS、Azure、GCPなどのパブリッククラウドを活用したシステム構築を専門とするエンジニア。 ↩
-
運用オペレーター - システムの日常的な運用・監視を担当するエンジニア。24時間365日のシフト勤務が多い。 ↩
-
キャリア - 通信事業者。NTT、KDDI、ソフトバンクなど、通信回線を提供する事業者を指す。 ↩