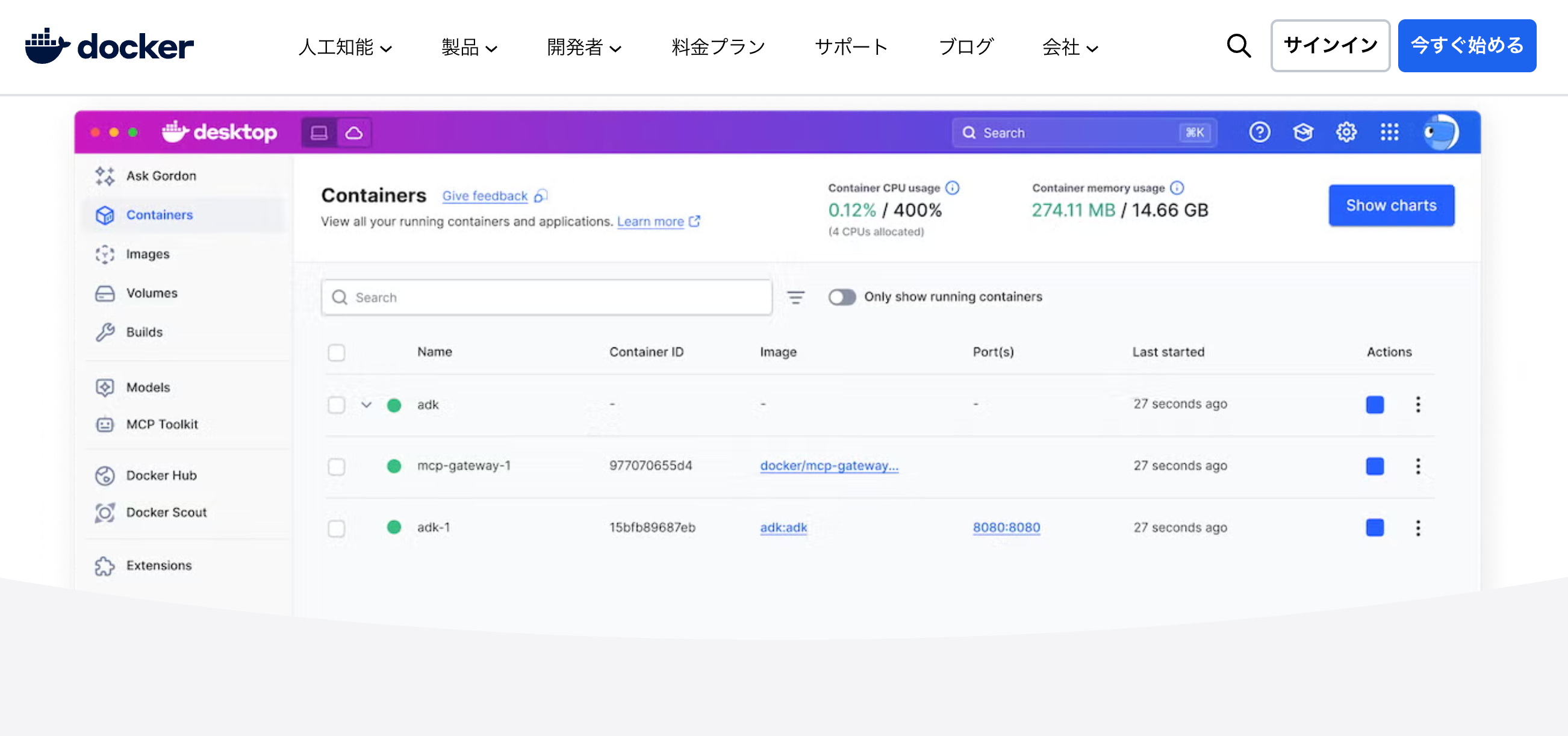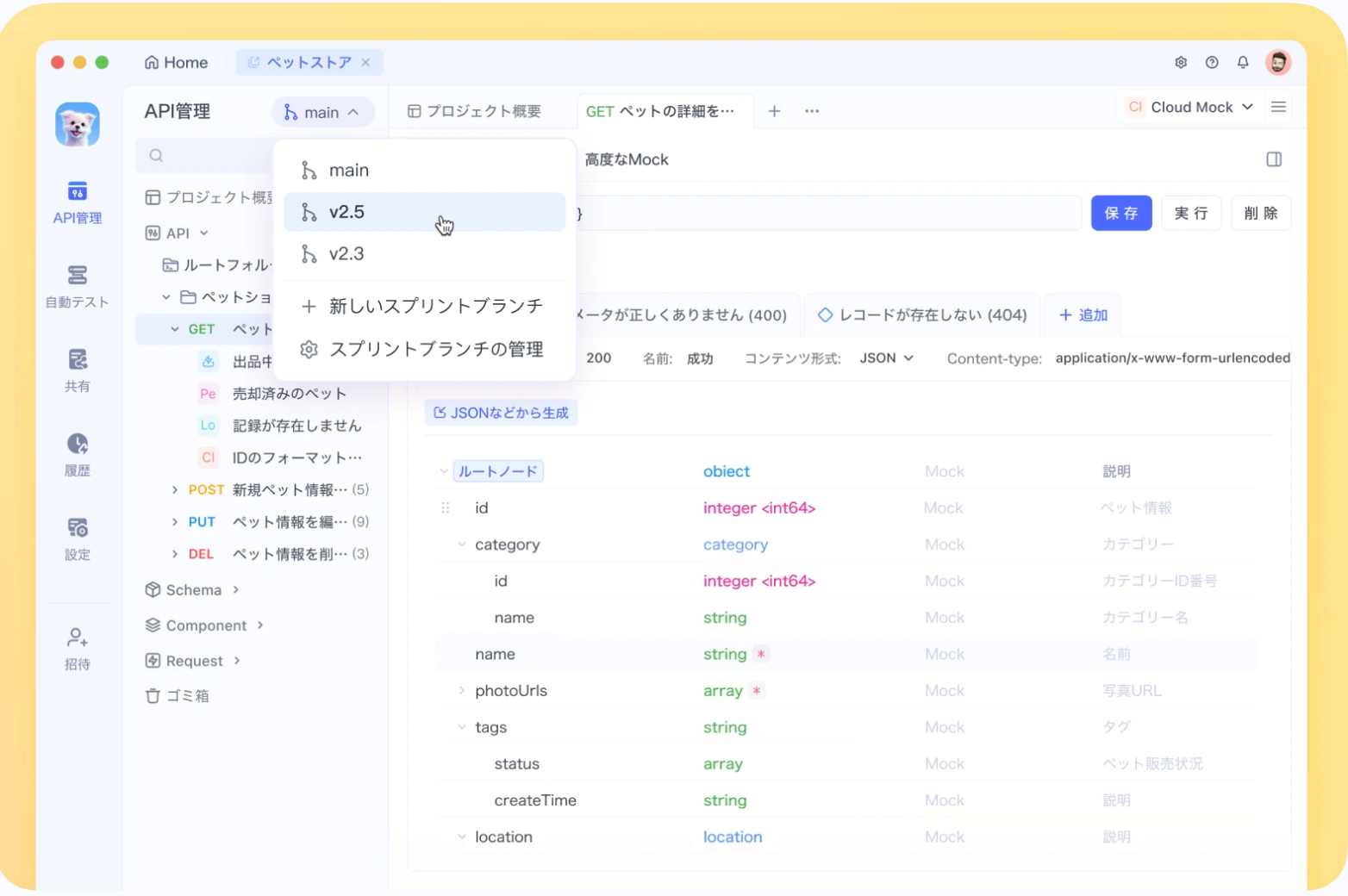去年の今頃、僕は完全な未経験者だった。
プログラミングの「プ」の字も知らず、ターミナルを開くのすら怖かった。
でも、2025年の今、僕は実務レベルのエンジニアとして働いている。
何が変わったのか?それはAIの力を借りながら、正しい順番で基礎を積み上げたことだ。
AIがあれば学習効率は5〜10倍になる。これは本当だ。
でも、AIは魔法じゃない。基礎がない人間を一瞬でエンジニアにはしてくれない。
AIはブースターであって、代行業者じゃない。
今回は、僕が実際に辿った学習ルートを全部公開する。
挫折しにくく、実務に直結する内容だけを厳選した。
Linux — 最初は怖かったけど、今は手放せない
最初にLinuxを触ったとき、正直意味がわからなかった。
「なんでGUIじゃないの?」「コマンドって何?」
でも、Linuxはサーバー、コンテナ、クラウドのすべての基盤だ。
完璧に覚える必要はない。以下だけ理解できれば十分:
- 基本コマンド(ls、cd、cat、grep)
- 権限とユーザー管理(chmod、chown)
- ネットワークの基礎(IP、Port、DNS、SSH)
- サービスの概念(systemctl、プロセス管理)
少し触るだけでも、IT全体の構造が見えてくる。
最初は怖いけど、慣れれば「なんでもっと早く触らなかったんだ」と思うはずだ。
Bash / Python — 自動化の第一歩を踏み出す
スクリプトを書けるようになると、世界が変わる。
最初は簡単なことから始めた:
- ファイルを一括リネーム
- ログファイルから特定の行を抽出
- APIからデータを取得して整形
こういった作業を自動化できるようになると、人間が30分かかる作業を数秒で終わらせられる。
これがエンジニアの本質だ。
「人間の手作業をコードに置き換える」
この感覚を掴めば、あとは応用するだけ。条件分岐、ループ、関数、ファイル処理——最初は難しく感じるけど、実際に手を動かせばすぐに慣れる。PythonでもBashでも、まずは小さな自動化から始めてみるといい。
Docker — 「環境構築で詰まる」から解放された
「ローカルでは動くのに本番で動かない」
この悪夢から解放してくれたのがDockerだ。
最初は概念が難しかった:
- イメージとは何か?
- コンテナとは何か?
- Dockerfileって何を書けばいいの?
でも、小さなアプリ(Node.jsやPython)をDocker化してみると、すぐに理解できた。
どこでも同じ環境が再現できる。環境構築のストレスが一気になくなった。
「ローカルで動いたのに本番で動かない」という悪夢から解放される感覚は、本当に最高だ。
チュートリアルを見ながら、まずは既存のアプリをコンテナ化してみるのがおすすめ。理屈より先に手を動かす方が理解が早い。
Git — エンジニアとして名乗るための必須スキル
Gitは単なるツールじゃない。チーム開発の文化だ。
最初は「コミット」「プッシュ」「プル」の違いすらわからなかった。
でも、実際にチーム開発に参加すると、その重要性が身に染みた。
必ず学ぶべきは:
- ブランチ戦略(feature、develop、main)
- Pull Request(レビューの文化)
- コンフリクト解消(最初は怖いけど慣れる)
- 履歴管理(git log、git blame)
AIがあれば、コンフリクトの解説やコミットメッセージの自動生成、PRの要約も簡単にできる。
Gitを使いこなせないエンジニアは、もはや存在しない。
CI/CD — コードを書く人から"ソフトを届ける人"へ
GitHub Actionsを初めて触ったとき、衝撃を受けた。
「コードをプッシュするだけで、テストが走って、ビルドされて、デプロイされる」
これが自動化の力だ。
最初は簡単なワークフローから始めた:
- テスト自動化(pytest、jest)
- ビルド自動化(Dockerイメージ作成)
- デプロイ自動化(Vercel、AWS)
これができるようになると、開発の全体像が見えてくる。
「コードを書く」だけじゃなく、「ソフトを届ける」ところまで理解できる。
最初は既存のテンプレートをコピーして使うだけでもいい。動く仕組みを見てから、少しずつカスタマイズしていけば理解が深まる。
API開発とテスト — 正しいツール選びで学習効率が変わる
ほぼすべての現代アプリケーションはAPIに支えられている。
最初はPostmanを使っていた。でも、すぐに問題に気づいた:
- 設計書はSwaggerで別管理
- テストケースはスクリプトで別管理
- ドキュメントはNotionで別管理
バラバラすぎて、管理が大変だった。
そこで出会ったのがApidogだ。
Apidog — API開発の面倒を一気に解決
Apidogの良いところは:
- 設計・テスト・ドキュメント・Mockが一つのツールで完結
- 設定がシンプルで未経験でも扱いやすい
- 設計とテスト、ドキュメントが自動で同期される
- Mockでバックエンドなしでもフロント開発できる
- AIによるテストケースやドキュメント生成が便利
実際の使い方:
- OpenAPI仕様をインポート
- AIが自動でテストケースを生成
- そのままチームで共有
PostmanやSwaggerを行き来する手間が一気になくなった。
未経験者にとって、API学習のハードルを大幅に下げるツールとして最適だ。
クラウド(AWS/GCP/Azure)— まずは1つを選ぶ
三大クラウドは"御三家"のような存在だ。
最初は「全部学ばなきゃ」と思っていた。でも、それは間違いだった。
まずは1つだけ選び、徹底的に触れるのが最短ルート。
僕はAWSを選んだ。理由は:
- 資料・事例・求人が圧倒的に多い
- 日本語ドキュメントが充実している
- コミュニティが活発
最初はEC2とS3だけ触った。それだけでも十分実務レベルに近づける。
無料枠を使って、小さなWebアプリをデプロイしてみるのがおすすめだ。
IaC — 中級エンジニアへの階段
TerraformやCloudFormationを使って:
- インフラをコード化し
- 再現性のあるデプロイを行い
- 変更履歴を管理する
これができれば、実務レベルのインフラ運用スキルが身につく。
Terraformから始めると学習しやすい。
AWSのコンソールをポチポチするより、コードで管理する方が圧倒的に効率的だ。変更履歴もGitで管理できるし、チーム全体でインフラの状態を共有できる。
最初は既存のテンプレートを読むところから始めるといい。書く前に読む。これが理解への近道だ。
AIの活用 — なぜ“基礎”が以前より重要なのか?
AIは僕の学習を劇的に加速させた。
実際に使っている活用例:
- コード生成(関数の雛形作成)
- Dockerfile最適化(ベストプラクティスの提案)
- APIドキュメント自動作成(Apidog対応)
- エラーメッセージの解説(英語のエラーも怖くない)
- SQL生成(複雑なクエリも一瞬)
- Gitの履歴分析(コードレビューの補助)
- テストケース生成(網羅的なテスト設計)
AIを使うだけで、未経験でも実務速度に近づける。
でも、忘れちゃいけないのは:
AIはあなたの代わりではなく、あなたの能力を伸ばすパートナーだ。
基礎がないとAIの出力が正しいかどうかも判断できない。だから、基礎学習は絶対に手を抜いちゃダメだ。
まとめ:正しい順番 × 正しいツール × AIの活用が最短ルート
1年前の僕は、何から始めればいいかわからなかった。
でも、今ならはっきり言える。
必要なのは才能じゃない。順番と継続、そしてツール選びだ。
正しい学習ルートと、良いツール、AIの力があれば、
未経験でも必ずエンジニアになれる。
僕がそうだったように。
あなたの学習ロードマップはどうですか?コメント欄で教えてください!
この記事が役に立ったら、ぜひシェアしてくださいね。