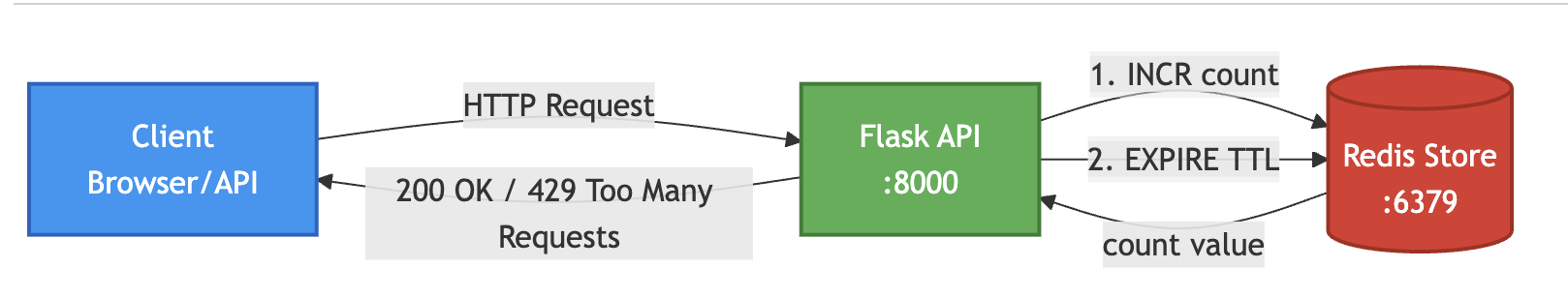1. はじめに
本稿では、分散システムにおけるAPIレートリミッターの設計と実装を、解説します。
Flask・Redis・Docker Composeを用い、固定ウィンドウカウンター方式を構築。
さらに、Jupyter Notebookで可視化検証を行い、バースト制御の限界と改善策を学びます。
技術選定理由
| 技術 | 理由 |
|---|---|
| Flask | 軽量で構造が理解しやすく、FastAPIなどへの移行も容易。 |
| Redis |
INCR / EXPIRE による原子的操作が可能で、高速・低レイテンシ。 |
| Docker Compose | Redis + Flask のローカル検証環境を簡単に再現可能。 |
| Jupyter Notebook | レートリミット挙動の記録・分析・可視化が容易。 |
| Luaスクリプト非使用 | 教育目的で可読性を優先。厳密運用ではLua対応を推奨。 |
2. 理論背景:レートリミッターの方式比較
レートリミッターには複数の方式があり、それぞれトレードオフがあります。
| アルゴリズム | 概要 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|---|
| トークンバケット | トークンを時間で補充し消費で制御 | バースト吸収に強い | 実装がやや複雑 |
| 固定ウィンドウ(本稿) | 一定期間のリクエスト数をカウント | 実装が簡潔・高速 | ウィンドウ境界でバースト発生しやすい |
| スライディングウィンドウ | 時間重みで連続的に制御 | 精度が高い | 実装コストが高い |
本稿では固定ウィンドウ方式を採用し、Redisを分散カウンタとして利用します。
3. アーキテクチャ概要
-
Flask: APIエンドポイントを提供(
/api/test,/api/reset) - Redis: カウントとTTLを保持
- Docker Compose: FlaskとRedisを同時に起動
- クライアント: curlやNotebookからHTTPリクエストを送信
シーケンス図
リクエスト処理の時系列を詳細に示しており、Redisとのやり取りとレート制限の条件分岐(カウンタ値が閾値を超えた場合の429エラー)を明確にしています。固定ウィンドウ方式の特性として、ウィンドウ開始時にカウンタがリセットされるため、境界付近でのバースト発生に注意が必要です。
このアーキテクチャの利点は、Redisの原子性操作(INCRとEXPIRE)により、高速かつ分散環境で動作可能な点です。一方で、固定ウィンドウ方式の欠点として、ウィンドウ境界でのリクエスト集中(バースト)が発生しやすいため、実運用ではスライディングウィンドウへの移行を検討してください。
4. 実装のポイント(コード省略)
実装の主な流れ
-
クライアント識別
IPアドレスをキーに使用。
→rate_limit:{client_ip}:{window_start}形式で保存。 -
カウンタ操作
-
INCRでカウントアップ - 初回のみ
EXPIRE設定 - カウントが閾値 (
RATE_LIMIT) を超えると HTTP 429 を返却
-
-
レスポンスヘッダ
X-RateLimit-Limit: 最大リクエスト数 X-RateLimit-Remaining: 残り回数 X-RateLimit-Reset: リセット時刻 -
例外パス
/healthや/api/resetは制限対象外。 -
運用補助
/api/resetで Redis のキーを削除し、開発検証を容易に。
5. ローカル環境構築(Docker Compose)
services:
app:
build: ./app
ports: ["8000:8000"]
environment:
REDIS_HOST: redis
RATE_LIMIT: "5"
WINDOW_SECONDS: "60"
depends_on: [redis]
redis:
image: redis:7-alpine
ports: ["6379:6379"]
6. 検証:Notebookで挙動を可視化
Jupyter Notebook(rate_limiter_test.ipynb)で自動的に連続リクエストを送信し、
ステータスコード・残り回数・リセット時刻を可視化します。
代表的な挙動:
- 最初の5回:HTTP 200
- 6回目以降:HTTP 429
- ウィンドウリセット後:再び許可
これにより、**固定ウィンドウ方式の境界問題(バースト現象)**を実際に観測可能です。
7. 設計上の注意点と運用の勘所
| 項目 | 解説 |
|---|---|
| 原子性 |
INCR と EXPIRE を別コマンドで実行すると TTL が設定されない可能性あり。Luaで改善可能。 |
| 時刻同期 | サーバ時刻がずれると誤判定が発生。NTPによる同期が必要。 |
| Redis可用性 | 本番では Sentinel / Cluster / ElastiCache を検討。 |
| バースト対策 | スライディングウィンドウまたはトークンバケット方式へ拡張を推奨。 |
| 監視・メトリクス | Redis応答時間・429発生率をPrometheus/Grafanaで可視化。 |
| エッジ制御 | API Gateway や CDN レイヤーでの早期拒否も有効。 |
8. まとめと今後の発展
学びの要点
- Flask + Redis による固定ウィンドウ型レートリミッターを構築。
- 分散環境下での一貫した制限を Redis の原子操作で実現。
- HTTPヘッダ・レスポンス挙動をJupyterで検証し、理論と実践を接続。
今後の改善案
- Luaスクリプトで
INCR+EXPIREの一括原子処理化 - トークンバケット/スライディングウィンドウ実装
- Redis Clusterによる高可用構成
- API Gatewayとの統合制御