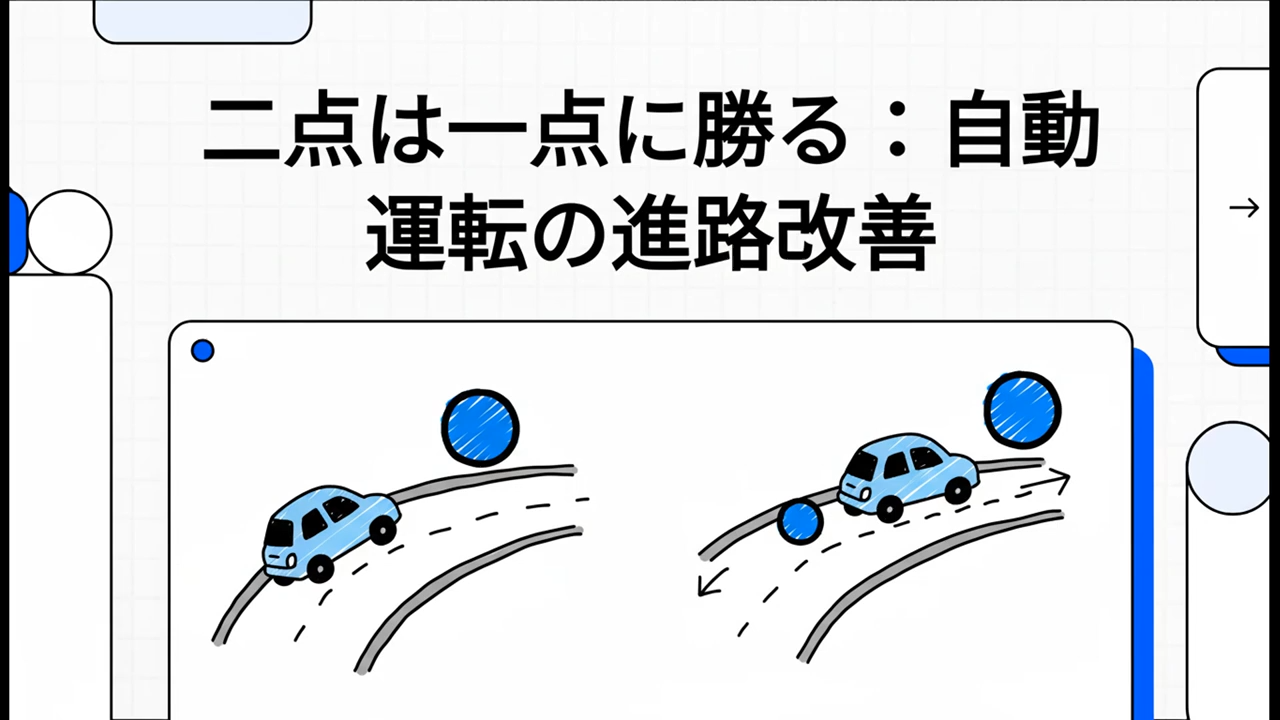はじめに
今年も自動運転AIチャレンジ2025に参加させていただいておりました。
実車決勝競技が去る10月25〜27日に開催され、7月1日より開始となったシミュレーション予選も含め全競技日程が終了しました。参加者の皆さま、お疲れさまでした。そして運営の皆さま、本当にありがとうございました。
弊チームは、一般部門1位(暫定) という結果で決勝を終えました。
学生部門1位のSSHさんには0.8秒差で負けてしまい、惜しくも総合優勝は逃してしまいましたが、良い結果を残すことができました。
さて、総合的な振り返り・技術紹介は別途チームリーダーが絶賛作成中!ですが、
先んじて、弊チームが採用した制御則 2点注視Pure Pursuit を理論的に分析した論文 「Pure Pursuit法の改良の検討(二点注視点法:Dual Preview Points法による軌道追従系の分析)」 を紹介しようと思います。
前置き : Pure Pursuit と 決勝における我々の工夫
そもそもPure Pursuitとはなにか?という話ですが、軌跡追従制御の1手法で、計算量が少なく実装も容易でありながら一定の追従性能を実現する制御として知られており、自動運転AIチャレンジでもデフォルト制御として採用されています。
弊チームでは昨年、このPure Pursuitを拡張した 「2つの前方注視点を使うPure Pursuit」 の実装に挑戦していました。以下記事です、Pure Pursuitの原理についてわかりやすいリンクも用意していますのでご参考まで。
実は昨年の決勝競技では採用を見送っていたこの「2点注視Pure Pursuit」ですが、今年の決勝競技で採用しています。この意思決定に至った背景の1つが、本記事で紹介する分析論文となっています。
関連事例: 高校生チームのPure Pursuit活用
昨年度、唯一の高校生チーム(!)として決勝の舞台に立った 「EIPIII NEXUS」さん の記事でも、Pure Pursuitが取り上げられています。
高校生がPure Pursuitを応用して実装した曲率ベース速度制御【自動運転AIチャレンジ】
前方の曲率に応じた速度制御も併せて行っており、非常に完成度の高い制御設計でした。
(我々も似たアプローチを採っていますが、詳細は別記事で紹介予定です)
論文紹介 : Pure Pursuit法の改良の検討
さて前置きが長くなりましたがここからが本題です。
自動運転などの軌跡追従制御でよく用いられるPure Pursuit法ですが、その改良手法のひとつである 2点注視点法(Dual Preview Points法) を理論的に分析した以下論文が2025年に発表されました。
「Pure Pursuit法の改良の検討(二点注視点法:Dual Preview Points法で実現される軌道追従系の分析)」, 王ら, 日本機械学会論文集, 2025年
本記事では、本論文で示されている2点注視点法の制御特性を簡単に紹介します。なお細心の注意は払っておりますが、一部意訳をしていたり、私の知識が不足している部分が多々あるため、理解を深めたい方は元論文を精読いただければと思います(HiICSさん等々、制御のプロがいらっしゃるので怒られそうでビビっています)。
1. Pure Pursuit法が抱える課題
Pure Pursuit法(PP法)は、実装の容易さと計算負荷の低さから、自動運転の制御で広く使われてきました。この手法は、車両の少し前にある目標点(前方注視点)を定めて、そこに向かって曲がる、というシンプルな原理に基づいています。
PP法の課題 : 制御特性のトレードオフ
しかし、PP法の性能は「前方注視距離」の設定値に依存し、以下のようなトレードオフが存在します。
- 応答性を高めたい場合: 注視距離を短くする必要があります。しかし、その結果、安定性が損なわれやすくなります
- 目標軌道の急な変化へ対応したい場合: 注視距離を長くする必要があります。しかし、その結果、目標軌道に対する追従の応答性が低下します(オーバーシュートやアンダーシュートが発生する)
※ コメント: これはPure Pursuitの調整をしたことがある人は納得いただけるかなと思うのですが、(1)注視距離を短くするとキビキビ動くがフラフラする、(2)注視距離を長くするとゆったり動くがショートカットが発生する、ようなトレードオフの理解で良いかなと思います。
原因 : 減衰特性の固定化
車両が目標軌道の近くを走っている時の挙動を分析すると、PP法による追従系は、バネ・マス・ダンパーで構成された単純な振動システム(二次の1自由度振動系)としてモデル化できます。
このモデルを解析すると、以下のように、実現される追従系の動特性に性能限界が存在することが示されます。
- 応答の速さ(固有振動数 $\omega_n$) は、$\sqrt{2}/T_p$となり、前方注視時間 $T_p$ に応じて一意に定まります
- 揺れの収まりやすさ(減衰比 $\zeta$) が、制御パラメータでは変えられず、システム構造によって $\mathbf{1}/\sqrt{2}$ に固定されてしまいます
この$\zeta = 1/\sqrt{2}$という固定された特性により、前述のトレードオフが発生しています。
2. 解決策 : Dual Preview Points法(DPP法)
この性能限界を克服するため、PP法の利点(実装の容易性、低コスト)を維持しつつ提案されたのが、 Dual Preview Points法(DPP法) です。
解決の仕組み : 注視点を2つに増やす
DPP法では、車両の前方に 2つの異なる前方注視点($P_1, P_2$) を設けます。
これにより、制御に使えるパラメータ(前方注視距離やゲイン)が増え、システム設計の自由度が向上します。
最も重要な結果として、DPP追従系では:
- 応答性(固有振動数 $\omega_n$)
- 安定性(減衰比 $\zeta$)
を一定の制約の中で、独立に設計し、個別に設定できるようになります。これは従来のPP法では実現不可能でした。
なぜ二つの点で特性が変わるのか?
DPP法がシステムの動特性を自由に設定できるようになった理論的な理由は、「2つの前方注視点の横偏差の動特性の違いを利用している」 ためです。
DPP追従系のブロック図を解析すると、従来のPP追従系の構造に対して、「ハイパスフィルタ」 という信号処理機構が新たに付加された形に等価変換できることが示されています。
この「ハイパスフィルタの追加」こそが、システムの減衰特性を調整する新たな自由度となり、応答性と安定性のトレードオフを解消した鍵となります。
おまけ : 「論文難しくて読めない…」と思ったあなたへ
安心してください、NotebookLM がいますよ。
このNotebookLMに論文をアップロードすると、
- 要約
- 対話型の質問応答
- 音声・動画での解説
までAIが実施・対応してくれます。
学術論文理解のハードルがどんどん下がっていますね、本当に便利な世の中です。
ただし、ハルシネーションの可能性があるので、詳細はご自身で再チェックいただくなど、生成AIの特性を理解して利用ください。
NotebookLMでのまとめ例
私も以下を利用して理解を深めました。
おわりに
今回は、弊チームが自動運転AIチャレンジにて採用した「2点注視Pure Pursuit」を理論的に分析した論文 「Pure Pursuit法の改良の検討(二点注視点法:Dual Preview Points法による軌道追従系の分析)」 を紹介しました。理論に裏付けられた制御特性を知ることで、本競技における制御設計・パラメータ調整の指針とすることができました。
また自動運転AIチャレンジは、このように、学術的な研究成果を応用する場としても機能してきており、業界として非常に良い取り組みであると感じます。改めて運営の皆様には感謝申し上げます、ありがとうございました。また来年も参加できたらいいなと思っています。
※ 弊チームの総合的な振り返り・技術紹介はもう少々お待ちください!
この記事は、AI文章校正ツール「ちゅらいと」で校正されています。
ちょっとだけ、ポエム・お気持ち表明を添えて…
ちなみに、アツい戦いを繰り広げた学生部門1位/総合優勝のSSHさんによる「自動運転AIチャレンジの魅力」記事がこちらです。
とても良いことが書いてあります。自動運転システムをシミュレーションで開発し、実車へデプロイして動かす体験は、そうそうできるものではないと思います。
学生の皆さんには、この貴重な機会を最大限に活かしていただき、本大会コンセプトにあるように「これからの自動車業界を(日本を)牽引」していってほしいと願っています。
私の記事が、その挑戦の道のどこかで、ほんの少しでも力になれていたら嬉しいです。