導入
今回は、Qiita Engineer Festa 2024のアプリケーション開発に注力するための工夫をシェアしよう!のテーマを見て、「普通はソフトウェアやツールの観点で、開発に注力する工夫を書くよなぁ」と思いながらも、「それだと他の人も同様な観点で記事を作成するだろう」と思い、私としては、自身の 「自作キーボードの紹介」 と 「昇降デスクの活用」 という2つの工夫について紹介することにしました。
※本記事はQmonus Value Streamの投稿キャンペーン記事です。
導入(その2)
アプリケーション開発は、長時間にわたる集中と繊細な作業を伴う仕事です。
しかし、開発者としてのキャリアを長く続けるためには、ただ効率の追求だけでなく、健康的な作業環境を構築することが不可欠です。
長時間の座り作業は、肩こりやそれに伴う頭痛、腰痛、手首の痛みなどの体調不良を引き起こすことがあり、生産性や集中力に悪影響を及ぼします。
どんなに自動化ツールであったり、開発生産性を向上させるシステムを導入しても、体調不良で作業ができなくては元も子もありません。
私自身、実際に体調の問題から効率が落ちることを経験してきました。
特に私は姿勢が悪く、ストレートネック気味であるため、肩こりと頭痛に悩まされることがしばしばありました。
(というか今回の工夫を行なっても不調な日はあったりしますが...)
そこで、体の負担を軽減し、健康的に作業に集中できる環境を整えるために、私が実践している「自作キーボードのカスタマイズ」と「昇降デスクの活用」という2つの方法を紹介していきます。
自作キーボード
自作キーボードとの出会い
初めての自作キーボードは、友人の紹介で始めました。
当時は特に健康面が理由で始めたわけではなく、 「自作」 という言葉に惹かれて始めたと記憶しています。昔からはんだ付けや物理的に物を作るのも好きだったので、とりあえずやってみたのがきっかけです。
パーツを組み立てながら、少しずつ自分の使いやすいキーボードが完成していく過程は、大変面白く、今でも楽しめています。
自作キーボードのココが良い!
【自分仕様のキー配置 1.自由なカスタマイズ】
自作キーボードの最大の利点は、キーの配置や機能を自由にカスタマイズできる点です。
例えば、私はタイプミスを減らすために、一般的なキー配置を変更しています。
そもそもタイプミスが多いことも問題なのですが、「BackSpace」がすぐに押せる位置に変更したのは、一つ開発をスムーズにしているように感じます。
具体的には、左手の親指の位置に「Del」を、右手の親指の位置に「BackSpace」を配置しています。
この配置により、タイプミスが発生した際に、すぐに修正できるようになりました。
【自分仕様のキー配置: 2.Macのショートカットも楽々】
Macを使用する際、Dockを開くショートカットは「^ control + F3」です。このショートカットが使いづらかったため、私は「F3」を「Fn + Cキー」に再割り当てしました。
これにより、より自然な手の動きでDockを呼び出せるようになり、生産性が向上しました。
【キースイッチの選定】
キースイッチの選定にもこだわることができます。
プライベートPC用には少し打鍵感のある茶軸、仕事PC用には静かな赤軸、と小指の位置には押しやすい白軸を採用しています。
これにより、長時間のタイピングでも疲れにくくなっているはずです。
【分割キーボード】
私は中古で購入した「ErgoDash」という基盤を使用しています。
この基盤は左右のキーが分かれた「分割キーボード」に属する基盤で、左右でそれぞれマイコンが付いています。
これらはケーブルでつながっており、ケーブルの長さを調節することで、左右の手の間隔を広げることが可能になります。
通常の1本のキーボードは左右の手の間隔が狭く、腕や肩が内側に入り込むような姿勢になります。
一方、分割キーボードを利用すると、左右の間隔を広く取ることができ、良い姿勢を維持することに役立ちます。
【ソケット化】
この基盤は通常、キースイッチをはんだ付けしますが、私はスイッチを容易に交換できるようにソケット化しました。この作業には約140本のソケットを取り付ける必要がありましたが、その結果、いつでもスイッチを交換できるようになりました。ソケット化により、キーボードのメンテナンスが容易になり、常に快適な打鍵感を保てるようになりました。

【RGB LEDで気分転換?】
これはお遊びです。
私のキーボードにはゲーミングPCのキーボードのようにRGB LEDも搭載しています。
カラフルに光るLEDは、作業中の気分転換にぴったりです。
光のパターンや色を変えることで、作業環境に応じた雰囲気を作り出しています。
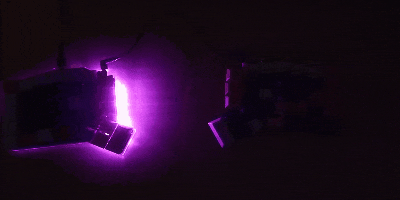


...
......
ただ、全く開発に注力できる要素ではありませんね。
次の目標:特定のキーでQiita起動
以前こちらの記事でも紹介している通り、Macのショートカットをカスタマイズすることで、特定のキーを押下して特定の処理を実行することができます。
今後の目標として、キーキャップを「Qiita Engineer Festa 2024」の完走賞としていただけるキーたんのキーキャップに変更し、そのキーを押すと「Qiita」が起動するように設定しようと考えています。
昇降デスクの活用
商品説明
次に紹介するのは、昇降デスク「FlexiSpot EJ2 2.0」です。
このデスクは、座ったり立ったりしながら作業ができるよう、自由に高さを調節することができます。
特に長時間のデスクワークでは、姿勢を変えることで疲労を軽減し、集中力を維持することができます。
公式のイメージ写真
以下の「実際の様子」に私が実際に使用しているデスクの写真を載せていますが、公式の写真の方が綺麗なので、載せました。

実際の様子
昇降デスクのココが良い!
【高さ調整で健康的な作業環境】
FlexiSpot EJ2 2.0は電動で高さを調整できるため、簡単に最適な作業姿勢を取ることができます。
例えば、座り作業と立ち作業を交互に行うことで、腰痛や肩こりを防ぐことができるだけでなく、長時間の集中作業にも適しています。
もちろんEJ2 2.0以外のFlexiSpot社の昇降デスクでも大半が電動で高さ調節できます。
【高さメモリ機能】
FlexiSpot EJ2 2.0には高さメモリ機能があります。
これは、数パターンの高さを記録しておくことができ、「上下」ボタンではなく「記録済み」ボタンを押すことで、設定された高さに机の高さを上下してくれる機能です。
これのおかげで、すぐに適当な高さに机を調整してくれます。
席を立って戻ってきたときに立って作業しようかな、と思ったときには、席を立つ前にボタンを押しておけば、戻ってきたときにすぐに作業を開始することができます。
最後に
自作キーボードと昇降デスクを活用することで、アプリケーション開発における効率と快適さを大いに向上させることができています。
カスタマイズ可能なキーボードにより、個々の作業スタイルに最適化された操作性を実現し、昇降デスクの導入により、健康的な作業環境を維持することができています。
皆さんもぜひ、自分に合った環境づくりに挑戦してみてもらえたらと思います!



