この記事は技術広報 Advent Calendar 2022の20日目の記事です。
ごめんなさい、タイトルは釣りです。そんな方法があれば私も知りたいです。
今年読んだとても良い本『エンジニアリングマネージャーのしごと ―チームが必要とするマネージャーになる方法』を真似しました。
こんにちは、molmolkenです。KLab株式会社の技術広報グループ(以下、技術広報G)でマネージャをしています。
KLab株式会社はモバイルオンラインゲームを開発している会社で、代表作には
などがあります。
KLab 技術広報G が2022年に行った活動の紹介
今年、KLabの技術広報Gは様々な活動を行いましたが、中には一般的な技術広報の活動からは少し外れたものもありました。
本記事では、それらを「社外広報」「社内広報」「(技術)コミュニティマネジメント」「タレントマネジメント」という4つの分類で紹介したいと思います。
「他社の技術広報はこんな活動をしているんだ」という参考にしてもらえれば幸いです。
1. 社外広報
「技術広報」と聞いたときに多くの方が想像するのは、いわゆる社外広報ではないでしょうか。
テックブログやmeetup(カンファレンス)の開催、アドベントカレンダーなども社外広報にあたります。
社外広報活動については、他社が行っている内容とそれほど変わらないと思うので、ざっくりやったことだけを記載します。
テックブログの運営
KLablog Technologyという名称でブログを運営しています。2022年は16記事を公開しました。
参考までに公開後、一定期間のPV数が特に多かった記事の紹介です。
Meetupの開催
不定期でKLab TECH Meetupという勉強会を開催しています。2022年は2回開催しました。
参加者に少しでも興味を持ってもらえるよう、毎回タイトルを工夫しています。
アドベントカレンダー
KLabでは2015年から毎年アドベントカレンダーの取り組みを行っています。
社外イベントへの登壇サポート
エンジニアが社外イベントに登壇する際に、資料のレビューやリハーサルを実施してサポートしています。
論旨のわかりづらさや資料中のタイポ、固有名詞の表記ゆれなどは気付きにくいため、第三者のレビューがあると安心です。
2022年はAWS Summit Online 2022や、Unity SYNC、CEDEC+KYUSHU 2022( 1⃣ / 2⃣ )に登壇するメンバーをサポートしました。
イベントスポンサー
今年は人事部の採用チームと連携し、ISUCONや技術書典といったイベントでのスポンサーの取り組みの一部を手伝わせてもらいました。
#KLab はシルバースポンサー & 食事クーポン提供をさせていただいています! #isucon 本選中は忙しく余裕がないと思いますので、ぜひ終わった後の反省会や打ち上げなどでご利用ください!
— KLab技術広報 (@klab_tech) August 27, 2022
#KLab は技術書典13をサポーターとして応援しています!
— KLab技術広報 (@klab_tech) August 31, 2022
また、KLab Tech Book Vol. 10を頒布予定です。詳細は近日中に発表します。#klab_tech #技術書典 https://t.co/a3Ct5RP9zh
2. 社内広報
KLabの技術広報Gは社『外』広報だけでなく、社『内』広報も行っています。
もちろん、(技術でない通常の)広報も社内広報活動は行っていますが、エンジニアリングに造詣が深い技術広報だからこそできる情報発信があります。
エンジニア全体ミーティングの開催
2021年末より毎月、エンジニア社員の全体ミーティングを開催しています。
コロナ禍でKLabはリモートワークとなり、それまで社内で自然発生していたエンジニア同士の雑談や情報共有が著しく減ってしまいました。
また、マネージャ層とプレイヤー層の精神的距離も広がってしまったように感じます。
そのような状況を改善すべく、以下を目的として開催しています。
- ボードメンバーやマネージャ層が考えていることをエンジニア全体に共有する
- ゲーム開発プロジェクトや横断組織での取り組みを紹介する
- エンジニアメンバーの疑問を取り除く
運営は技術広報Gだけでなく、CTO室(のような部署)やエンジニア有志メンバーと協力し、企画~実施~振り返りまでを一括で行っています。
情報発信や技術広報の重要性を布教する活動
KLabに技術広報Gが結成され、はや3年となりますが、技術広報活動の重要性はまだまだ社内に浸透しきっているとは言えない状況です。
そのため、社内の勉強会や新卒研修にて、情報発信を行うとどのようなメリットがあるかを説明したり、技術広報Gの活動内容をまとめた資料を社内全体に公開するなどの活動を行いました。
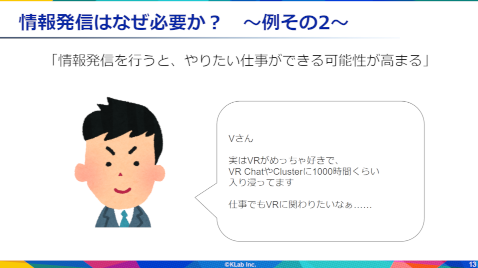
3. (技術)コミュニティマネジメント
3つ目はエンジニアに関するコミュニティマネジメントです。
社内のエンジニア同士のネットワーキングや交流促進を目的としたイベントを開催しています。
上述したように、リモートワーク下でコミュニケーションが減ったことにより、それまで生まれていたエンジニア同士のコラボレーションが減ったり、仲間意識の強さにより保たれていた組織エンゲージメントが低下したりといった問題が発生しました。
これらの活動はいわゆる一般的な「技術広報の取り組み」からは少し外れますが、技術広報Gのメンバー自身がネットワーキングを行うことにより、テックブログや登壇の依頼が行いやすくなるという明確なメリットがあります。
社内ゲームジャム
KLabでは昔からゲームジャムの取り組みが盛んで、2014年ごろから毎年2~3回のペースで社内ゲームジャムを開催しています。
(たまに社外向けにも行っていましたが、基本は社内向けです)
コロナ以前は会社のミーティングルームに集まって行っていたのですが、コロナ禍以後はリモートでの開催となりました。
下記の記事には実際に遊べるゲームも載っていますので、興味がある方はぜひご覧ください。
もくもく会
2022年になると、コロナの感染者数も多少落ち着く時期がでてきたので、そのタイミングを狙ってオフラインのもくもく会を開催しました。
やはりリアルに対面すると雑談が捗りますし、会の最後に発表タイムを設けることにより発表駆動開発で進捗も出るため、とてもオススメです。
コロナ禍以後に入社したメンバーが 「AIじゃなくて本当に実在したんですね……」 と言われていたのが印象的で面白かったです。
4. タレントマネジメント
最後となる4つ目はタレントマネジメントです。
本来のタレントマネジメントと比べると規模も目的も小さいですが、エンジニアメンバーがどういった技術スタックを持っているか、どんな技術に興味があるかを知ることで、テックブログや登壇の依頼に役立てています。
Tech ML、全部読む
KLabには誰でも自由に送れるエンジニアリング系のメーリングリスト(通称:Tech ML)があり、毎年300~400件ほどのメールが送られています。
メンバーによっては評価目標の1つとなっていたり、四半期ごとのアワードの対象にもなっているため、MLへの発信が非常に盛んです。
内容としては、業務での技術的取り組みや成果の紹介だけでなく、趣味プログラミングの話や、勉強会/イベントの勧誘など、多岐にわたっています。
技術広報Gでは毎週の定例でメーリングリストに送られたメール全てに目を通し、「これはぜひテックブログで社外に発信してほしい」「次のmeetupではXXさんに登壇してもらいたい」 といった目線で活用しています。
カンファレンスの受講取りまとめ
GDC(Game Developers Conference)やCEDECといったゲーム開発系のカンファレンスの受講希望者を募り、一括でチケット購入や支払いを行っています。
これはもちろん事務作業の効率化という側面もありますが、社内のプロジェクトや横断部署から満遍なく受講者を出すことで情報格差をなくす目的もあります。
また、情報のインプットが盛んな人はアウトプットできるネタも多いので、カンファレンスの受講者はそのまま情報発信予備軍としてマークできますし、受講者が提出したレポートからどんな技術/プロセス/プロダクトに興味があるのか、文章力や構成力がどれくらいあるのかを把握できるというメリットもあります。
まとめ
以上のように、2022年のKLab 技術広報Gは一般的な「技術広報活動」以外にも様々な取り組みを行いました。
中には「それって本当に技術広報がやるべきことなの?」と思われてしまいそうな取り組みもありますが、どれも少なからず、テックブログやmeetup開催といった技術広報本来の活動に役立っています。
一方で正直な話、手を広げすぎている感もあり、1つ1つの成果は薄まってしまっています。
もう少しフォーカスを絞って活動した方が、総合的なパフォーマンスは向上する可能性があります。
現在、2023年の活動内容を策定している真っ最中なので、そちらについては続報をお待ちください。
最後に宣伝
KLabの技術広報GのTwitterアカウント(@klab_tech)があります!まだまだ認知度が低くフォロワーが非常に少ないです!
今年中にフォロワー200人いかないと上司にしばかれます!助けてください!
よかったらフォローをお願いします!

