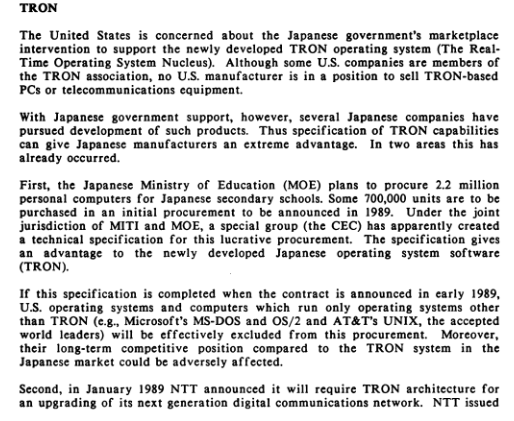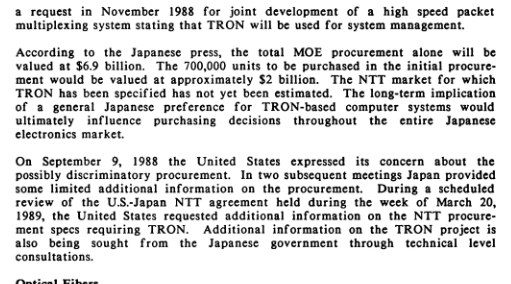はじめに
1989 年、米国通商代表部 (USTR) は 2 つの市場(「教育用パソコン」と「NTT の次世代デジタル通信ネットワーク」)が TRON プロジェクトに有利なものになっているとして、TRON をスーパー 301 条の制裁対象の候補に指定し、この 2 つの市場に米国企業が参入できるようにしろと圧力をかけました。
↑ これが「米国はなんと言ったのか?」の簡潔な答えなのですが「米国が日本の技術が広まることを恐れて TRON プロジェクトから手を引けと脅しをかけた」みたいなデマが広まっているようです。別に米国は日本の技術なんか恐れていませんよ? 日米の貿易摩擦は貿易の話で「米国の製品を日本で売らせろ」という話で、そもそも「日本が米国の技術を恐れて米国の技術が普及しないように日本から締め出そうとした」のが発端です。デマが広まるのは USTR がなんと言ったのかが広まっていないからというのが大きいと思うので、この記事で実際になんと言っていたのかを広めたいと思います。
とまあ、記事としての体裁を整えるために、いろいろ話を付け足していますが、この記事は、TRON がスーパー 301 条に名指しされた件で、実際に USTR はなんと言ったかと、その日本語訳を、他の記事から参照しやすくするために独立させたものです。(当時の)スーパー301条は 1989 年と 1990 年の 2回が予定されていました。下記はそれに対応する USTR の外国貿易障壁報告書(+1991年版)です。それ以外の年の外国貿易障壁報告書へのリンクはこちら。
- 1989 National Trade Estimate Report on FOREIGN TRADE BARRIERS
- 1990 National Trade Estimate Report on FOREIGN TRADE BARRIERS
- 1991 National Trade Estimate Report on FOREIGN TRADE BARRIERS
関連記事
スーパー301条とは
スーパー301条とは、不公正な貿易慣行を行う国を特定し制裁措置(関税引き上げなど)を講じることを可能にする条項です。これは日本を脅して新技術の開発から手を引けと迫るようなものではありません。つまり、「輸出制限などで脅しをかけて TRON プロジェクトから手を引くことを迫る」ようなものではありません。
米国は TRON プロジェクトから手を引けなんて要求してません。そもそも当時にパソコン用の TRON (BTRON) をまともに開発していたのは松下電器だけで(猛反対した NEC を除いて)国内のパソコンメーカーは様子見でした。松下電器が BTRON 開発から撤退し、他のパソコンメーカーは蜘蛛の子を散らすように去っていきました。BTRON の開発は(松下通信工業を経て)パーソナルメディア社に引き継がれましたが 2006 年頃より開発は停滞しています。また、米国は TRON プロジェクトに参加させろとも言っていません。実際になんて言ったかは「外国貿易障壁報告書」に書かれています。
外国貿易障壁報告書とは、その名の通り貿易の「障壁」となっている項目の報告書です。これは貿易相手国(米国から見て日本など)が持つ市場参入の障壁要因を項目別に洗い出したものです。いきなりスーパー301条に指定して制裁(関税引き上げなど)を行うようなものではなく、まず USTR が調査し「◯◯◯が貿易の障壁となっています」と外国貿易障壁報告書で報告し、制裁対象国と協議を行ってから制裁対象とするかを決めます。協議は12ヶ月(知的所有権は6ヶ月)行われ、およそ 1年後に制裁対象が決定され、制裁措置が実施されるという予定でした。(参考 双子の赤字とスーパー301条 : 日米摩擦の諸相)
1989年 外国貿易障壁報告書
1989年4月28日に、USTR は 1 回目の外国貿易障壁報告書が発表しました。TRON は名指しされたと言われますが、実際にはTRON は障壁があるとされた 34 項目のうちの 1 つに過ぎません。この時の障壁とはどのような意味であるかは、下記の実際の外国貿易障壁報告書を読んでください。重要な箇所は太字にしています。
英語の原文(リンク先が消えたときに備えてのバックアップ)
TRON
The United States is concerned about the Japanese government's marketplace intervention to support the newly developed TRON operating system (The Real-Time Operating System Nucleus). Although some U.S. companies are members of the TRON association, no U.S. manufacturer is in a position to sell TRON-based PCs or telecommunications equipment.
With Japanese government support, however, several Japanese companies have pursued development of such products. Thus specification of TRON capabilities can give Japanese manufacturers an extreme advantage. In two areas this has already occurred.
First, the Japanese Ministry of Education (MOE) plans to procure 2.2 million personal computers for Japanese secondary schools. Some 700,000 units are to be purchased in an initial procurement to be announced in 1989. Under the joint jurisdiction of MITI and MOE, a special group (the CEC) has apparently created a technical specification for this lucrative procurement. The specification gives an advantage to the newly developed operating system software (TRON).
If this specification is completed when the contract is announced in early 1989, U.S. operating system and computers which run only operating systems other than TRON (e.g., Microsoft's MS-DOS and OS/2 and AT&T's UNIX, the accepted world leaders) will be effectively excluded from this procurement. Moreover, Japanese market could be adversely affected.
Second, in January 1989 NTT announced it will require TRON architecture for an upgrading of its next generation digital communications network. NTT issued a request in November 1988 for joint development of a high speed packet multiplexing system stating that TRON will be used for system management.
According to the Japanese press the total MOE procurement alone will be valued at \$6.9 billion. the 700,000 units to be purchased in the initial procurement would be valued at approximately $2 billion. the NTT market for which TRON has been specified has not yet been estimated. The long-term implication of a general Japanese preference for TRON-based computer systems would ultimately influence purchasing decisions throughout the entire Japanese electronics market.
On September 9, 1988 the United States expressed its concern about the possibly discriminatory procurement. In two subsequent meetings Japan provided some limited additional information on the procurement. During a scheduled review of the U.S.-Japan NTT agreement held during the week of March 20, 1988, the United States requested additional information on the NTT procurement specs requiring TRON. Additional information on the TRON project is also being sought from the Japanese government through technical level consultations.
TRON
米国合衆国は、日本政府が新たに開発された TRON オペレーティングシステム (The Real-Time Operating System Nucleus) を支援するために市場に介入していることに懸念を示している。TRON 協会には一部の米国企業も加盟しているが、TRON をベースとしたパソコンや通信機器を販売できる立場にある米国の製造業者は存在しない。
しかしながら、日本政府の支援のもとで、複数の日本企業がそのような製品の開発を進めてきた。そのため、TRON 機能の仕様は日本の製造業者に極めて大きな優位性を与える可能性がある。このような状況は、すでに 2 つの分野で発生している。
第一に、日本の文部省 (MOE) は、日本の中等教育機関向けに 220 万台のパーソナルコンピュータを調達する計画を立てている。そのうちおよそ 70 万台が、1989 年に発表される予定の最初の調達において購入されることになっている。通産省 (MITI) と文部省の共同管轄のもと、特別グループ (CEC) がこの利益の大きい調達に対する技術仕様を作成したと見られている。この仕様は、新たに開発されたオペレーティングシステムソフトウェア (TRON) に有利となっている。
1989 年初頭に契約が発表される際にこの仕様が完成している場合、TRON 以外のオペレーティングシステム(例えば Microsoft の MS-DOS および OS/2、ならびに AT&TのUNIX ― いずれも世界的に認められたリーダー)でしか動作しない米国のオペレーティングシステムおよびコンピュータは、事実上この調達から排除されることになるだろう。さらに、日本の市場にも悪影響を及ぼす可能性がある。
第二に、1989年1月、NTT は次世代デジタル通信ネットワークのアップグレードにおいて TRON アーキテクチャを必要とすることを発表した。NTT は 1988年11月に高速パケット多重化システムの共同開発を求める要請を出し、その中でシステム管理には TRON が使用されると述べている。
日本の報道によれば、文部省による全体の調達は 69 億ドルと見積もられている。初期調達で購入される 70 万台は、約 20 億ドルに相当する。また、TRON が仕様として求められている NTT の市場規模は、まだ算出されていない。日本国内で TRON ベースのコンピュータシステムが一般的に好まれるようになれば、その長期的影響として、日本の電子機器市場全体にわたって購買決定に影響を与える可能性がある。
1988年9月9日、米国合衆国は、この差別的である可能性のある調達について懸念を表明した。その後 2 回の会合で、日本はこの調達に関する限られた追加情報を提供した。1989年3月20日の週に予定されていた米日 NTT 協定の見直しの場において、米国は TRON を求める NTT の調達仕様に関する追加情報を要求した。TRON プロジェクトに関する追加情報は、日本政府との技術レベルでの協議を通じて、引き続き求められている。
補足解説1
「スーパー301条で TRON が名指しされた」とだけしか言っていない動画や書いていない記事ばかりですが、実際には次の 2 つの分野で障壁があると指摘されました。
- BTRON: 教育用パソコンをトロンパソコンに限定しようとした
- CTRON: NTT は次世代デジタル通信ネットワークをトロンに限定しようとした
BTRON (Business) とはビジネス用のコンピュータ(パソコン)のことで、CTRON (Communication and Central TRON) とは通信用またはサーバー用のコンピュータのことです。
教育用パソコンの問題とは、当時の通産省と文部省の共管であるコンピュータ教育センター (CEC) が、日本で広く使われていた PC-98 パソコンを無視し「未完成の BTRON パソコン」を教育用パソコン市場に導入しよう計画し、PC-98 パソコンを販売していた NEC が猛反対した事件です。通産省は PC-98 が MS-DOS を採用していたことが気に食わなかったため、国家権力を使って MS-DOS を PC-98 ごと排除しようとしていました。日本は米国の技術を恐れており、直接対決で負けるのが怖かったのです。
USTR の報告書を読んでわかるように「TRON プロジェクトから手を引け」と言っているわけではありません。気にしているのは日本の市場であって、日本の技術なんて気にもとめていません。TRON 以外の OS (例、MS-DOS、OS/2、UNIX)が調達から排除されることを気にしています。ついでに日本の市場にとっても悪影響がある(意訳: 日本でガラケーならぬガラパソが蔓延してしまう)と心配までされています。
米国は最初から一貫して「市場を気にしている」事がわかるでしょう。日本が米国で商売しているように、米国も日本で商売させろと言っただけの話です。
補足解説2: TRON 協会の的外れな反論
TRON 協会が反論とかやって成果を出した感を出しているのですが、おそらくあまり関係ないと思われます。なぜならこれは日本と米国、国と国との話し合いで、米国は「通産省と文部省の下部組織であるコンピュータ教育センター (CEC)」のやり方に文句をつけているわけで、直接の対応は CEC です。事実、米国政府はトロン協会の活動自体には反対していないと返答しています。TRON 協会サイトの(過去の)トロン沿革 と 通商問題経緯 ページより重要と思われる部分だけをまとめると次のようになります。
- 4月18日 朝刊各紙に「米国スーパー301条適用濃厚」と発表
- 4月28日 米国政府が米国議会に提出した外国貿易障壁報告書にトロンが含まれていた
- 新聞などで大々的に報道される
- 4月29日 「米国政府の貿易障壁年次報告に関する見解」を報道各紙へ送付
- 5月22日 米国 USTR ヒルズ代表あてに文書にて抗議を行う(トロン憲章を添付)
- 5月25日 スーパー301条の対象品目からはずされた
- 6月12日 米国 USTR ヒルズ代表より5月22日の抗議文に対する返答
- 6月28日 新聞などで「教育用パソコンに BTRON 採用断念」との報道
トロン協会は教育用パソコン市場の閉鎖性ではなく、TRON プロジェクト自体にしか焦点を当てていません。トロン協会(TRON プロジェクト)は教育用パソコンと直接関係ない話ので当然と言えば当然なのですが、だったらなぜ無関係のトロン協会が反論したんだろう?と考えるべきようなものです。おそらく当時の新聞発表の内容などから「米国が TRON プロジェクトに反対していると勘違いした」のでしょう。5月22日の USTR への抗議内容とトロン憲章の内容は次の通りです。
■ 抗議内容
- トロンは世界に開かれたオープンアーキテクチャである。
- トロン協会は開かれた機関であり、誰でも会員になることができる。
- トロン仕様書は公開され、誰でもこれに準拠した製品化をすることができる。
■ トロン憲章
- トロンは坂村健博士により提唱されたコンピュータのオープンアーキテクチャであり、トロン仕様書は、全世界の誰にでも公開する。
- トロン仕様書の著作権は、トロン協会に帰属する。トロン仕様書に準拠する製品化のために、誰でもトロン仕様書を利用することができる。
- トロン仕様書の作成、仕様適合性の検証、その他トロンプロジェクトの推進に関する中核機関としてトロン協会が設立されている。トロンプロジェクトの目的に賛同し、所定の規約に従うものは、世界中の誰でもトロン協会の会員になることができる。
とまあ、いくらこんな反論しても、教育用パソコン(と NTT次世代デジタル通信ネットワーク)市場の閉鎖性への反論にはなっていないわけで意味がありません。TRON 協会は「誤解だ」と言って USTR に抗議したわけですが、誤解しているのはむしろ TRON 協会です。なので 6月12日の USTR からの抗議文に対する返答は当然と TRON 協会の誤解を解くような内容になっています。
米国政府はトロン協会の活動に対して反対するものではない。 しかしながら日本政府が実質的及び潜在的に市場介入することによって トロンを援助することに関心を持っている。 政府の命令によってではなく市場の力によって、 どのOS・マイクロプロセッサ及びコンピュータアーキテクチャが 成功するかが決定されるべき。 トロン以外の単一の OS が作動するコンピュータは、 (財)コンピュータ教育開発センター(CEC)の仕様に合わないし、 トロン以外の単一の OS が動く PC の試作機は (CEC) には採用されなかった。
この通り、米国政府は TRON 協会の活動に反対していません。米国政府が反対しているのは通産省と文部省の共管である CEC のやり方なわけで、CEC は教育用パソコンを BTRON に統一するのを断念しました。このときに日経新聞などは「BTRON 採用断念」という見出しで報じており(内容を読めば「統一」を断念したとわかる)、そのため、後日 CEC は採用を断念したわけではないと声明をだしたようです。
トロン協会は5月22日に反論を行い同月中に誤解を解いたと主張していますが、USTR が発表した4月28日の「外国貿易障壁報告」から30日以内に行うことが決まっていた「優先交渉国と優先交涉項目(不公正な貿易慣行) を特定する作業」で対象とならなかったに過ぎません。日本で対象となったのは、スーパーコンピュータ、人工衛星、木材加工品の貿易 の 3 項目のみです。つまり、TRON はスーパー301条の制裁対象の候補に指定され、後に外されましたが、それは教育用パソコンの BTRON 統一を断念すると国が決めたからです。もちろん、米国は TRON プロジェクトからの撤退を要求したわけではないので、引き続き BTRON ベースの教育用パソコンを開発しても構いません。TRON パソコンの開発が禁止されていない証拠に、松下通信工業は BTRON ベースの教育用パソコンを開発しました。各パソコンメーカーが TRON パソコンの開発から撤退したのは、米国が脅したからではありません。
各パソコンメーカーが BTRON パソコンの開発から撤退したことを、坂村氏は「BTRON 採用断念」と騒ぎ立てた新聞やマスコミのせいにしているようですが、CEC は BTRON ベースの教育用パソコンを断念したわけではないと公表してますし、新聞やマスコミが間違った情報で騒いだ程度で BTRON 開発から撤退するとは思えないですよね? 話は単純で、各パソコンメーカーが撤退した理由は、教育用パソコンが BTRON で統一できないのであれば、BTRON を採用しても意味がないと思ったからです。元々各パソコンメーカーが BTRON を採用しようと思った理由は、当時に大きなシェアを持っていた NEC(日本電気株式会社)のパソコン、PC-98 シリーズに対抗するためです。しかし、それは NEC への対抗策の一つでしか無く、本気で BTRON 開発に取り組もうとはしていませんでした。その証拠に BTRON OS を開発していたのは松下電器だけです。教育用パソコンが BTRON パソコン限定になれば膨大な PC-98 用の資産(アプリおよび周辺機器)がリセットされ、シェア争いをスタートからやり直せると考えていましたが、教育用パソコンが BTRON パソコンでなくてもよいなら、当然 NEC は PC-98 パソコンにするわけで、そうなったら PC-98 シリーズと互換性がない BTRON パソコンを作っても勝ち目がありません。BTRON の開発から撤退し、世界標準の PC 互換機(AX 規格や DOS/V を含む)に乗り換えるのは合理的な判断です。
参考: 障壁となった全34項目
-
IMPORT POLICIES(輸入政策)
- Tariffs(関税)、Cigarettes and Tobacco Products(シガレットとタバコ製品)、Leather and Leather Footwear(革と革靴)、Wood and Paper Products(木材と紙製品)、Aluminium(アルミニウム)、Agricultural Products(農産物)、Feedgrains(飼料用穀物)、Rice(コメ)、Fish Products(水産物)
-
STANDARDS, TESTING, LABELING, CERTIFICATION(基準、試験、ラベル、認証)
- telecommunications Terminals, Radio Equipment and Systems(通信端末と無線機器とシステム)、Pharmaceuticals/Medical Device(医薬品と医療機器)、Food Additives(食品添加物)
-
GOVERNMENT PROCUREMENT(政府調達)
- Supercomputers(スーパーコンピュータ)、Satellites(衛星)、Government Procurement Code Implementation(政府調達協定)
-
BARRIERS TO INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION(知的財産保護への障壁)
- Patents(特許)、Trademarks(商標)、Copyrights(著作権)
-
SERVICES BARRIERS(サービス業への障壁)
- Construction, Architectural and Engineering Services(建築と設計とエンジニアリング)、Legal Services(弁護士)、Insurance(保険)、High Cube Containers(背高コンテナ)
-
INVESTMENT BARRIERS(投資への障壁)
- Direct Investment(直接投資)
-
OTHER BARRIERS(その他の障壁)
- Semiconductors(半導体)、TRON(トロン)、Optical Fibers(光ファイバ)、Aerospace(航空宇宙)、Auto Parts(自動車部品)、Soda Ash(ソーダ灰)、Distribution System(流通システム)、Marketing Practice Restrictions(販売促進の制限)、Law on Large Retail Stores(大規模小売店舗立地法)
-
付属(よくわからないけど、新聞にはこう書かれている)
- 自動車貿易、金融
1990年 外国貿易障壁報告書
1990年3月30日に、USTR は 2 回目の外国貿易障壁報告書が発表しました。前年の 34 項目から「たばこ」「自動車」が外され、「アモルファス合金」「果実」「造船」が追加されました。つまり、35 項目中 TRON を含む 32 項目は前回と同じです。同じ項目が再指定された理由は、一年の間に具体的な市場開放協議が進んでいないためです。
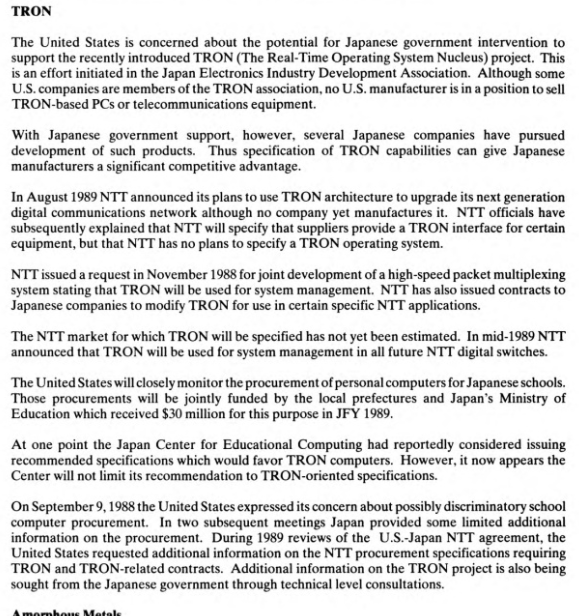
英語の原文(リンク先が消えたときに備えてのバックアップ)
TRON
The United States is concerned about the potential Japanese government intervention to support the recently introduced TRON (The Real-Time Operating System Nucleus) project. This is an effort initiated in the Japan Electronics Industry Development Association. Although some U.S. companies are members of the TRON association, no U.S. manufacturer is in a position to sell TRON-based PCs or telecommunications equipment.
With Japanese government support, however, several Japanese companies have pursued development of such products. Thus specification of TRON capabilities can give Japanese manufacturers a significant competitive advantage.
In August 1989 NTT announced its plans to use TRON architecture to upgrade its next generation digital communications network although no company yet manufactures it. NTT officials have subsequently explained that NTT will specify that suppliers provide a TRON interface for certain equipment, but that NTT has no plans to specify a TRON operating system.
NTT issued a request in November 1988 for joint development of a high-speed packet multiplexing system stating that TRON will be used for system management. NTT has also issued contracts to Japanese companies to modify TRON for use in certain specific NTT applications.
The NTT market for which TRON will be specified has not yet been estimated. In mid-1989 NTT announced that TRON will be used for system management in all future NTT digital switches.
The United States will closely monitor the procurement of personal computers for Japanese schools. Those procurements will be jointly funded by the local prefectures and Japan's Ministry of Education which received $30 million for this purpose in JFY 1989.
At one point the Japan Center for Educational Computing had reportedly considered issuing recommended specifications which would favor TRON computers. However, it now appears the Center will not limit its recommendation to TRON-oriented specifications.
On September 9, 1988 the United States expressed its concern about possibly discriminatory school computer procurement. In two subsequent meetings Japan provided some limited additional information on the procurement. During 1989 reviews of the U.S.-Japan NTT agreement, the United States requested additional information on the NTT procurement specifications requiring TRON and TRON-related contracts. Additional information on the TRON project is also being sought from the Japanese government through technical level consultations.
TRON
米国合衆国は、最近導入された TRON (The Real-Time Operating System Nucleus) プロジェクトを支援するために日本政府が介入する可能性について懸念している。これは、日本電子工業振興協会によって開始された取り組みである。TRON 協会には一部の米国企業も加盟しているが、TRON をベースとしたパソコンや通信機器を販売できる立場にある米国の製造業者は存在しない。
しかしながら、日本政府の支援のもとで、複数の日本企業がそのような製品の開発を進めてきた。そのため、TRON 機能の仕様は日本の製造業者に大きな競争上の優位性を与える可能性がある。
1989年8月、NTT は次世代デジタル通信ネットワークの高度化にあたり、TRON アーキテクチャを採用する計画を発表したが、その時点ではいかなる企業も TRON を製造していなかった。その後、NTT の関係者は、特定の機器について供給業者に TRON インターフェースの提供を求める仕様とする予定であるが、TRON オペレーティングシステムを仕様として求める計画はないと説明している。
NTT は 1988年11月、高速パケット多重化システムの共同開発を求める要請を出し、その中でシステム管理に TRON を使用することを明記した。また NTT は、特定の用途において TRON を使用できるようにするため、日本企業に対して TRON の改変を委託する契約も交わしている。
TRON が仕様として求められる NTT 市場の規模については、まだ試算されていない。1989年半ば、NTT は今後のすべての NTT 製デジタル交換機において、システム管理に TRON を使用する方針を発表した。
米国合衆国は、日本の学校向けパーソナルコンピュータの調達状況を綿密に監視する予定である。これらの調達は、地方自治体と日本の文部省によって共同で資金提供されるものであり、文部省はこの目的のために 1989 年度予算で 3,000 万ドルを受け取っている。
かつて、教育用コンピュータ開発センターが TRON コンピュータを優遇する推奨仕様を発表することを検討していたと報じられた。しかし現在では、同センターは推奨仕様を TRON 向けに限定することはないと見られている。
1988年9月9日、米国合衆国は、差別的である可能性のある学校用コンピュータの調達について懸念を表明した。その後の 2 回の会合において、日本は当該調達に関する限られた追加情報を提供した。1989年に行われた日米 NTT 協定の見直しの過程では、米国は TRON を要件とする NTT の調達仕様および TRON 関連の契約に関する追加情報を求めた。また、TRON プロジェクトに関するさらなる情報についても、技術レベルの協議を通じて日本政府に対して要請が行われている。
補足解説3
1989年版では「TRON オペレーティングシステム」だったのが、1990年版では「TRON プロジェクト」となっており、USTR の理解度が向上しているように思えます。1989 年版は教育用パソコンの問題のほうがメインだったように思えますが、1990 年版は NTT の次世代デジタル通信ネットワークのほうがメインになっているように思えます。教育用パソコンについては、CEC が BTRON に統一するのを断念したため、調達状況を綿密に監視する予定となっていますが、問題視してないように思えます。
1991年 外国貿易障壁報告書
2025-12-07 追記
TRON が指定されていたのは、1989 年と1990 年だけだと勘違いしてたので追記します。これは「7. OTHER BARRIERS」に含まれています。
In another area of possible concern, Nippon Telegraph and Telephone (NTT's) announced its intention to specify the real-time operating system nucleus (TRON) as a standard in future computer systems. However, it has decided to allow other real-time operating systems and interfaces to be considered along with TRON. The United States will closely monitor this situation and other matters related to TRON.
別の潜在的懸念分野として、日本電信電話(NTT)は、将来のコンピュータシステムにおいて the real-time operating system nucleus(TRON)を標準として指定する意向を発表した。しかし、NTTは TRON と併せて他のリアルタイム・オペレーティングシステムおよびインターフェースも検討対象とすることを決定した。米国は、この状況および TRON に関連するその他の事項を注意深く監視する予定である。
さいごに
外国貿易障壁報告書を読むことで、米国通商代表部 (USTR) は、日本に TRON プロジェクトから手を引けと言っていたわけではなく、教育用パソコン市場に参入できるようにしろ(TRON 以外の OS も許可しろ)と言っていたことがはっきりしました。つまり、最初からコンピュータ教育センター (CEC) は、教育用パソコンを BTRON に限定にしなければスーパー301条で名指しされることはなかったんですよ(NTT の次世代デジタル通信ネットワークの話もありますが)。
一体なんで BTRON 限定にしようとしたのでしょうね? その答えはわかっていて、通産省が日本の技術に固執していて、米国の技術を排除しなければ、日本は米国に勝てないと思っていたらです。事前にパソコンメーカーに BTRON パソコンを作るように通達を出し、BTRON 限定になるように教育用パソコンの仕様作りを進めていたわけですが、そんな方法で米国に勝っても将来はありません。せいぜい "教育用パソコンだけ" が BTRON パソコンになっていただけでしょう。だって日本国中、誰もが国民機と呼ばれた PC-98 シリーズを使っているんですよ? 互換性がないパソコンに乗り換えるわけも会社のシステムを入れ替えるわけもないじゃないですか?
最終的に TRON はスーパー301条の制裁対象にはなりませんでした。なぜなら教育用パソコンを BTRON に統一するのをやめたからです。BTRON に統一するのをやめただけで、教育用パソコンは BTRON パソコンでも構いませんでした。米国は TRON プロ上クトから手を引けと脅したわけではありません。それなのに TRON プロジェクトから手を引いたのは、国内の各パソコンメーカーが BTRON に将来性がないと考えたからです。その代わりに PC 互換機を作るようになりました。