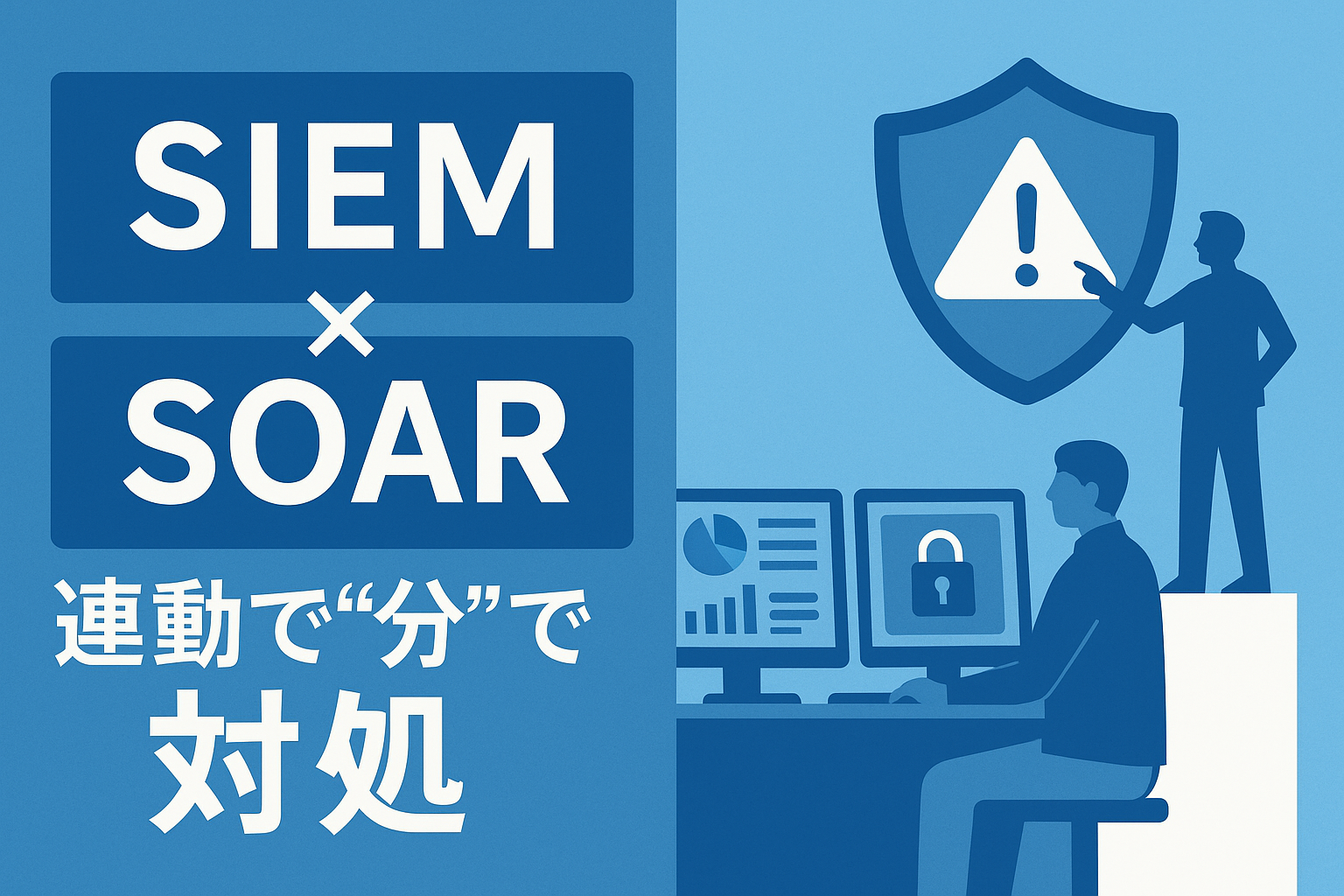はじめに
セキュリティ運用の現場では、ログを集約して相関分析するSIEMと、対応手順を自動化するSOARが“両輪”です。とはいえ、どちらを先に入れるのか? 何を連動させるのか? 投資対効果はどう測るのか?――実務では判断が割れがちです。
本記事は、①役割の最短整理、②連動による価値と運用の型、③30-60-90日の導入ロードマップと失敗回避を提示し、MTTD/MTTRを圧縮するための実装ポイントを俯瞰して解説します。
1. 基礎を最短整理:SIEMとSOARの役割
SIEMは各種ログを統合・相関・可視化して異常の全体像を描く意思決定エンジンのイメージです。SOARは対応手順を自動化・標準化して調査→隔離→封じ込め→復旧を高速化する実行プラットフォームです。
まずはトップ10ユースケースを定め、SIEMは誤検知チューニング、SOARは高頻度×低難度のプレイブックから着手してみましょう。
できること
- SIEM: FW/EDR/WAF/IAM/AD/クラウド監査ログの集約・正規化、相関ルール、KPI可視化。
- SOAR: チケット化→証跡収集→端末隔離→ユーザー凍結の半自動化、承認ゲート、監査証跡。
▼注釈
- FW: Firewall(ファイアウォール)
- EDR: Endpoint Detection & Response
- WAF: Web Application Firewall
- IAM: Identity & Access Management
- AD: Active Directory
- KPI: Key Performance Indicator(重要業績評価指標)
- MTTD: Mean Time To Detect(検知までの平均時間)
- MTTR: Mean Time To Recover/Respond(復旧・対応までの平均時間)
- プレイブック: 定型化した対応手順の台本
2. 連動の価値と運用:検知から対処を“分”対応へ
基本アーキテクチャ:①ログはSIEMへ→②検知イベントをSOARへ→③プレイブックで自動調査・隔離→④結果をダッシュボード/レポートで還元。
メリット:MTTD/MTTR短縮、運用品質の平準化(夜間・休日も同品質)、監査対応強化(証跡自動収集)、アナリストの高付加価値化(ハンティングへ集中)。
現場オペレーションの型
- 役割:L1=自動化監視、L2=相関/プレイブック改善、L3=高度分析。
- ルール:DEV→STG→PRDの段階的に適用、信頼スコア×承認ゲートで問題点の洗い出しと承認・共有、週次レビューでトップ10アラートを分析して継続的に最適化。
▼注釈
- ダッシュボード: 状況を可視化する画面
- ハンティング: 能動的な脅威探索
- L1/L2/L3: セキュリティ運用の層別役割
- DEV:Development(開発)
- STG:Staging(検証)
- PRD:Production(本番)
- 信頼スコア: 検出精度を数値化した内部指標
3. 導入ロードマップと失敗回避:30-60-90日
Day 0-30:接続対象と保持要件を決定、SIEMに最大10系統を優先接続/トップ10ユースケース合意/メール媒介・異常ログインをSOARで半自動化。
Day 31-60:SIEM相関精度を改善しハンティング手順を文書化/SOARで端末隔離・IAM凍結・チケット連携を本番化。
Day 61-90:週次品質レビュー会を定常化/撤去すべきルールを整理/KPIダッシュボードと月次レポートで経営可視化。
よくある落とし穴 → 回避策
- ログ“全部取り”→ユースケース起点でホット/コールド分割。
- 自動隔離の乱用→承認ゲートとロールバックを内蔵。
- “作って終わり”→週次レビューと廃止基準を運用に内蔵。
- 属人運用→プレイブック・台帳・教育で標準化。
▼注釈
- IAM: Identity & Access Management
- TCO: Total Cost of Ownership(総保有コスト)
おわりに
結論はシンプルです。SIEM=見える化と洞察、SOAR=素早い行動。この二つをトップ10ユースケースから連動させ、週次レビュー×変更管理で痩せた運用に磨き込むことで、MTTD/MTTR、監査コスト、属人リスクを同時に下げられます。
まずはDay 0-30で“つなぐ・回す”を小さく始め、Day 31-60/61-90で精度と可視化を底上げしましょう。意思決定はダッシュボードで見える化し、現場はプレイブックで自動化する――それが、限られたリソースで最大の防御効果を得る最短ルートです。
ぜひ現場でお試しください。