GYAOの玉利です。
弊社、副業ができるようになりました。いままで通訳とか頼まれても手弁当になってしまっていたので、個人的にはすごく助かります。
ちょうど最初の職場(環境保護団体)の先輩が転職して、ある政令指定都市の市役所の出先機関(環境系)の受託業務で所長を勤めることになり、実務経験のある植物分類学・生態学の専門家として土日に非常勤でお手伝いすることになりました。
もちろん、こんなはずじゃなかったということで、話は予想外の方向に進みます。なぜか役所でITによるオープンイノベーションを起こすことになってしまいました。
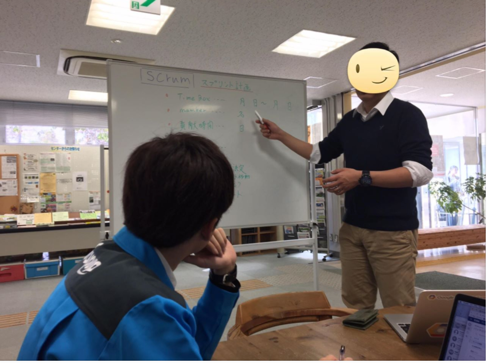
先に結論
最初に弊社内でオープンイノベーションと言い出した社内の人は、社外の人が来てくれて自分の会社にいい刺激を与えてくれると思っていたと思います。かなり虫のいい話です。
ところが実際にやってみると、今の自分にできるオープンイノベーションは社外に出ていって他組織の課題を解決し、なにかを共有して持ち帰るべき性質のものでした。もしも自組織でこれができるのであれば、トップダウンでほとんど無制限の権限委譲がなされているのが前提だと思います。
別組織の内部に入ってみて
公共施設はひどい有様
以前の管理は地元の環境NGOがおこなっていました。主婦の方などがやっているので、業務の管理が全くなされていない状態で、思い出したらやる、定時が過ぎたら作業を始めるなど、普通の会社では信じられないことが起きていました。
展示についても更新がされず、3-10年前の展示がそのまま茶色くなってたり、謎の企業ポスターが貼ってあったりして、来場者は毎日ほぼゼロ、期待された機能を果たしていませんでした。
このように地元の環境NGOでは運営が難しいということで、市役所のほうから別の部署で実績のある地元企業社長に頼んで、そこの所長として元ITマネージャーの先輩がヘッドハントで引っ張られてきたのです。
実際に引き継ぎをしてみるとなると、地元に貢献するという強い意気込みで利益の薄い仕事を受けた社長が凹む有様でした。
もちろん、展示もあれなら他のところも推して知るべきな状態でした。民間だったらとっくに潰れてるような状況でも、公的施設だとそうならないのです。
プロフェッショナルが集まる
所長(先輩)から相談されて、それならば前職のベテランFさんが近所に住んでいて個人で環境調査業務をやってるから、頼んでみましょうか?とコンタクトしたら、地元の環境保護に大きなコネクションを持ってました。コンテンツ部分は彼がしっかり見てくれます。
私は植物の専門家、ではなく、オフショア立ち上げなどの経験を活かしITインフラ含むオペレーションの全体コーディネートをすることに。
一緒にベトナムに行く同僚には、スクラムマスターの講師として教育担当に入ってもらい、業務内容の可視化と進捗効率改善を進めてもらうことにしました。
話が始まってわずか数ヶ月で、専門家集団としての形が整いました。主要メンバーは17年ぶりの再会です。
ITインフラから整備すべし
所長は前職で外資系のITマネージャーだったのですが、基本システムはグローバルITが用意してました。今回は彼が自分でアーキテクトからやらなきゃいけません。
所長「玉利くん、なんか古いサーバがあるんだけどさ、これバックアップどうしたほうがいい?」
私 「今時、Amazon S3やAzure Storageあたりのクラウドのほうが保管コスト安くて3面ミラーですよ。なんか無茶苦茶ボリュームある仕事みたいので、コンサル受けましょうか?」
自分はヤフーグループで一番事務処理ができるネットワークエンジニアを自称してますので、組織の建て付けづくりからインフラ構築はお手の物です。まずは情報を整理できるように各人の頭の中から作業を可視化することころからはじめました。
- コミュニケーションにSlack導入
- タスク管理はJIRAでアジャイル・スクラム
- ドキュメントはConfluence(Wiki)
- インフラはクラウドを最大活用。個人情報だけはオンプレミス
github/bitbucketを入れれば、そのままITスタートアップですね。
10人程度の組織なので、大げさなシステムは不要です。非常勤のシフト勤務などが多く、言ってみればリモートワークのエンジニアの集合体みたいな組織なので、ITスタートアップっぽい仕組みを使いました。
私はいまのところRailsエンジニアなので、やることはRails wayに乗っかることにしました。
参考文献
強いチームはオフィスを捨てる: 37シグナルズが考える「働き方革命」
ジェイソン・フリード
http://amzn.asia/gxaePUn
アジャイル・スクラムの導入
所長は外資系のITでチケット運用に慣れていたので、JIRAの操作にはすぐに慣れました。ITエンジニアだからできる組織運営かとは思いますが、一般的な問題でも期日を設定してしっかりと潰しこむのには非常に向いている仕組みだと感じました。
お金の話
副業のスポット報酬はいくらに設定すべきか
受託先の社長には、スポーツトレーナーのプライベートレッスンと同じ価格帯で、ということで納得していただきました。弊社の基準工賃からみると割安ですし、バイト代よりは高い値段です。自分はここから経費がかかるので、まるまる残るわけではないのですが、市場原理で形成された価格設定なのでどちらかが損することもありません。エンジニアにとって、このあたりが一番むずかしい部分だと思います。
- スポーツパーソナルトレーナーの価格設定を参考に(6,000-12,000円/時間) 今回は初回友人価格。
- 交通費・移動時間工賃は片道1時間はコンサル費に含む
- リモート質問はスポーツだと月2件まで、のところを無制限に
本業との兼ね合いがあるので、貢献時間としてピークになっても月30時間を上限に考えました。
経費の使い方
サラリーマンエンジニアだとまったく経験のない、経費をいかにうまく使うかが求められます。移動手段もコストと時間を考えますし、機材や足りない能力もお金で解決して、いちばん苦手な簿記関係はクラウド会計ソフトに入れていくことにしました。最近の簿記ソフトは自動仕分けしてくれるので楽ですね。でも、いちど簿記3級の勉強だけはしておいたほうが良いと思います。
何がオープンイノベーションを起こすのか
以下はWikiからの引用です。
「オープンイノベーション(英: open innovation)とは、自社だけでなく他社や大学、地方自治体、社会起業家など異業種、異分野が持つ技術やアイデア、サービス、ノウハウ、データ、知識などを組み合わせ、革新的なビジネスモデル、研究成果、製品開発、サービス開発、組織改革、行政改革、ソーシャルイノベーション等につなげるイノベーションの方法論である。」
いま、オープンイノベーションの真っ最中にいて行政サービスを改善しています。オープンイノベーションに何が必要かというと、以下の条件が浮かび上がりました。
- 現場リーダーへの権限移譲
- 現場リーダーの人脈コネクション
- 責任者との信頼関係。君臨すれども統治せずという姿勢が望ましい
- 外部からのプレーヤーの出会うタイミング
多分、オープンイノベーションを期待して何かを始めても、大抵の会社は内部の都合で失敗すると思います。最初に所長をヘッドハントした社長の人脈力が始まりで、その社長に相談した市役所の方が、とても良い選択をしたのだと思います。キーパーソンの人間力がイノベーションを生み出すのだと感じました。