はじめましてインフラSE歴約20年のY.Ksmyと申します。
よろしくお願いいたします🙇
いきなりですが、私の長いインフラSE歴の中で、今、最大の危機が訪れようとしています。
それはAIによる「仕事の再定義」という巨大な波です。
もうすでに進化したAIが、様々な業種の仕事を奪取している現状は対岸の火事では済みません。
そんな状況になっていることを、未だ多くのインフラSEは気がついていないのではないでしょうか。
今からでも遅くありません。まずはAIを使うところから始めてみませんか?
自問自答必須!AIの波に乗り遅れていないか!?
最近、技術ニュースでAIの話題を見ない日はありません。
ChatGPTなどの生成AIを少し触ってみたものの、思ったような答えが返ってこず、「業務で使うのはまだ難しいか」と、利用を中断してしまった方も多いのではないでしょうか。
日々の業務に追われる中で、AIはどこか遠い世界の技術だと感じられるかもしれません。
しかし、インフラ構築や運用の現場で、論理的に物事を考え、手順を組み立てるスキルを磨いてきたエンジニアだからこそ、このAIというツールを、誰よりも巧みに使いこなすポテンシャルを秘めているのです。
AIを業務で活用するための第一歩として、AIへの指示、すなわち「プロンプト」の質を劇的に向上させる5つの重要なポイントを抑えて、明日からの業務の効率化を実践していきましょう。
なぜ今、インフラエンジニアがプロンプトを学ぶべきか?
結論から言えば、プロンプトスキルは、今後のインフラエンジニアの生産性と市場価値を大きく左右するからです。
インフラの現場は、常に安定稼働とコスト効率、そしてセキュリティという複数の要求を同時に満たす必要があります。この複雑な課題に対して、AIを使いこなせるかどうかは、業務の質とスピードに天と地ほどの差を生む可能性があります。
-
定型業務からの解放:
TerraformやAnsibleのコード生成、膨大なサーバーログの解析、障害対応手順書のドラフト作成、セキュリティパッチ情報の収集と要約。これらの作業をAIに任せることで、エンジニアはより本質的なアーキテクチャ設計やパフォーマンスチューニングに集中できます。 -
思考の壁打ち相手:
新しいクラウド構成の設計、コスト削減のためのインスタンス選定、複雑なネットワーク問題の切り分けについて、AIは24時間365日、相談に乗ってくれる壁打ち相手になります。多様な視点からアイデアを得ることで、一人で悩むよりも速く、質の高い解決策にたどり着けるはずです。
要件を定義し、論理的にタスクを分解する能力は、インフラエンジニアが持つ強みです。これは、優れたプロンプトを作成する上で、この上なく強力な素養となります。AIは仕事を奪う脅威ではなく、エンジニアの能力を何倍にも増幅させてくれる、最高のパートナーなのです。
AIプロンプトを劇的に改善する5つのポイント
AIを「超優秀なアシスタント」に変えるための、具体的な5つのポイントを解説します。
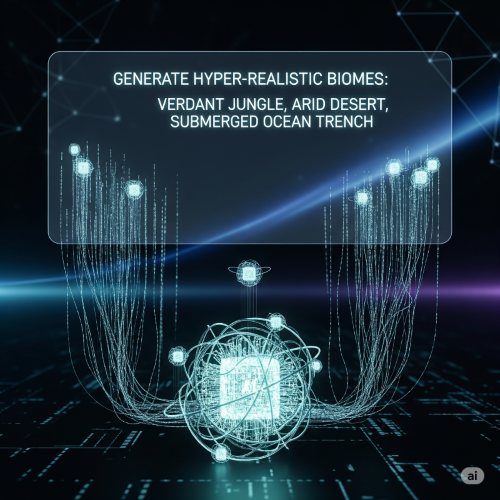
ポイント1:役割(ペルソナ)を与えて専門家にする
AIに何かを頼むとき、漠然と指示を出すのは避けましょう。
まず最初に、AIに特定の「役割」を与えます。 これにより、AIはその分野の専門家として思考し、回答の質が格段に向上します。
-
悪い例:
クラウド移行について教えてください -
良い例:
あなたは、AWSとAzureの両方に精通した、経験豊富なクラウドインフラエンジニアです。現在、オンプレミスで稼働しているWebサービスをクラウドに移行する計画を立てています。可用性とコスト効率を両立させるための最適な構成案について、考慮すべき技術選定のポイントや注意点をアドバイスしてください。
ポイント2:文脈(コンテキスト)を具体的に伝える
次に、「何のために、どのような状況で」その指示を出しているのか、という背景情報をAIに共有します。
状況を詳しく伝えるほど、AIは意図を正確に理解してくれます。
-
悪い例:
サーバーに繋がらない原因を教えてください。 -
良い例:
あなたは、ネットワークとセキュリティの専門家です。現在、本番環境のWebサーバーへのSSHアクセスが突然できなくなりました。【状況】Webサービス自体は閲覧可能。同セグメントの別サーバーからはSSH接続できる。auth.logに不審なIPからのログイン試行が多数記録されている。【推測】fail2banがオフィスのIPをブロックした可能性がある。この状況から考えられる原因の特定方法と、安全な復旧手順をステップバイステップで示してください。
ポイント3:目的とゴールを明確にする
最終的に何を得たいのか(目的)、どのようなアウトプットが欲しいのか(ゴール)を明確に伝えます。
ゴールが曖昧では、AIが生成するアウトプットもぼやけたものになります。
-
悪い例:
監視項目を考えてください。 -
良い例:
あなたは、経験豊富なSREです。システムの監視体制を強化するため、監視ツールに実装すべきカスタム監視項目を定義してください。【目的】障害の予兆を早期に検知し、サービス影響が出る前に対処できるようにすること。【ゴール(含めるべき項目)】監視対象(Web/AP/DB)、具体的な監視項目、閾値の設定基準、アラート発生時の対応プライオリティ。
ポイント4:制約条件と出力形式を指定する
期待通りのアウトプットを得るには、制約や出力形式を指定することが有効です。 これで手戻りを大幅に削減できます。
-
悪い例:
Terraformのコードを書いてください。 -
良い例:
AWS上にVPC、サブネット(Public/Private)、EC2インスタンスを構築するためのTerraformコードを生成してください。【制約条件】変数はvariables.tfに分離すること。EC2インスタンスのOSはAmazon Linux 2とする。【出力形式】ファイル名(main.tf, variables.tfなど)を明記した上で、それぞれのコードブロックを提示してください。
ポイント5:対話を重ねて精度を上げる(反復的な改善)
AIは「一度で完璧な答えを出す魔法の箱」ではありません。
最初の回答を「たたき台」と捉え、対話を通じて理想に近づけていくことが大切です。
-
あなた:
システムの監視項目リストをMarkdownテーブルで作成してください -
AI:
(監視項目のテーブルを生成) -
あなた:
ありがとうございます。DBサーバーの監視について、レプリケーション遅延やデッドロックの監視を追加してほしいです。 -
AI:
(指摘項目を追加した更新版テーブルを生成) -
あなた:
完璧です。最後に、このリスト全体をJSON形式で出力していただけますか?
※この反復的なプロセスこそが、思考を整理し、より質の高い成果物を生み出す鍵になります。
まとめ
AIの進化は、もはや止められない大きな潮流です。
この波を脅威と捉えるのではなく、エンジニアの能力を拡張する強力なツールとして使いこなすべきでしょう。
インフラエンジニアとして培ってきた論理的思考力は、AIを使いこなす上で必ず武器になります。
今日からでも決して遅くはありません。
まずは、今抱えている小さな課題、例えば「このシェルスクリプトのリファクタリング案を出してください」、「このエラーログの原因を解説してください」といった問いをAIに投げかけてみましょう。
その小さな一歩が始まりで、さらにAIを使う流れ作り自身をアップデートしていくことが、これからのインフラSEに求められれるスキルなのかもしれません。
まずは生成系AIで有名なChatGPT、Claude、Geminiを使い、必要に応じてサブスクリプション契約をしていくようにしましょう。
AIを利用できる環境も、スマートフォンだけではなく、必要に応じてPCでも
利用できるようにすることで、常日頃からAIを利用する環境を身近に置くべきかと思います。
そして、継続してどのようなプロンプトがあるのか、どんなプロンプトが効果的なのか、自身で試す事から始めていきましょう。

