結論
- 指揮の動きは,間接運動と直接運動の2種類に分けられます.
- まずは,点の示し方が異なるこの2つの動きの違いを区別して振れるようにしましょう.
- 力が入りすぎて,間接運動が直接運動に近くなると指揮が見にくくなるので注意しましょう.
1. はじめに
マンドリンオーケストラを振っているロンといいます.
身の回りで,
「指揮法とか習ったことない.」
「どう振っていいかわからないからテキトーにやってました.」
という指揮者さんが案外多いことに驚きました.
幸い私は関西にいたころ,プロの指揮者の先生について10年ほど指揮法を習う機会に恵まれました.
今回は「指揮とかどう勉強していいかわからない」というマンオケ人のために,(自分のことは棚に上げて)解説をしようと思います.
2. 間接運動とか直接運動ってなに?
小澤征爾の師匠として有名な,齊藤秀雄による分類です.
- 間接運動 : 点の前に連続した運動(点前運動)があるもの.
- 直接運動 : 点の前に,その点の暗示する点前運動がないもの.
なんのこっちゃわけわからんと思うので,順番に動画で見ていきましょう.
バーンスタインが振っている,チャイコフスキーの交響曲第5番の1音目にご注目!

この場合は,指揮棒が一番下に行った時が拍の点にあたります.
このように,点の前に動きがあることで拍を間接的に示す運動を,間接運動と呼びます.
一方で,こちらでは小澤征爾が直接運動を教えています.

この場合は,手が動き出した瞬間が拍の点にあたります.
このように,動き出しで直接的に拍を示す運動を,直接運動と呼びます.
3. 間接運動の利点
間接運動は,点の前に動きがあるので,点が予測しやすいことが利点です.
下は,平林さんによる指揮法レッスン動画ですが,リタルダンドをかけるときに間接運動を使っています.
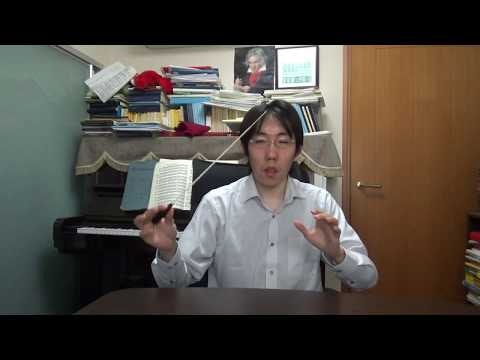
このように,テンポを大きく動かすときには間接運動が有効です
また,点の前に動きがあるので,ニュアンスをつけやすいことも利点の一つでしょう.
マンドリン合奏は,ヴァイオリンのようにボーイング(弓の動き)で合わせることができないので,間接運動が重用される傾向があるように思います.
ARTEの井上さんも

この曲では基本的に間接運動を使っています.
テンポとニュアンスの違いが明確にわかりますね.
舞踊風組曲第2番で有名な久保田孝さんも
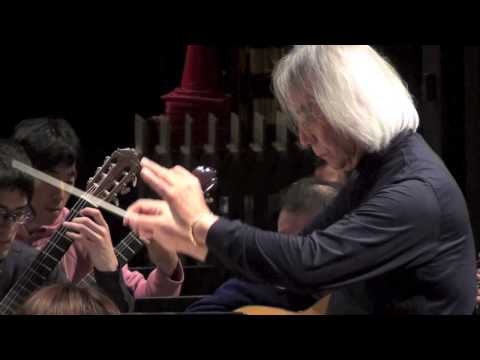
このように,この曲ではほとんどの部分で間接運動を使っています.
4. 直接運動の利点
動き出しによってテンポを明示できます.点をはっきり示したいときに有効です.
例えば,先ほども紹介したバーンスタインが振るチャイコフスキーの交響曲第5番でも,

このように一定のテンポになってからは直接運動を使っています.
自分の例で申し訳ないのですが,丸本大悟さんの虹彩,ffの後に静かになった場面で直接運動を使いました.
このように,テンポの遅い部分でテンポを明示したいときにも有効な手段です.
久保田孝さんが,先ほどと同じ動画で部分的に直接運動を使っているところを見つけました.
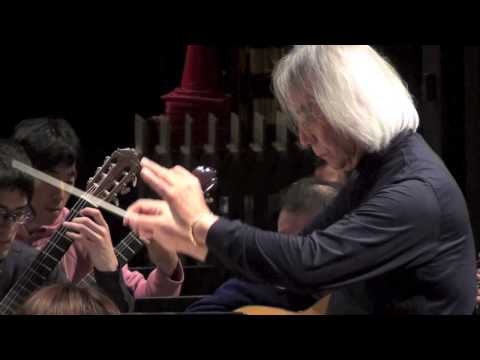
このように,アクセント的な表現にも使えます.
5. 区別しないとどうなる?
ここからは,注意したほうがいい例を見ていきましょう.
この指揮者さん(指揮法クリニックの生徒さん)は,基本的には間接運動で振っているのですが,4拍子の1拍目は全て直接運動になっています.
他にも,フレーズが切れる3拍目でも直接運動的になっており,その他の拍もだんだんと直接運動に近くなってしまっています.
この方が意識してそのように振っているのかこの動画ではわかりませんが,フレーズの入りを明確に示すという意味では有効な直接運動も,あまり多用しすぎるとフレーズが停滞してしまったり,指揮が見にくくなる弊害があります.

この動画,まずBeforeの例は完全に直接運動です.テンポは明確ですが,かなり力が入っていて,ずっと見ていると奏者も疲れてしまうと思います.
Afterの例は間接運動に近づいています.しかし,こちらも力が入っていて,打点の直前で急速に加速しており,点の予測がしにくく,見にくく感じてしまいます.
間接運動は力を抜かないと,動きが急速に変化してしまい,直接運動に近くなってしまいます.
間接運動と直接運動は,点の示し方が完全に異なるため,力を抜いて,区別して振らないと見にくい指揮になってしまいます.
6. おわりに
指揮法の最も基本的な分類である間接運動と直接運動について,定義やそれぞれの利点・欠点をまとめ,区別しないとどうなるかの例を示しました.
初心者の方は,まず自分が日頃どちらの動きで振ろうとしているのかを明確にしましょう.
これから指揮法を勉強する方は,まずは間接運動から始め,力が入りすぎて直接運動に近くならないよう注意することをおすすめします.
次回は,指揮の基本である「脱力」について解説します.
参考文献
- 齊藤秀雄, "指揮法教程", 音楽之友社.
- 斉田好男,"はじめての指揮法", 音楽之友社.

