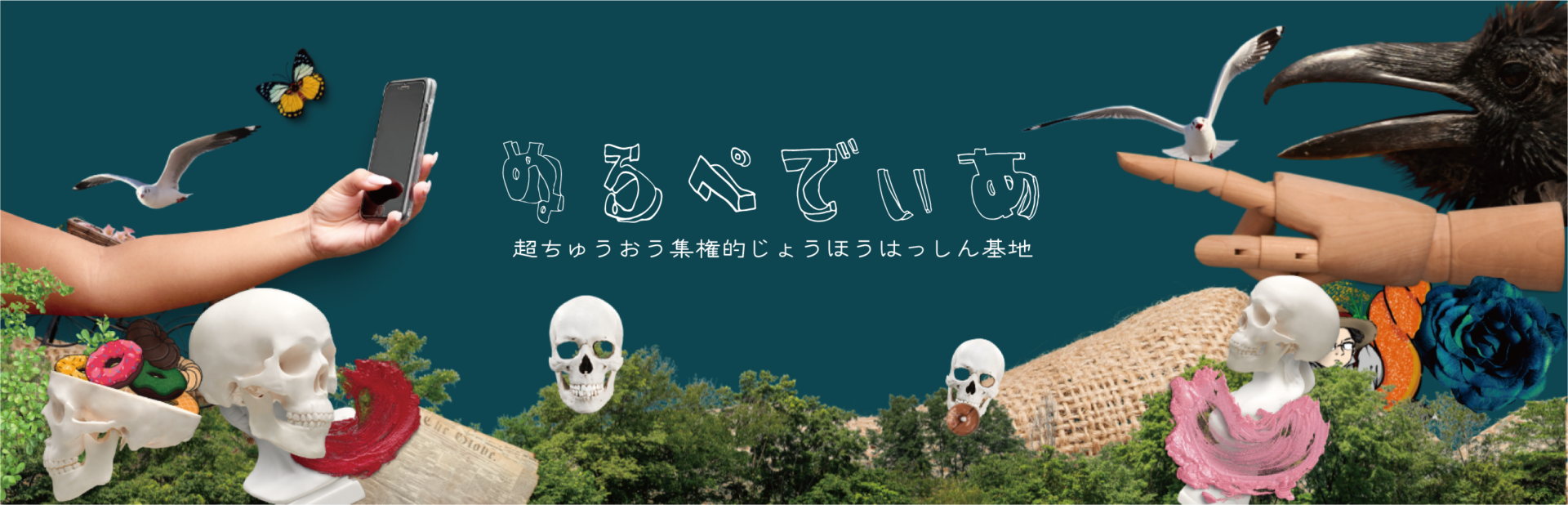毎週1~2回の頻度にて、不定期で配信中の「ドーナツ部長のホールナイトニッポン」。現在、スタンドFMにて絶賛配信を継続中です。(スタンドFMでの放送は、SpotifyやPodcastへも転載されています)
「ホールナイトニッポン」のユニークな点は、過去の放送回をテキスト化し読めるようにしていること。サイト「ぬるペディア」内で、過去の重要な放送回から順にテキスト化し、記事としてリリースしています。
音声をテキスト化する意味
Youtube動画で、最も面白い箇所や引きの強い箇所だけにスポットを当てた「切り抜き動画」が登場したように、音声メディアにおいても「切り抜き」要素が登場するだろう…と私は予想しています。
Youtubeにおける「切り抜き動画」は、時間のない方や手軽にサクッと動画を楽しみたい方の「要約だけ観たい」「一番のヤマ(あのシーン)を観たい」という要求を見事に満たしてきました。
では、音声はどうでしょう?
この1年で、音声での配信者は急増し、音声における良質なコンテンツの数も多くなってきました。VoicyやスタンドFMなど、配信によって収益を得る仕組みを導入するプラットフォームも存在しており、今後ますます参入者が増えることが予想されます。
動画と違って、編集作業が少なくて済む点で、音声の参入障壁はとても小さいと言えるのも、その理由の一つです。
つまり、今後ますます「耳の交通渋滞」が起こることは…ほぼ間違いない、と私は考えています。
そこで、「音声の切り抜き方」について真剣に考えてみることにしました。
音声の切り抜きは、テキストである
音声を切り抜いて、当該箇所だけピックアップする…まさに文字通りの「切り抜き」でも良い…と最初は考えました。しかし、いざやってみると、その部分だけ切り抜いたものは、不思議とコンテンツとしての魅力までもが、きれいに洗い流されてしまったのです。
映像と音声の違いなのか、単に切り抜きにつかった私のコンテンツが弱かったのか…は、さておき。
この実験から「単純に音声を切り抜いて、短くするだけでは、ダメそうだ」という考えにたどり着きました。そうなると…音声を全て聞くことなく、話の内容を手っ取り早く理解できて、かつコンテンツとしての魅力を失わないためには…?
「テキストで、読めばいいのか」
そこで、スタンドFMの過去回を、音声化し、一部要約や補足を加えつつ、記事化してみることにしたんです。これが、「読むアーカイブス」の誕生です。
誕生の経緯や「テキスト化」の重要性については、下記の記事をご覧ください。
読むアーカイブスとは?
「読むアーカイブス」とは、音声配信の切り抜きを区的としたテキストベースによる「読むコンテンツ」です。本サイト上で誰でも、自由に閲覧することが可能です。現状では「ホールナイトニッポン」の過去放送の中から、優先度が高い重要なテーマを中心に、テキスト化を行っています。
※「読むアーカイブス」はコチラから
音声をテキストに変える作業にあたっては、そのまま音声を文字起こしをしても面白くないので、AIによる文字起こしを使って実装しています。その後、音声に見られる繋ぎの言葉や、繰り返しになる部分を編集し、記事として読めるように、内容や表現の一部を修正することで出来上がっています。
「読むアーカイブス」としてテキスト化した内容は、さらに抜粋されて、TweetやThreadsなどでの情報発信に使われています。
「聴く×読む×発信する」を選べる、選択的メディアの提案
こうして運用している「読むアーカイブス」を、さらにパワーアップさせてみようと考えました。
- 本サイトにおける「読むアーカイブス」へのアクセスが上昇傾向にあること。
- 音声配信→読むアーカイブス→Tweetへ投下 という流れが非常に使い勝手が良く、反響もいいこと。
- 「読むアーカイブス」→スタンドFM という外部リンクしかなく、流れが一方通行。
以上の3点が、バージョンアップを考える理由です。
聴く×読む×発信する「オルタナティブ」
下記は、従来の音声メディアとSNSの関係性です。内容を把握するには、音声放送のタイトルと概要欄が参考になりますが、とにかく放送を聴くことが必須でした。
また、放送の内容をSNSで発信する場合、「あの部分が良かった!」と内容に触れようとすると、脳内で音声を再生し、テキストとして入力する…そんなことが必要でした。
そこで、こんな座組を考えてみました。音声配信とテキスト、SNSの新しい関係性を示した「オルタナティブ構想」です。
「ドーナツ部長のホールナイトニッポン」で行っているのは、まさにこの座組となります。
※これらの図は、どうぞご自由にご活用ください。
音声をテキスト化する(私の場合は、記事としてサイトへ掲載しています)ことで、3つの利点が生まれます。
- 音声を聴く前に、どんな内容なのか把握することができる
- テキストを読んで、聴きたい部分だけ聴きに行くことができる
- 音声をテキストとしてストックすることで、検索性がアップする
「あの内容を話してる放送は…いつだったっけ?」という場合にも、テキスト化しておくことで、探しやすさは段違いに向上します。意外な盲点として、「音声はアーカイブには不向き」であることを、ぜひ押さえておいてください。
さらに、放送の内容をSNSで発信する場合も、音声をテキスト化した内容を参考に発信ができるので、非常に便利です。わざわざ脳内で音声を再生し、テキストとして入力する…なんてことをせずにすみます。
テキスト化したものを公開するには、私のようにサイトを持っていない方の場合、「note」で十分だと思います。配信した内容を、noteで公開して、音声メディアへのリンクもそこに掲載しておきましょう。
音声をテキスト化することで、聴いて楽しむのか、読んで楽しむのか、さらに第三者へ発信をして楽しむのか…色々な選択が生まれることになります。
大切なのは、選択。
大切なのは、選択です。「ドーナツ部長」のNFTコレクションでは、この「選択」が最も大切な概念として重要視されてきました。楽しむ方が、どんな楽しみ方を選ぶのか…それは、楽しむ側が決めるものであり、運営が無理強いするものではないのです。
「ドーナツ部長のホールナイトニッポン」でも、スタンドFMの方へ以下の変更を加える予定です。
- 「読むアーカイブス」としてテキスト化されていることが、一目で分かるようにする
- スタンドFMの概要欄へ、対応する「読むアーカイブス」のURLリンクを掲載する
これだけAIの進歩が現在進行形で進み続け、あらゆるサービス化の速度が上がっている時代において、音声をアップすると精度の高い記事が出来上がる‥なんてことも、すぐ先の将来に起こり得るかもしれません。実際にスタンドFMでは、音声放送から見出し付きの記事を作成できる「AI記事化機能」が公開されています。今後の流れとして、音声とテキストがセットで配信される…なんてことが起こるかもしれないですね。
ここまで読んで気になった方は、ぜひ音声・テキスト・SNSの構造を意識したメディアの運用をしてみましょう!
この記事は、著者が運営するメディア「ぬるぺでぃあ」でも読むことができます(記事はコチラ)