初めに
リーダーというロールを初めて担うことになり、「どうチームをマネジメントすればいいのか?」という問いに向き合う中で、**MBO(Management by Objectives and Self-control)**という概念に出会いました。
この記事では、MBOの本来の意味と、それをチーム内で実践してみた経験を踏まえた私の解釈と感想をまとめてみたいと思います。
MBOとは?私の理解と背景
書籍「目標管理入門」から得た学び
MBOを理解するうえで特に役に立ったのが、**「目標管理入門」**という書籍です。私のMBOに対する認識は、この書籍の内容が大きな土台となっています。
https://amzn.asia/d/1kHRLyt
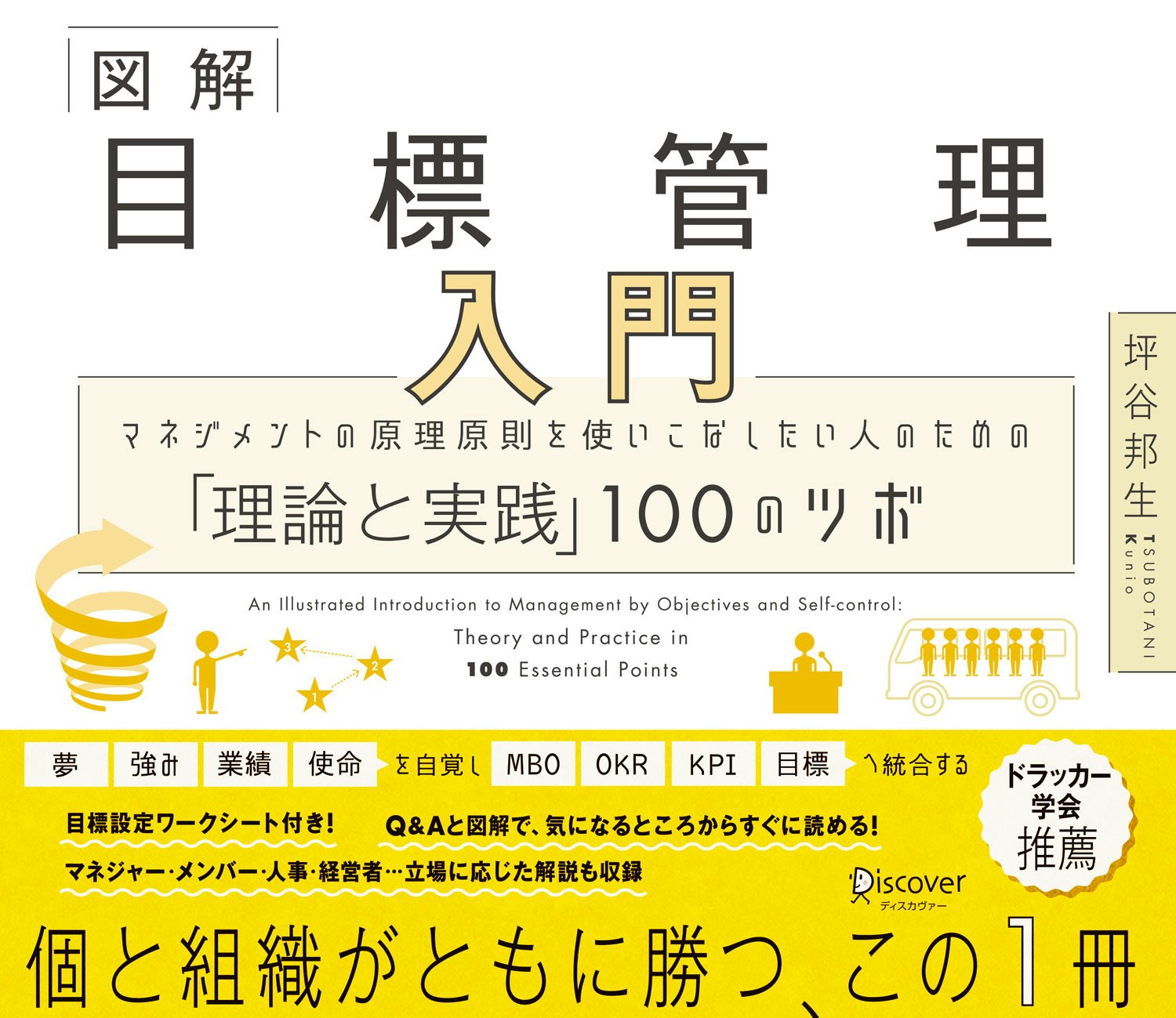
「Objectives and Self-control」が本当の意味
一般的に広まっているMBOは「Management by Objectives(目標による管理)」という略称ですが、実はこれは本来の意味の一部でしかありません。
ドラッカーが提唱した正式な名称は、
Management by Objectives and Self-control(目標と自己統制によるマネジメント)
です。
この「and Self-control」という後半部分が日本ではほとんど省略されており、その結果、上司が部下に目標を与え、それを評価・管理する手法として誤解されてしまっていると感じます。
私がこの部分で強く共感したのは、「目標とは、上から与えられるものではなく、個人が自らの意思と責任で設定し、達成へ向かって自己管理していくための道標であるべき」という考え方です。
つまり、MBOは命令による統制ではなく、信頼と自律による協働を目指したマネジメントのあり方であり、単なる「上司による進捗管理」や「数値目標のチェックリスト」とは一線を画します。
個人が目標を設定することのメリット・デメリット
メリット
自律性が高まる![]()
自分自身で目標を設定するというプロセスには、「自分は何を達成したいのか?」という問いがが不可欠です。与えられた目標に従うのではなく、自らの意志で目標を立てることで、
責任感や主体性、自主的な行動が生まれると思っております。
メンバーが主体的に動いてくれるので私自身も、「細かく指示を出す」必要が減り、代わりにサポートや自分自身がやりたいこと時間を使えるようになったのは大きな変化でした。
モチベ維持に繋がる![]()
自らのスキルや興味、現在の課題意識に基づいて目標を立てることでモチベーションが維持されると思っております。その目標というのは設定時点で組織への貢献につながるのかという判断を通過しているため、自分自身が建てた目標=組織への貢献につながる構造となっているため努力が無駄になるという可能性を減らすことができます。
自然とボトムアップの流れができる![]()
個人が自ら目標を設定する仕組みを取り入れることで、各個人から課題やアイデアが自然と上がってくる土壌が形成されます。
転職が当たり前の世の中になっているのでメンバーがそれぞれ異なるバックボーンを持っています。自身の過去の経験や視点から組織に貢献できることを考え目標を立てるプロセスは単なる一人ひとりの目標達成だけでなく、チーム全体の文化としての自律性や創造性の醸成にもつながると考えています。
デメリット
目標設定文化を経験してこなかった人には負担が高い![]()
「目標を設定してください」と突然言われても、何を基準に、どんな粒度で、どんなゴールを設定すればよいのかが分からないというのが、多くの人にとって自然な反応だと思います。
特に、これまで目標設定や振り返りの文化が根付いていない組織にいた人や、新卒に近い若手の場合は、“目標設定する”という行為自体に強い抵抗感や戸惑いを覚えることもあります。
また、「自分がやりたいこと=会社にとって必要なこと」とは限らず、個人の興味関心が組織の目的とリンクしないケースも少なくありません。
たとえば、「新しい技術を勉強したい」「デザインスキルを磨きたい」といった個人の意欲は素晴らしい一方で、それが直接的に今期の事業ゴールやチームの目標と結びつかない場合、どこまでを目標にしてよいのか?という判断が難しい場面が多々あります。
組織の方向性とずれる可能性![]()
個人が自主的に目標を立てられる反面、全社・部署の方針と整合しない目標になってしまうリスクもあります。
特にミッションやOKRなどの上位概念と連動していない場合、チームとしての一体感が薄れ、「それぞれが別の方向を見ている状態」になりかねません。
この課題に関してはまだ解決しておらず、MBOの実践における課題として上がっているところですね。
振り返りの粒度が人によって異なる![]()
振り返りに関しては自己評価を行うのですがここの基準が人によってばらつきが出ます。
何を持って「達成」と見なすのか、ここの判断基準が決められていないとAさんとBさんで振り返り結果にずれが生じてしまします。
なのでこの課題に関しては下記のような共通の評価尺度を決めて運用しております。
- 目標に向けた行動や成果がほとんど見られない状態
- 一部の行動に改善点があり、目標達成にまだ遠い状態
- 目標をほぼ達成しているが、安定性や継続性が不足している状態
- 目標を着実に達成し、安定した成果を継続して出している状態
- 目標を上回り、チームやプロジェクトに貢献しつつ、自身の成長も著しく見られる状態
- 目標を大幅に上回り、新たなチャレンジを自ら見つけ、周囲を巻き込んで成果を達成する状態
あえて抽象的な評価尺度をおくことでどの目標に対してもある程度測れるようにしています。
ただし、抽象的が故に解釈の仕方次第で変わってしまう部分があります。
なので
これらの課題を解決するために次のような運用をしております。
チーム全体で同期的に目標を設定/振り返りをする
MBOの本質が「個人の自律的な目標設定と自己統制」であるとはいえ、それを組織として機能させるには“チームとしての同期”が不可欠だと感じています。
実際、個人がバラバラに目標を立ててしまうと、以下のようなズレが生じることがあります
- チームとしてどこを目指しているのかが曖昧になる
- 他のメンバーの動きが見えず、重複や漏れが発生する
- 評価や貢献度の比較が難しくなる
これらを防ぐため、私たちのチームでは「チーム全体での同期的な目標設定・振り返り」に取り組んでいます。
具体的な取り組み
四半期始めのチーム内での目標設定会
このタイミングでチーム内全員で同期的に時間を作り目標設定を行います。やりたいこととやらなければならないことのバランスと目標が組織貢献ないしは事業貢献につながる内容になっているかなど判断して今期の個人目標を決めていきます。
月に1度行う1on1
この時間は相談事を聞いたり相談したりヒアリングを通してメンバー個々の変化をキャッチします。同時に目標の進捗状況を確認して躓いている理由があればサポートするなど細かい軌道修正を可能にする機械であると思っております。
目標中間レビュー
チーム内で目標の中間レビューを行っております。中間時点での進捗確認を行い、状況に応じて目標の修正を行います。当初の目標に取り組んだ結果実現できそうになかったり、他に優先度の高いやらなければならないことができてしまったり、仕事をする上での変数に対応するために中間レビューの時間を作っています。
四半期終わりにチーム内で目標振り返り会
目標の振り返りを行います。同期的にその目標の進捗とやっことに対して評価を行います。同期的にやることで偏りのない公平な評価ができると考えております。
同期的に行うことの効果
このようにチーム全体で目標や進捗、振り返りを“同期的”に行うことで、以下のような効果を実感しました
- 目標の粒度や方向性に自然と統一感が生まれる
- メンバー間の相互理解や協力関係が生まれる
- 他の人の成長・価値観を見て、自分も刺激を受けるサイクルが生まれる
個人がそれぞれの視点で目標に取り組む一方で、「今期、チームとして何を目指していたか?」「誰が何に挑戦していたか?」を全員がある程度把握できている状態は、非常に健全なチームの在り方なのではと思っております。
まだ少人数のチームだからできているとことだとは思いますが
この考え方を軸におきながら人数増えてきた時や変化の中で最適解を考えて実践していくことが求められるような気がしています。
最後に
リーダーという立場を任され、「どうマネジメントすべきか」に悩むなかで出会ったMBO。最初は手探りでしたが、チームで向き合いながら実践してみて、「人ではなく目標をマネジメントする」という解に辿り着きました。
これらの考え方・取り組みにはまだ課題があるので頼りになるチームのみんなと一緒に考えていき目標設定のあり方を磨いていきたいと思っております。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
目標設定や組織形成に関しておすすめな書籍とかあればコメント欄で教えていただきたいです。