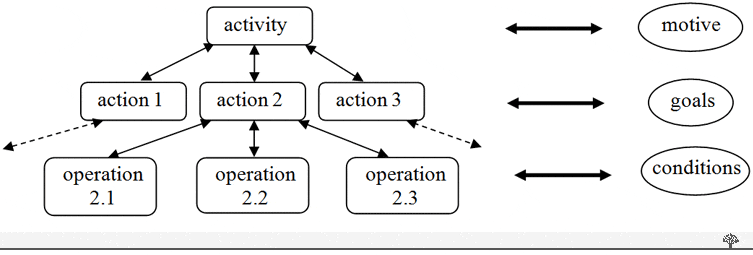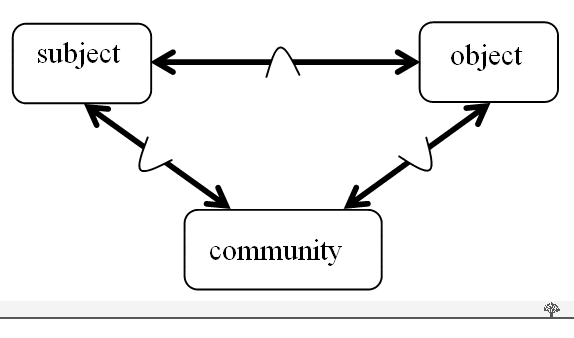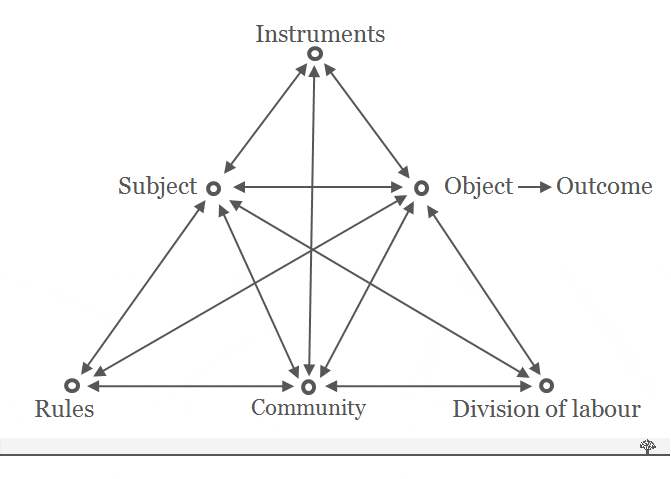※ 個人的メモ
Activity Theory
- https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/activity-theory
- Activityは現在HCI(ヒューマンコンピュータインタラクション)研究における基本的な概念の1つ
イントロダクション
- 活動理論はロシアの心理学における社会文化的伝統に由来する概念的フレームワーク
- ロシアの心理学者Aleksei Leontievによって開発
- フレームワークの基本的な概念はActivityであり、意図的で変容的、そしてアクター(subject)と世界(object)との間の相互作用の発達として理解される
- Leontievの枠組みに基づく活動理論のバージョンは、1980年代にフィンランドの教育研究者YrjöEngeströmによって提案された
- 心理学だけでなく教育や組織学習、分野研究など広く利用されている
Leontievのフレームワークの基本概念と原則
「活動」の概念
- Activityは、広い意味でアクターと世界の相互作用
- 活動理論の専門用語によれば、SubjectとObjectに関連するプロセスとして記述される
Activityを表す一般的な方法は「S⇔O」 - Activityを他のタイプの相互作用と区別するための2つの重要な側面
- ActivityのSubjectsは世界との相互作用を通して満たされるべきニーズをもつ
- ActivityとそのSubjectsは互いに決定する、あるいはより一般的には活動はSubjectとObjectの両方を変換する生成力である
- Subjectsにはニーズがある
- Activityは客観的な世界に存在する重要なSubjectの「unit of life」として理解される
- Subjectsは自身のニーズをもち、生き残るためにActivitiesを実行しなければならない、すなわち自分のニーズを満たすために世界のObjectと対話しなければならない
- Leontievの分析は主に個々の人間の活動に関係していたが、Subjectの概念は個々の人間に限定されず、動物やチーム、組織もニーズに基づいたagencyを持てるため、Activityの対象となる可能性がある
- ActivityとSubjectは相互に決定し、ActivityはSubjectとObjectの属性によって影響される
- ある人が数学の問題を解くことができるかは、問題の性質(どれだけ難しいか)やその人のスキル(どれほど優れた数学者か)に左右されるが、長期的には反対のことも当てはまり、ObjectとSubjectは時間の経過と共にActivityによって変換される。その人の数学のスキルはそれまでの経験の結果であることは明らかであり、数学の問題を解くことを通して発展してきた。
- ある人の数学的能力がその人がどのようにして数学的問題を解決するかを決定するのは事実だが、数学的問題を解決することがその人の数学能力を決定することも事実
- 被験者は自分たちの活動を表現するだけでない。現実的な意味では、それらは活動によって生み出される
基本原則
オブジェクト指向
- この原則は、「Subject-Object」の関係としてのActivityの概念そのものに直接関係している
- Subjectと世界の相互作用がObjectとの相互作用という観点から定義されているのはなぜか→オブジェクト指向の原則による説明
- 世界は構造化されており、客観的に存在する個別のエンティティつまりオブジェクトで構成されており、世界とSubjectとの相互関係も構造化されている
内部化と外部化
- 人間の活動は外部/内部の次元に沿って分配され、そして動的に再分配される
- 人間の活動には内的要素と外的要素の両方が含まれる
- 内在化と外在化(internalization and externalization)は活動の内的要素と外的要素との間の相互変換のプロセスを指す。
- 内在化の過程で、外付け部品は内的になる。
- 幼児はしばしば単純な数学をするために彼らの指を使うが、時間がたつにつれて指の使用は通常冗長になる。
- 経験の浅い運転手は、「縦列駐車」の手順を思い出すために声を出して話すかもしれないが、声を出して話す必要性は練習で消える可能性がある
- 内在化とは反対のプロセスは外在化、活動の内部コンポーネントから外部コンポーネントへの変換
- デザイン案のスケッチなど
- 内部/外部および個人/社会の側面は多くの点で互いに似ている
エンゲストロームのActivity System Model
- Leontievのアプローチは主に個々の人間の活動に関係している
- 活動は個々の人間だけでなく社会的実体(集団)によっても実行される事ができると明確に述べているが、集団的活動の構造と発展を体系的に研究せず概念モデルも提示していない
- Activity System Model(エンゲストロームの三角形)はフィンランドの教育研究者Yrjö Engeströmによって提案された
- このモデルは、Leontievの最初のActivityの概念を2段階で拡張したものである
- 最初のステップとして重要な概念は3番目のノード「Community」を追加する事
- 構造内の3つの相互作用それぞれは特別なタイプの瞑想手段で仲介される
- “subject - object”はtools/ instruments
- “subject - community”はrules
- “community - object”はdivision of labour
- このモデルには、活動システム全体の結果としてObjectから生成されるOutcomeが含まれる
- コンピュータアプリケーションのUIを再設計する上で設計チームの一員として働くインタラクションデザイナの例
- Objectは既存のインターフェース
- 期待されるOutcomeは新しいインターフェース
- デザイナは様々なツールを使用しており、物理的な対象物(コンピュータ)やソフトウェア(開発環境)、方法と技術(ペルソナ)など
- Communityはインタラクションデザイナ、PM、エンジニアなど
- コミュニティとインタラクションデザイナの関係は、明示的または暗黙的なルールで仲介される(プロジェクト会議への参加、特定の報酬のうけとりなど)
- アクティビティシステム全体の結果、新しいインターフェースを作成することは設計チーム全体の責任である
- インタラクションデザイナの作業は他のチームメンバーの作業と調整する必要があり、これは分業を採用することによって達成される
- 複雑な現象を研究する時、1つの活動モデルシステムを適用することは十分ではない、そのような現象は活動システムのネットワークとして表現される
- コンピュータアプリケーションのUIを再設計することは、問題のアプリケーションの新しいバージョンを開発することに向けられた、いくつかの設計チームを含むさらに大規模な努力の1部であり得る。その場合にUIを再設計することは、アクティビティシステムのネットワークの包括的な目的を達成する為に他のアクティビティシステム(製品の新しい機能を開発するチームなど)の結果と統合される必要がある部分的な結果を提供する
- エンゲストロームのフレームワークの重要な原則は、活動システムは常に発展しているということである
- 開発は弁証法的な意味で矛盾によって駆動されるプロセスとして理解されている
- エンゲストロームは、活動システムにおける4つのタイプの矛盾を識別している
- アクティビティシステムの各ノードの内部矛盾
- 医師が使用する調停手段は様々な薬があり、一方では医学的な効果、他方では費用や法規制、流通経路など
- アクティビティシステムのノード間で発生するもの
- 特定の種類の治療は特定の患者には不適切である可能性がある
- アクティビティシステムの既存の形態とその潜在的な、より高度な目的と結果との間の関係において現れる潜在的な問題
- 全体としてのアクティビティシステムの進歩は、既存の組織によって示されるように変化に対する抵抗によって損なわれる可能性がある
- アクティビティシステムのネットワーク内
- アクティビティシステムと共同成果の生成に関与する他のアクティビティシステムとの間の矛盾
- アクティビティシステムの各ノードの内部矛盾