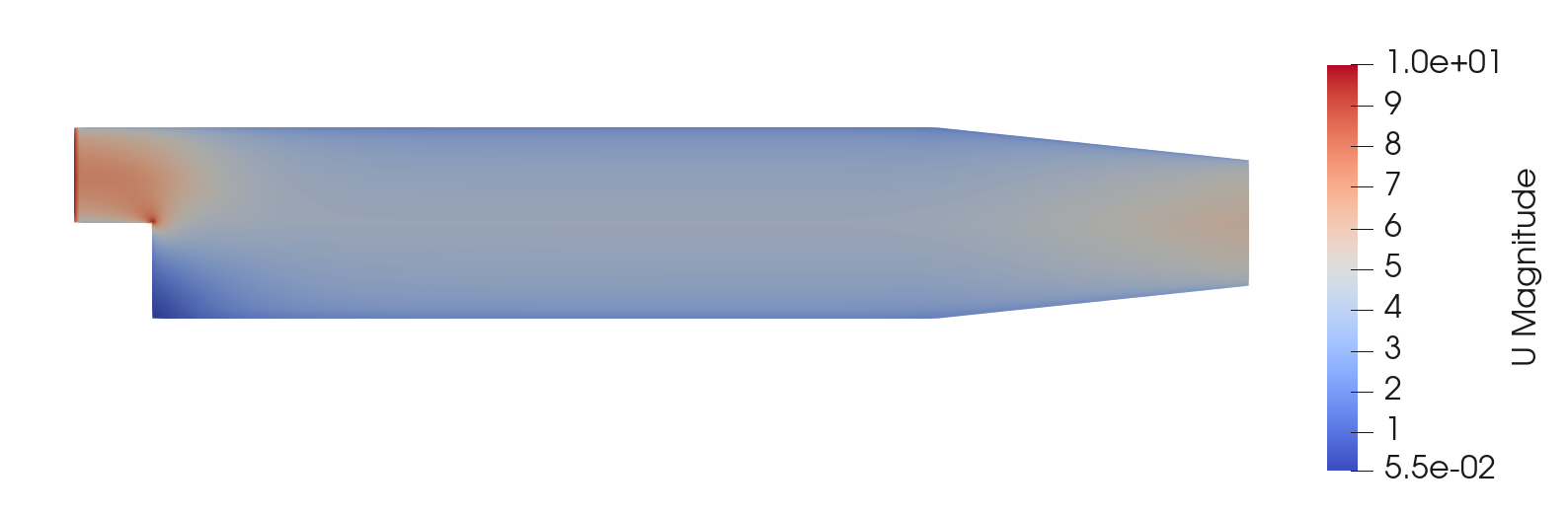はじめに
数値解析においては、初期条件、境界条件を適切に設定することが重要です。OpenFOAMでは、特にこの条件が計算安定性に及ぼす影響は大きいです。
OpenFOAMでは初期条件を作成する方法として、potentialFoam(完全流体流れ)を使用する方法が主流ですが、デメリットとして、(当然ではありますが)境界層がない、流束を過大評価する、があります。
本記事では、OpenFOAM ver.8環境下でpotentialFoam + applyBoundaryLayerを組み合わせた初期条件の設定方法をまとめます。
Step 1: potentialFoam
- Tutorial
pimpleFoam/pitzDailyを作業ディレクトリにコピーします。 - このままでは
potentialFoamが実行できないのでfvSolutionを編集します。
solvers
{
Phi
{
solver GAMG;
smoother DIC;
tolerance 1e-06;
relTol 0.01;
}
}
potentialFlow
{
nNonOrthogonalCorrectors 2;
}
- Step 2: potentialFoamを実行
下図のような境界層が無い流れ場が0ディレクトリに得られます。
applyBoundaryLayer
applyBoundaryLayerは速度場データを元に壁面境界を計算するソルバーになります。
以下はソースの抜粋になります。
// Modify velocity by applying a 1/7th power law boundary-layer
// u/U0 = (y/ybl)^(1/7)
// assumes U0 is the same as the current cell velocity
Info<< "Setting boundary layer velocity" << nl << endl;
scalar yblv = ybl.value();
forAll(U, celli)
{
if (y[celli] <= yblv)
{
mask[celli] = 1;
U[celli] *= ::pow(y[celli]/yblv, (1.0/7.0));
}
}
mask.correctBoundaryConditions();
Info<< "Writing U\n" << endl;
U.write();
ここに記載している通り境界層を__「$1/7$乗則」__で計算します。
使用方法ですが、以下のようにオプションをつけて実行するのみです。
applyBoundaryLayer <option>
- options
- -Cbl scalar
- -ybl scalar
前者は壁面からの平均距離(第1層のメッシュ厚さ)にオプションで指定した値を乗じたものを境界層厚さとします。後者は境界層厚さをそのまま指定することになります。
その他、詳細はここを参考にしていただければと思います。
あとは、fvSchemesにwallDistの設定を追記すれば良いです。
wallDist
{
method meshWave;
// Optional entry enabling the calculation
// of the normal-to-wall field
nRequired false;
}
上図がapplyBoundaryLayerによって得られた速度場の初期条件になります。先のpotentialFoamの結果と比べて、よりリーズナブルな速度場(境界層があり、かつ、速度の過大評価が是正されている)が得られていることがわかります。
なお、対象が乱流のcaseであれば、乱流パラメーターも計算してくれます。
さいごに
解析が発散するような場合は、離散化や線形ソルバーの見直しも必要ですが、このような初期条件の見直しも有効だと思います。