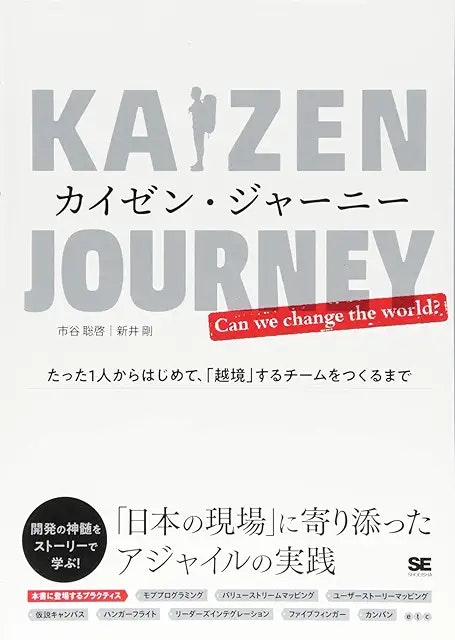はじめに
書籍「カイゼンジャーニー」を読みました。
自分にとって紛れもない良書でした。
書籍だけの学びはすぐ流れてしまうので、感想文を残しています。
(ネタバレに当たる内容があるかもしれないので、ご注意願います。)
第1部 一人から始める
主人公(江島)が一人であれこれアジャイル開発の手法を試みて、
最後に一人の限界を感じるところで終わる部です。
「分割して、統治せよ」という言葉が印象に残ってます。
取り扱っている主なプラクティス
- タスクマネジメント、タスクボード、朝会、ふりかえり
- 緊急・重要のマトリクス
- 1on1
仕事をよりうまくやるためには一体何からやったら良いか?と聞かれることは少なくない。
そのとき、私が挙げるのは次の4つ、タスクマネジメント、タスクボード、朝会、ふりかえりだ。
なぜ、この4つなのかというと、仕事のカイゼンは、まず状態の見える化から始めるべきだからだ。
4つのプラクティスのうち、時間がないとふりかえりを最初にやらなくなることが多い。
しかし、私としては他の3つよりもむしろ、ふりかえりだけは続けることようにした方が良いと考えている。
ふりかえりがなければ、仕事のやり方に向き合い、より良くする機会を失ってしまうからだ。
第2部 チームで強くなる
個人的に印象深い部でした。
話の流れの中でそれまで続けていたある取り組みを止めるのですが、
個人的に最近考えている
「アジャイル開発とはアジャイル開発のプラクティスを行うことではなく、チームがそういう状態になることではないか?」
という問いに答えてくれた気がします。
アジャイルな状態になるためにはどうしたら良いのか?という問いには、
「開発メンバーが開発する時間を多く取れるように各プロセスを効率化すること」
もあれば、
「メンバーが各々の強みを生かせるように星取表を作って、強み弱みを共有すること」
もあると思います。あるいは、
「誰かが仕様の窓口になって、メンバーは開発に集中できるようにすること」
かもしれません。
開発で成果を出さないといけないので、まずは時間を確保するのが第一かもしれません。
質を保持しないと後半で失速するのでレビューの時間を綿密に持つことが必要なのかもしれません。
詰まるところ、フレームワークはないので目的の状態に達するためにプラクティスを維持する必要はないのだと思いました。
取り扱っている主なプラクティス
- スクラム(スプリント、スプリントプランニング、デイリースクラム、スプリントレビュー、スプリントレトロスペクティブ)
- インセプションデッキ
- Working Agreement
- ドラッカー風エクササイズ
- ファイブフィンガー
- リファイメント
- 狩野モデル
- むきなおり
- 星取表(スキルマップ)
- モブプログラミング
- バリューストリームマッピング
- カンバン
- ポストモーテム
- タックマンモデル
チームやプロジェクトが立ち上がるチームビルディングの初期段階で、
星取表を作成するのが良いだろう。
これまで紹介した3つの取り組みをセットにすることでプロジェクトとチームメンバーとスキルが一気に共有できる。
チームビルディング三種の神器だ!
・インセプションデッキ: プロジェクトやプロダクトの目的や方法論
・ドラッカー風エクササイズ: チームメンバーの価値観
・星取表: 目的を達成するために必要なスキル
第3部 みんなを巻き込む
主人公が自身がリーダーを務めるPJを成功に導くために
あらゆるステークホルダーとの交渉・折衝を行っていくのがこの部のメインだと思います。
スーパーSEというかコンサルというかかなり難易度が高く勇気がいる行動を繰り返しています。
(ただ、真に優れたリーダーやPMの取る行動ってこれなのかなとも思いました...)
多分、一つ一つを実践するだけでも相当難しいですが、
大事なのは度々出てくる言葉「越境」なのかなと思います。
取り扱っている主なプラクティス
- リーダーズインテグレーション
- モダンアジャイル
- プランニングポーカー
- パーキンソンの法則
- CCPM
- スクラムオブスクラム
- デイリーカクテルパーティー
- ユーザーストーリー
- 仮説キャンバス
- ユーザーストーリーマッピング
- MVP
- ユーザーインタビュー
- SL理論
- ハンガーフライト
まとめ
各部ごとに印象に残った部分の感想をまとめましたが、
自分にとっては「越境」という言葉が全てだったのかもしれません。
おそらく誰しもが自分が大変な時に相手の越境を受け入れたり、
自分から越境することを行うのは難しいことだと思います。
越境か境界線を引くかは普段の業務の中でも常にせめぎ合いですが、
エンジニア経験の中で「越境」出来たプロジェクトが楽しく、
自分自身が評価をいただけたことが多いので、
2020年は「越境」をキーワードに頑張ろうかと思えました。