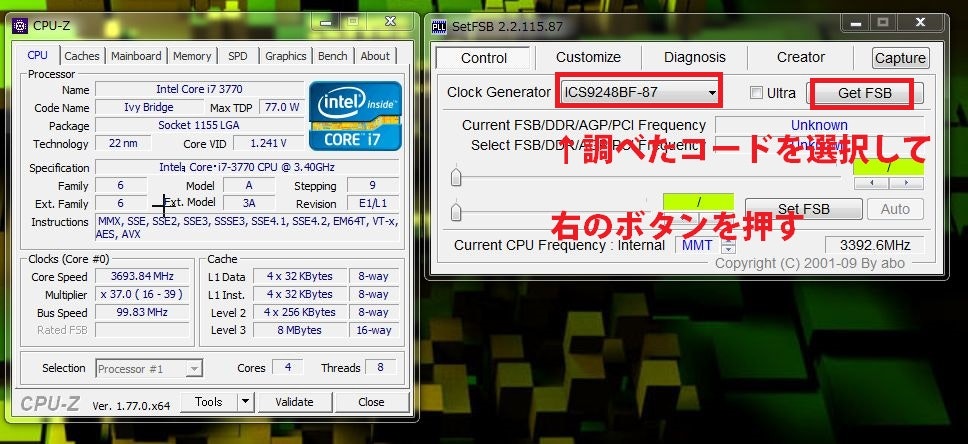古くてもう壊れてもそんなに問題ないパソコンだけど、
限界まで使い倒したい、けれども重すぎて使う気がおきない。
なんでそこで諦めるんだよ。もっと熱くなれよ(CPU的な意味で)
というわけでオーバークロックを試してみた記録をここにまとめます。
オーバークロックとは?
定格で動いているCPUにたいして、
もっと本気だせよと鞭打つ行為とイメージして頂けるとわかりやすい。
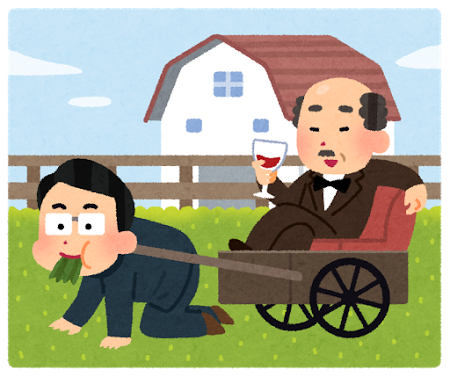
オーバークロックにはリスクが伴い、
マザーボードやメモリなど他の機器にも負荷がかかるので、
行う場合にはリスクを承知の上で行いましょう。
普通のパソコンならば・・・
BIOS画面(Windowsを起動したときになんらかのキーを押下するといける画面)にて設定可能なのだが、DELLなどのメーカ品パソコンの場合などはBIOSレベルで制御されており、オーバークロックが行えないようになっている。
しかしもう一つ裏道とも言える手法が残っているので、今回はそれを紹介する。
※当然の如くメーカーのサポート対象外になるので自己責任でお願い致します。
具体的やり方
1 Clock Generatorを確認する
まずパソコンの蓋をあけて「Clock Generator」(通称PLL?)のコードを確認する。
以下の記事を見る限り、水晶発振子というパーツを目印に探すのが良さそうです。
http://jizounokimagure.at.webry.info/201007/article_1.html
2 作業用のツールを用意する
様々なツールといろいろなやり方があるそうだが、
今回は恐らく初心者がやりやすいであろう以下の2つのツールを使ってオーバークロックを行う。
CPU-Z(CPUの状態を表示するソフト)
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/hardware/se492853.html
setFSB(オーバークロックを行うソフト)
http://www.vector.co.jp/soft/win95/hardware/se453950.html
上記2つのソフトをダウンロードしたら、両方とも起動する。
GetFSBボタンを押下して正常に認識すると以下の画像の部分に値が入り、メモリをいじくれるようになるので、初期値をメモしておくと良い。
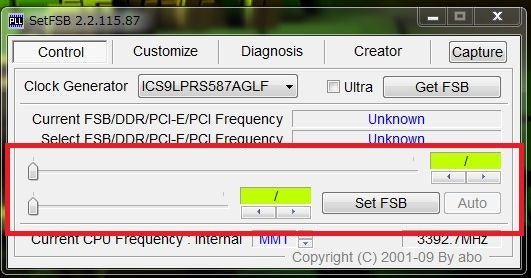
3 オーバークロック開始!
上のつまみを右に対して少しずつ、こまめに動かして「SetFSB」ボタンを押下する。
つまみを右に動かせば動かすほどCPU-ZのCore Speedがガンガン上昇していくのが確認できる。
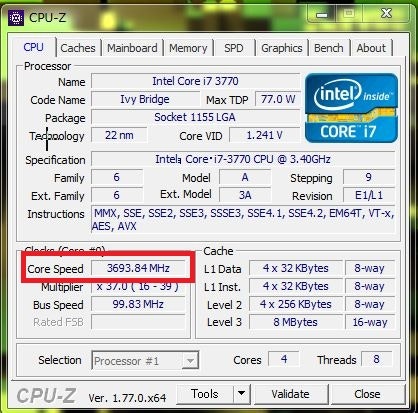
右につまみを動かしてsetFBS
右につまみを動かしてsetFBS
右につまみを動かしてsetFBS .....これを繰り返す。
そうしてるうちに限界ポイントに到達し、システムが不安定(フリーズOR強制終了)する位置までくるので、そこがオーバークロック限界点でとなる。
4 システムがフリーズしまくって(再起動しまくって)設定なおせない\(^o^)/
BIOSでオーバークロックの設定はいじれないが、BIOSの初期化はできるので
落ち着いてPCを再起動し、BIOSのデフォルト化のボタンを押下すればクロック数は元に戻る。
以上のサイクルを通して、
もっともシステムが安定する、
かつコアスピードをあげられる地点を指定して固定ができればオーバークロックは完了となる。
以上、快適なPCライフを!