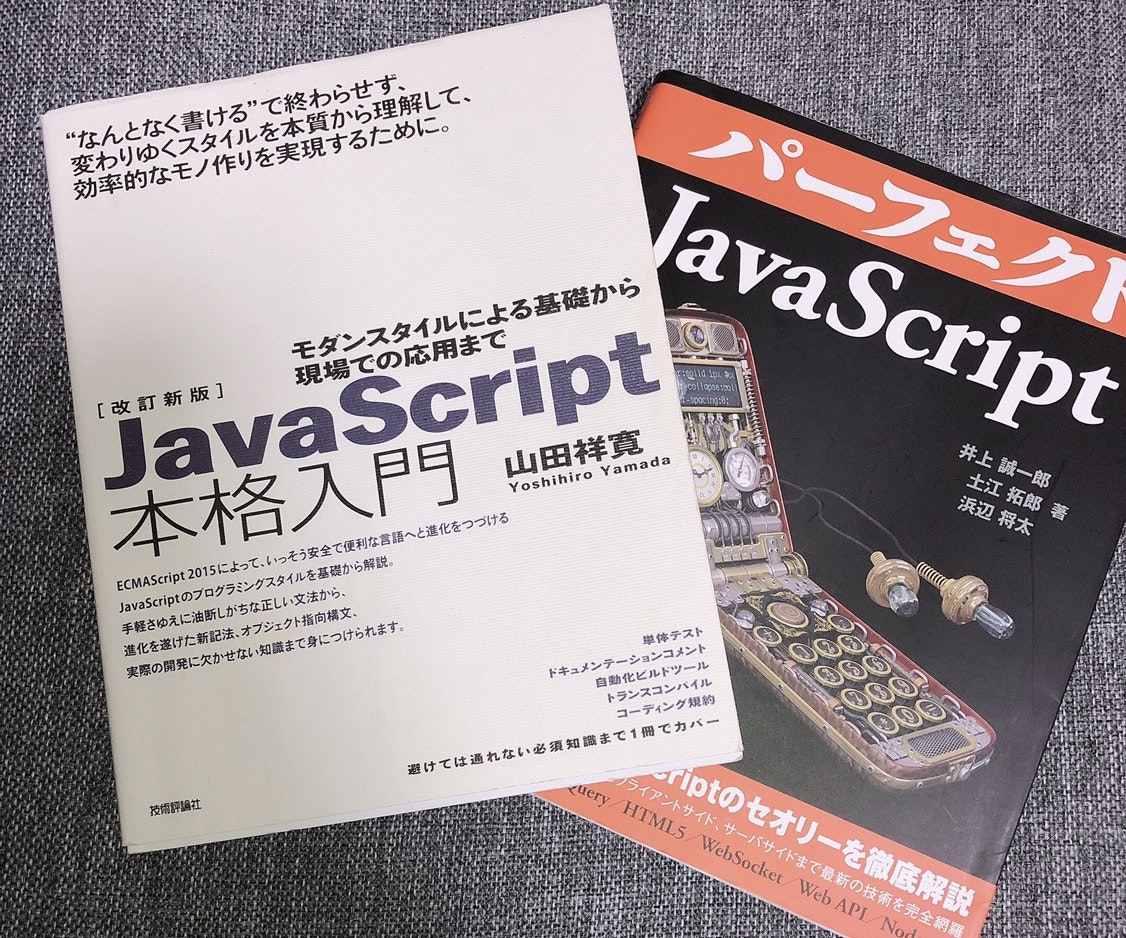友人が、「転職する気がなくても読んでおいたほうがいい」と強く念押ししていた書籍を購入。
転職の思考法。
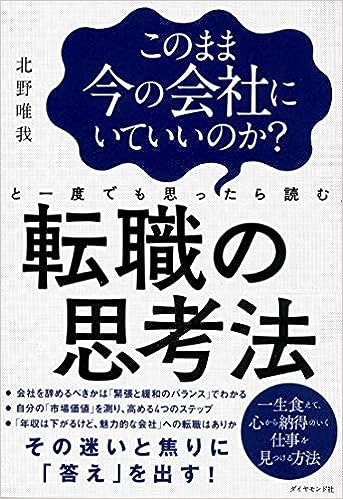
この本は社会人として働き続ける上での知恵を説いている本なので、生き残る術を身につけるためにも役立つ内容でした。私は1年前に今の事業会社に転職して3社目なのでまだ転職を意識していないですが、読了して自分の考え方にまた変化が出てきたので良かったです。
自分の備忘録的にまとめつつ、決意表明も少し書き記します。
会社を変えても価値のあるスキルをどれだけ持っているか
自分のマーケットバリュー(市場価値)を測る上で重要な項目の9つあるうちの1つ。
結構このキーワードに大事なことが集約されていると思うし、会社員として働き続ける上で常に意識しなければいけない点だと思いました。
会社に帰属している以上コミットメントしてアウトプットしているけれども、それは自分自身のスキルを高めるものなのか、それともその"企業に所属している自分"のスキルを高めるものなのかによって大きく変わります。後者の場合は、そのスキルが市場価値を高めることにつながらないので、注意が必要です。特に分業化が進んでいる大企業などはルーチンワークが作業の大部分を占めていたり、会社の風習で習慣となっているデザイナースキルとは直接関係のない仕事などが増えてくると、本来高めたいスキルに割く時間が減ってしまいます。
自分はbeing型(どんな人でありたいか、どんな状態でありたいか)の人間だった
人間はtodo型とbeing型の2パターン存在していて、99%の人間はbeing型である。と書かれていて、自分の中の霧が少し薄くなったような感覚になりました。ホリエモンと落合さんの「10年後の仕事図鑑」という本を読んだ時、「自分の好きなもの(夢中になるもの)を掛け合わせて専門性を高めることでオリジナリティを出し、その個性を前面に出して戦っていく」といったような内容が書かれており、その重要性を理解したものの自分に当てはめたときにこれと言ったものが浮かびませんでした。
で、この本を読んだ時、あぁそれが指していたのはtodo型の人間への道しるべなのかも知れないと理解しました(解釈の仕方が間違っているかもしれませんが...)
だからこの本に書かれているようにbeing型の人間は「心からやりたいこと」がなくても悲観する必要はなく、自分の状態と環境の状態を整えつつ、小さなやりたいことから見つけていけばいいのだと思いました。
20代は専門性、30代は経験、40代は人的資産でキャリアを作れ
20代というともうすぐ終わってしまうんだけれども(笑)、30歳になる2019年は専門性を高めることに集中する一年にと決めました。その理由は現職での専門性がまだまだ高められていないと危惧しているからです。具体的な目標でいうとHTML5プロフェッショナル認定試験 Level2の合格。試験内容はほぼJavascriptでしかもソースコードを読み解いて答える問題が多いとのことなので、普段業務でJSのソースに慣れていないと時間が足りずにタイムリミットが来てしまうそう...。
私の場合は、HTML5とSassを使ったコーディングやたまにUI設計をするといった業務内容なのでJSはほぼ使うことがないです。前職では、jQueryやNode.jsなどに触れる機会があったのですが、使わなくなってからほぼ忘れていてまずいなぁと思っていました。でもこの本を読んで、専門性を高めることの重要に改めて気付かされ、Webデザイナーの私が高めたいものがJSだったのでこれを機に受験します。
ひとまずこの2冊の本を読み返して忘れ去られていたJS脳を呼び起こし、認定教材となっているテキスト、HTML教科書 HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル2 スピードマスター問題集 Ver2.0対応で実力をつけつつ、試験に臨みたいと思います。
最後にこの本を通して、自分の心に刺さったキーワードを備忘録がてら書き記しておきます。
この本から学ぶことがとても多かったので紹介してくれた友人には感謝です。
- 他人の作った船に自分の人生を預けるな
- 伸びている(成長が見込める)産業にピボットする
- 他の会社でも通用する「レアな経験」がどれだけあるか。その経験は、世の中からどれだけ「強いニーズ」があるのか。
- 自分の所属しているマーケットに成長性はあるか
- 「働きやすさ」は「マーケットバリュー」と相反しない。むしろ長期的には一致する