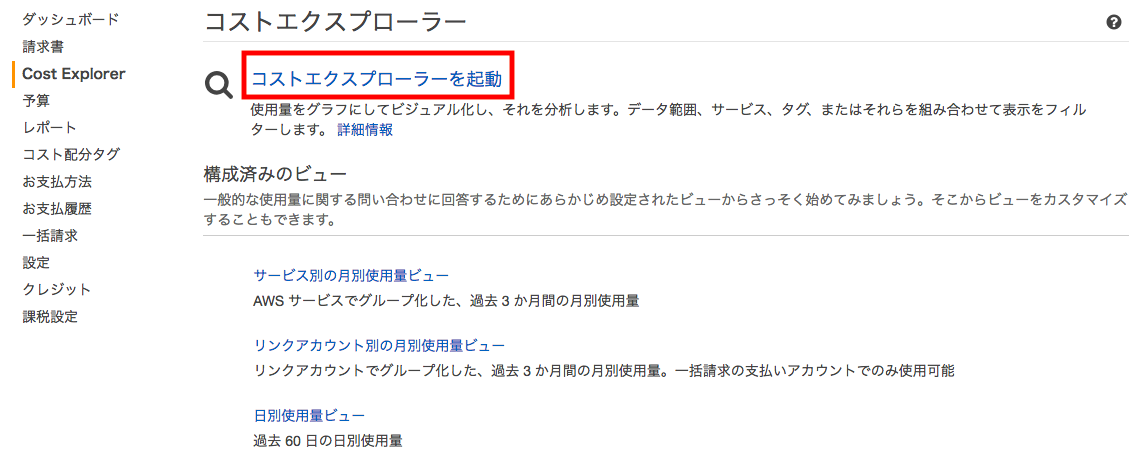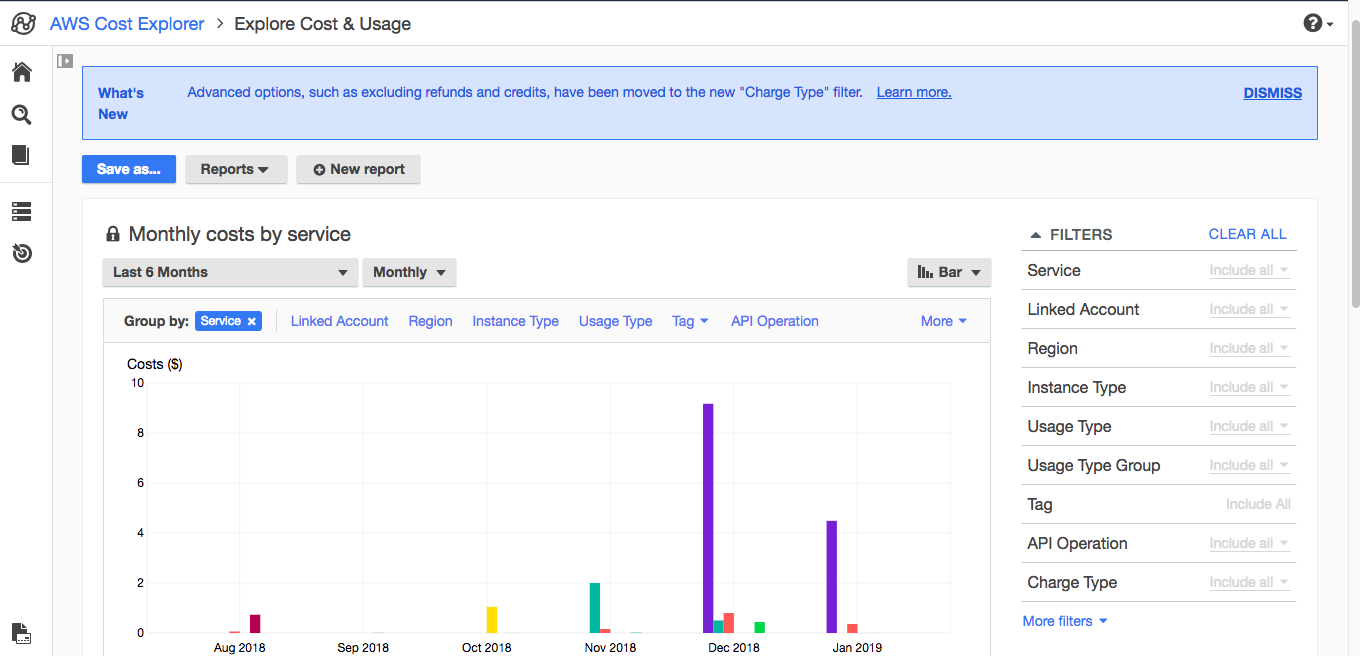具体的な料金については変動があるため、記載しません。
利用の際はAWSの各サービスのサイトを確認しましょう。
1.基礎##
実際の必要なリソースの量、使っているリソースの量に応じて料金を支払うということになります。
- 従量課金制
- 予約による値引き
- 使うほど値引き
- AWS拡大に応じて値下げ(スケールメリット)
2.AWS無料利用枠##
一部のサービスは1年間、無料で利用できます。
詳細は↓のサイトを見て見ましょう、そして、とりあえず利用して見ましょう。
AWS無料利用枠
3.追加料金なし##
一部のサービスでは料金は発生しません。
例えば、Amazon VPC。
ただし、Amazon VPCにつくられたAmazon EC2などはもちろん料金は発生します。
他にはこんなサービスもあります。
・AWS Elastic Beanstalk
・AWS CloudFormation
・AWS IAM
・Auto Scalling
・AWS OpsWorks
4.支払いの対象となるもの、ならないものの基本的な考え方##
-
支払いの対象となるもの
-
コンピューティング
-
ストレージ
-
送信データ転送 → AWS Data Transfer Out という明細で記載されます。
-
支払いの対象とならないもの
-
受信データ転送
-
同一リージョン間でのサービス間のデータ転送
5.AWS間のデータ転送##
- インバウンドデータ転送は、すべてのリージョンにおけるすべてのアマゾンウェブサービス全体で無料です。
- 同じリージョン内のアマゾンウェブサービス間でのアウトバウンドデータ転送に料金はかかりません。
6.見積もり##
提供しているツールは3つ。
7.請求ダッシュボード##
AWSアカウントを作成したら、「請求ダッシュボード」を登録することを忘れずに!
CloudWatch の画面が開くので、「請求アラームを作成すると」をクリックし、請求アラームに必要な条件を入力して設定してください。
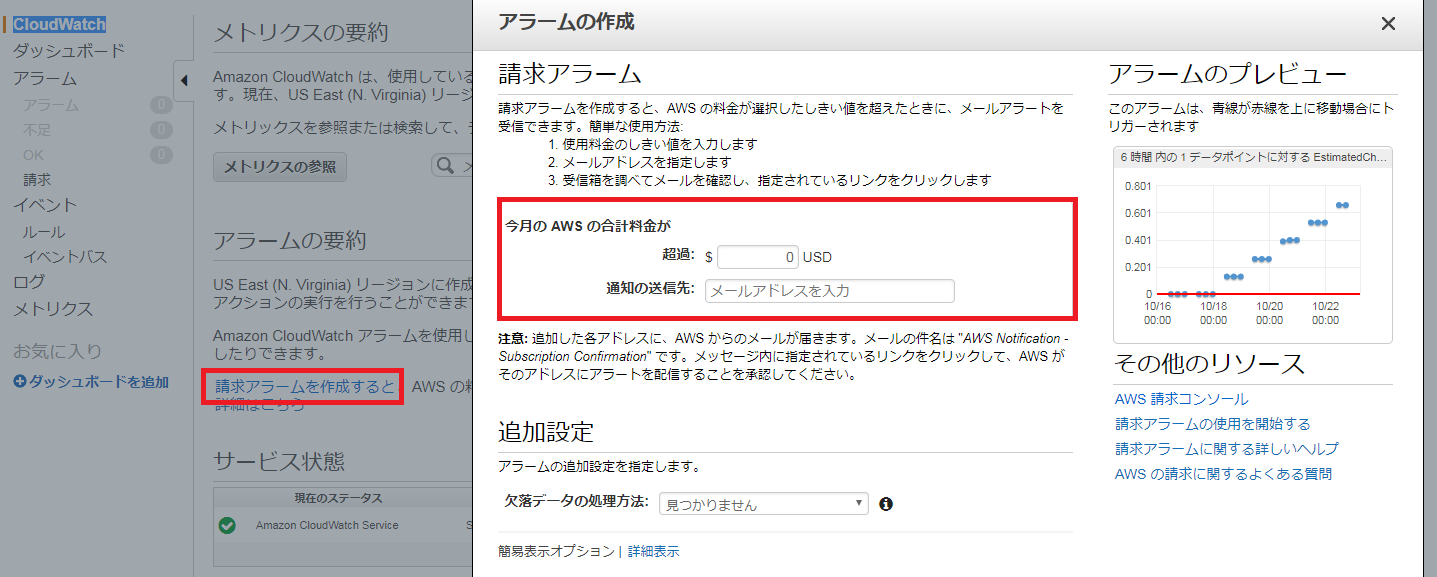
8.料金の調べ方##
-
pricing で検索しサービスごとに調べる。
-
Amazon Web Services Simple Monthly Calculator を利用する。
9.AWS Cost Explorer##
経済的変化を可視化できるツールです。