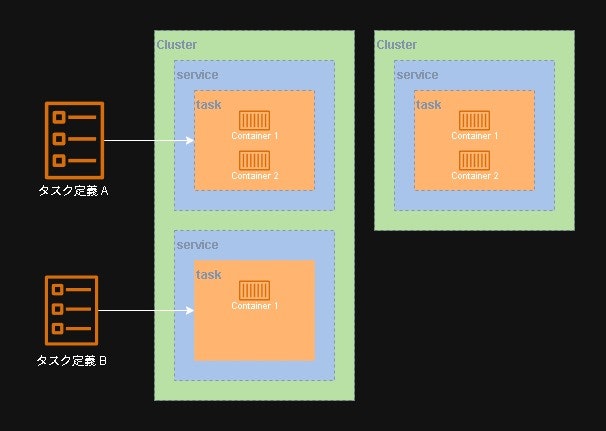Amazon ECS(Elastic Container Service)
概要
-
AWSが提供するフルマネージドなコンテナオーケストレーションサービス
-
コンテナを簡単にデプロイ・管理・スケーリングできる
-
代表的な起動タイプ
- EC2起動タイプ:EC2インスタンス上で動かす
- Fargate起動タイプ:サーバーレスで基盤を意識せず動かす
ECSの主要コンポーネント
1. クラスタ(Cluster)
- ECSの基盤となる入れ物
- タスクやサービスを実行する場所
- EC2インスタンスやFargateリソースをまとめる単位
2. タスク定義(Task Definition)
-
タスクの設計図
-
記載する内容:
- 使用するDockerイメージ
- CPU・メモリの割り当て
- 環境変数
- ポート設定
- コンテナ数(1つ以上)
3. タスク(Task)
- タスク定義から実際に起動したインスタンス
- 実際にアプリケーションが稼働する単位
- 1つのタスクの中に複数のコンテナを含めることも可能
4. サービス(Service)
-
タスクを安定稼働させる仕組み
-
機能:
- 指定した数のタスクを維持(オートヒーリング)
- ALB/NLBと連携してロードバランシング
- ローリング更新やブルー/グリーンデプロイ
-
サービスなしで単発タスク実行も可能(バッチ処理など)
5. コンテナ(Container)
- 実体のアプリケーション
- タスク内で動くプロセス
- Dockerイメージから起動
- サイドカー構成(例:アプリ+ログ収集)も可能
関係性イメージ(テキスト図解)
ECS クラスタ(Cluster)
│ ← コンテナを動かす基盤(EC2/Fargate)
│
├─ サービス(Service)
│ │ ← タスク数を維持・デプロイ管理
│ │
│ ├─ タスク(Task)
│ │ │ ← タスク定義から起動された実体
│ │ │
│ │ ├─ コンテナ(Container)
│ │ │ ← アプリ本体
│ │ └─ コンテナ(Container)
│ │ ← サイドカー(ログ収集など)
│ │
│ └─ タスク(Task)
│ └─ コンテナ(Container)
│
└─ (サービスを使わず単発で動かすタスクも可能)
- クラスタ = 実行基盤(工場)
- タスク定義 = 設計図(どんなアプリをどう動かすか)
- タスク = 設計図から実際に動いたインスタンス(生産ライン)
- サービス = タスクを管理して安定稼働させる仕組み(工場の監督)
- コンテナ = アプリケーションの実体(機械)
ECSのローリングアップデート(Rolling Update)
- ECS サービスに対して新しいタスク定義を適用すると、古いタスクを順次停止し、新しいタスクを起動していく
- これにより「アプリを落とさずにバージョンを切り替えられる」
制御パラメータ
サービス定義時に次の2つを設定できる:
-
minimumHealthyPercent
- デプロイ中に「最低限維持すべき稼働中タスクの割合」
- 例: 100 → 現行タスクを止める前に必ず新タスクを立ち上げる
-
maximumPercent
- デプロイ中に「最大で何%までタスクを増やして良いか」
- 例: 200 → 一時的に2倍までスケールアウトして更新
-
例:サービスに10タスクがあるとき
- min 50%, max 200% に設定すると、更新中は 5〜20タスクの範囲で入れ替え が進む
ECSのスケーリング
ECSのスケーリングには大きく2種類あります。
1. Service Auto Scaling
-
タスク数を自動でスケール
-
トリガー例:
- CPU利用率が70%を超えたらタスクを+2
- SQSのキュー長に応じてタスク数を増減
-
EC2起動タイプでもFargate起動タイプでも使える
-
アプリケーションレベルのスケール
2. Cluster Auto Scaling(EC2起動タイプの場合)
- クラスタに属するEC2インスタンス自体をスケール
- Service Auto Scalingでタスク数を増やすと、インスタンスが足りなくなる場合あり
- その場合、自動的にEC2インスタンスを追加起動してキャパシティを確保
- インフラレベルのスケール
(Fargate起動タイプではAWSが基盤を管理するので、クラスタスケーリングを意識する必要なし)
Amazon ECS vs Amazon EKS
共通点
- どちらも AWSのコンテナオーケストレーションサービス
- コンテナをデプロイ・スケーリング・管理する基盤
- Fargate を利用すれば両方とも「サーバレスでコンテナ実行」が可能
ECS(Elastic Container Service)
- AWS独自のオーケストレーションサービス
- タスク定義 / サービス / クラスタ というシンプルな概念
- 学習コストが低い(AWS独自用語だけ理解すればOK)
- 他のAWSサービス(ALB, CloudWatch, IAM, App Meshなど)とシームレス統合
- Kubernetesの知識が不要
EKS(Elastic Kubernetes Service)
- マネージドKubernetes(オープンソースK8s互換)
- Kubernetes API がそのまま使える(kubectl / Helm / ArgoCDなど)
- 移植性が高く、オンプレや他クラウドのKubernetesともほぼ同じ運用が可能
- ただし学習コストが高い(Pod, Deployment, Service, Ingress, Namespace... などK8sの概念が必要)
- 運用管理も複雑になりがち
ECS vs EKS 比較表
| 項目 | ECS | EKS |
|---|---|---|
| 管理モデル | AWS独自(シンプル) | 標準Kubernetes |
| 学習コスト | 低い(AWS知識中心) | 高い(Kubernetes知識必須) |
| AWS連携 | ネイティブ統合が強い | 追加設定が必要な場合も |
| 移植性 | 低い(AWS依存) | 高い(他クラウド/オンプレ可) |
| 規模 | 小〜中規模向き | 中〜大規模、マルチクラウド向き |
| 起動タイプ | EC2 / Fargate | EC2 / Fargate |
ポイント
- ECS = AWS専用、シンプル、学習コスト低
- EKS = Kubernetes標準、移植性高、複雑
- どちらもFargateでサーバレス実行可能
- マルチクラウドやK8s運用経験がある場合はEKSが適切