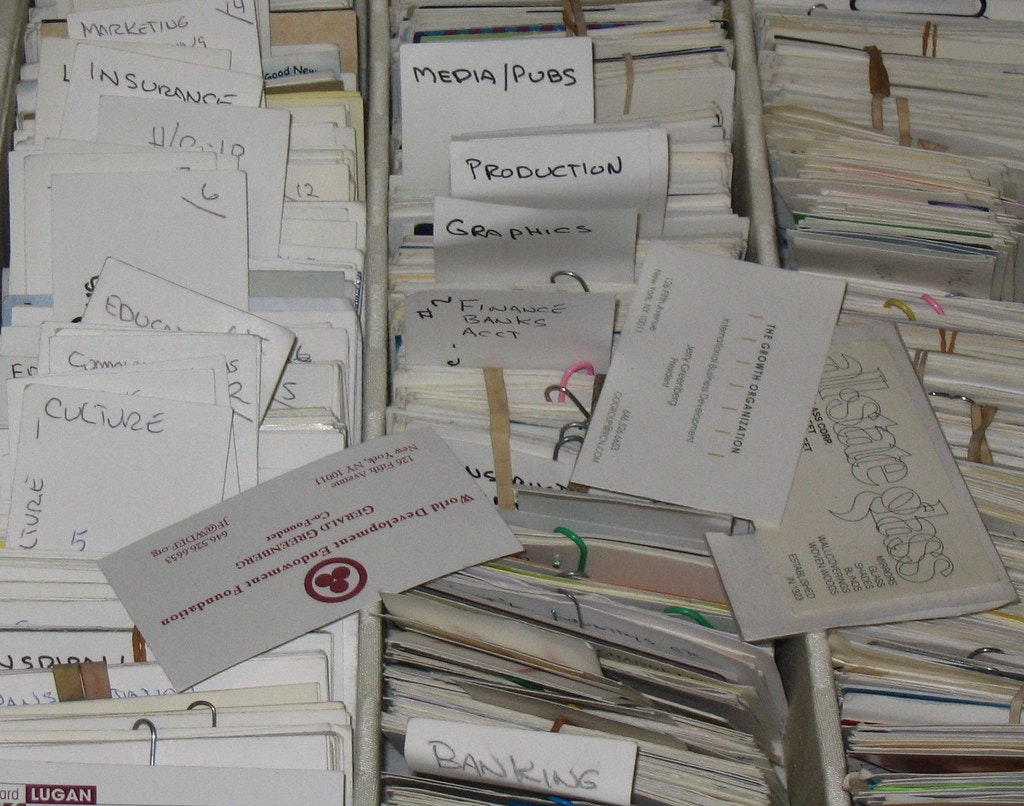
最近、自治体で運用されているデータベースを使わせていただく機会が増えました。それぞれのデータベースは大変優れたもので使い勝手の良いものです。しかし、その運用には疑問を感じています。
データベース間の移動は紙が原則
私が経験したデータベースを使用したワークフローは以下のようになります。
- データベースから集計表を出力(紙媒体)
- 取り出した集計表(紙媒体)をエクセル一覧表に入力
- エクセル一覧表を出力(紙媒体)
- エクセル一覧表(紙媒体)のデータを別のデータベースに入力
冗談のようですが、データベースを使用していながら、2回も同じ内容を手入力しています。
データベースは素人でも運用はプロ
同じ自治体でも私が以前勤務していた図書館の蔵書データベースは素人がつくったものでしたが、運用はしっかりと考えられていました。たとえば登録作業は以下のようになります。
- バーコードリーダーでISBNコードを読み取ってcsvファイルに送る
- ISBNコードの入ったcsvとアマゾンの書誌情報をマッチングさせる
- バーコードで本の登録番号を読み取って書誌情報の入ったcsvに登録番号を入力する
- csvファイルを蔵書データベースにインポートする
人間はキーボードを触らないので、本の取り違えをしなければ間違いは発生しません。
100冊くらいの本なら30分で登録作業が完了します。
この仕組みはデータベース素人の職員が試行錯誤しながら考えたものですが、運用はプロですからとてもよく考えられていました。
2度も手入力するのは過酷です
最初に紹介したデータベースはエクセル以外はすべてプロが作った高価なものです。しかし、データ運用の一貫性が考慮されておらず、途中の2回はフル手入力になります。集計結果が紙ベースなので、最初のデータベースの出力と最後のデータベースの入力が一致しているかどうかを知るすべはありません。
電卓と目視の確認がたよりの過酷な作業です。
電子データは一貫して電子データとして流す
近年、国や県の業務が次々と権限委譲で自治体に降りてきています。個人情報を含む大切な情報を扱う作業です。間違いも許されません。このような作業を遅れず間違わずにこなしてきた前任者には本当に頭が下がります。
しかしながら、そうした職員をささえるデータベース運用はとても悲しいことになっています。
個人情報の取り扱いの問題を考えても、紙媒体を基本とする作業では多くのミスコピーが発生します。電子データの流出も大きな問題ですが、個人情報が記載されたミスコピーが何十枚も発生する環境も大きな問題です。
役所ですから、作業の最下流(決裁やお知らせ文書)が紙媒体になることはやむを得ません。しかし、中間で多量の紙が発生し、情報流出を誘発する環境は好ましいものではありません。電子データはワークフローの最下流まで一貫して電子データとして流さなければなりません。
こうしたデータベース運用を見直すだけで、自治体業務の効率が大きく向上する可能性を感じています。