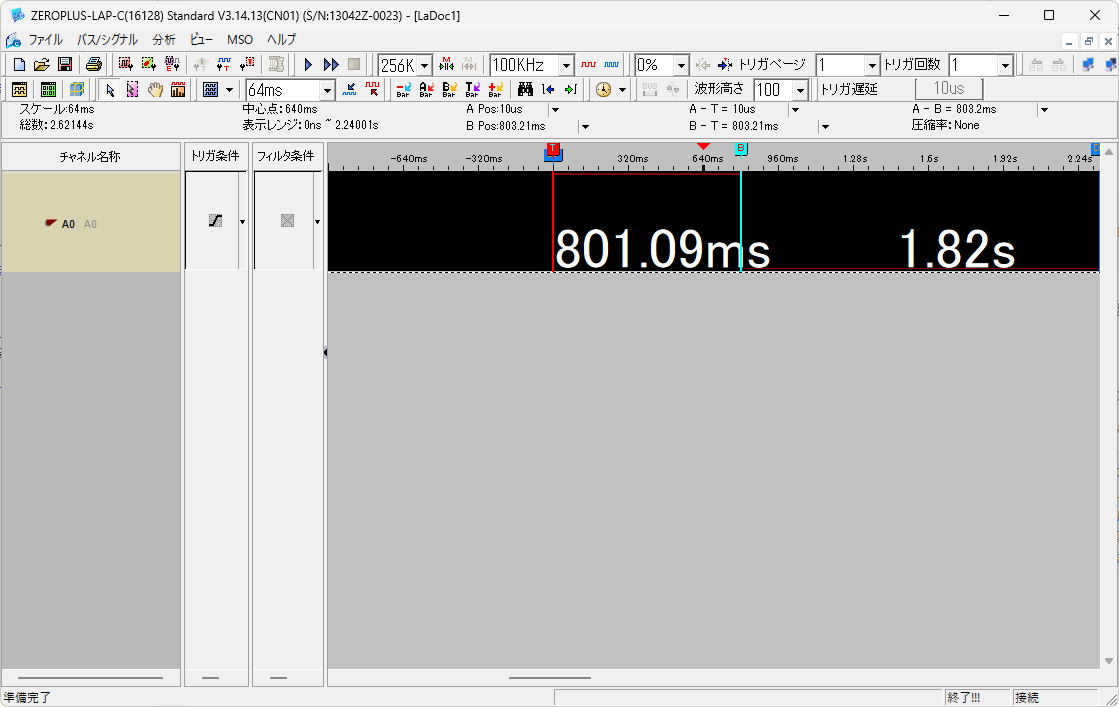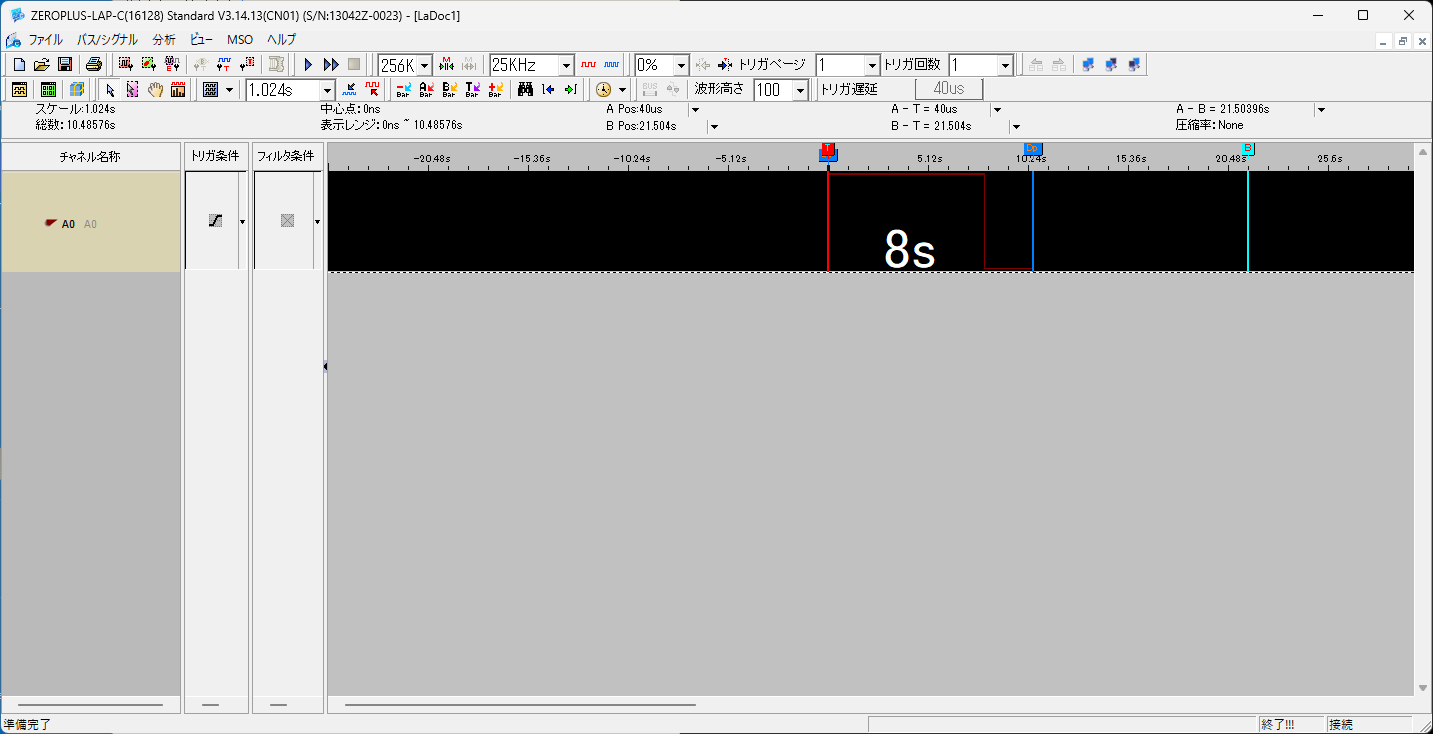NanoKVMとは?
PiKVMに継ぐ次世代のKVMツールである。高価なサーバについているIPMI(リモートコンソール、物理スイッチ操作、ISOマウント)を提供する。(以下、Nano KVM FullをFull、NanoKVM LiteをLiteと表記する。)
NanoKVMにはLiteとFull版が存在しており、Lite版では下記の機能が去勢されている。
- 外部電源供給
- 電源供給とマウス・KBが同じUSBポートで兼用になる。PCを再起動するとLiteがリセットされてしまい、UEFI画面などが操作できない。
- ATX電源操作
- Fullではマザーボードのピンヘッダーを直接操作して電源ONできる。LiteではIOボードが付属しないので自分で何とかする必要がある。
- 液晶
- IPアドレスなどを表示するOLEDがついていない。
Full版を購入された方のレビューはたくさん上がっている。
FullとLiteのHWは共通となっている。そこで、とりあえず格安のLite版を購入し、Full版との違いを確認する。
ハードウエア
LicheeRV Nanoがベースとなっている。マイコンボードの詳しい資料は
https://wiki.sipeed.com/hardware/zh/lichee/RV_Nano/1_intro.html
より確認できる。
ピン配
ファームウエア
https://github.com/sipeed/NanoKVM/releases
からダウンロードする。最新版をWin32DiskimagerなどでMicroSDへ書き込む。今回は、20241120_NanoKVM_Rev1_3_0.imgを使用。
IPアドレス探索
何らかの方法でIPアドレスを特定する。公式の手順は下記を参照すること。
https://wiki.sipeed.com/hardware/zh/kvm/NanoKVM/system/updating.html#%E8%8E%B7%E5%8F%96-IP
初期パスワード
WEB UIの初期パスワードは
- admin / admin
SSHの初期パスワードは
- root / root
どちらも脆弱なので、落ち着いたら直しておくのがよさそう。
外部電源
まず外部電源を供給できるようにする。適当なUSBケーブルを切って、VSYSとGND間に5VをつなげばOK。
PoEを用いる場合は、PoEスプリッタがアマゾンで手に入るのでそれを使う(5V版を選択すること)
VBUSとVSYS間には0オーム抵抗でショートされている。もしかすると0オーム抵抗は取ったほうがいいのかも?とりあえず取らずに動作している様子。
ATX電源操作機能
ファームウエア上は生きている。GUIより操作すると、ATX PWRやRST出力がHIGHになる。しかし、ピン配列が微妙に誤っているようで(?)、公式情報でRSTとなっている端子がPWR、GPIOA22として未使用になっているポートがRSTになっているように見える。
テスター当ててみた感じ、おそらくこんな感じ?(ファームによって異なる?。利用は自己責任で、必ずテスターを当ててから行ってください。)
周辺回路を作れば、ATX電源も使えそう。
UART
UART0は、デバッグ出力か何かに使われている。
- UART1が、内部Linuxの/dev/ttyS1へ割り当てられている
- UART2が、内部Linuxの/dev/ttyS2に割り当てられている
ttys1,s2は、WEB UIから
OLED
OLEDの動作は未確認。OLEDまでつなげるならFull版買えばいいのでは....。
ISOアップロード
ISOは、WinSCPでSSH SCP転送するのがよい。適当なPCにUSBケーブルをつなぐと、マスストレージとして認識するが、動作が安定しなかったため。イーサネット経由の転送であれば安定する。WinWCPでroot / rootでログインし、/dataへISOを転送する。2MB/secくらいしか出ないので気長に待つのが良い。
所管
Lite版でも十分楽しめそう。