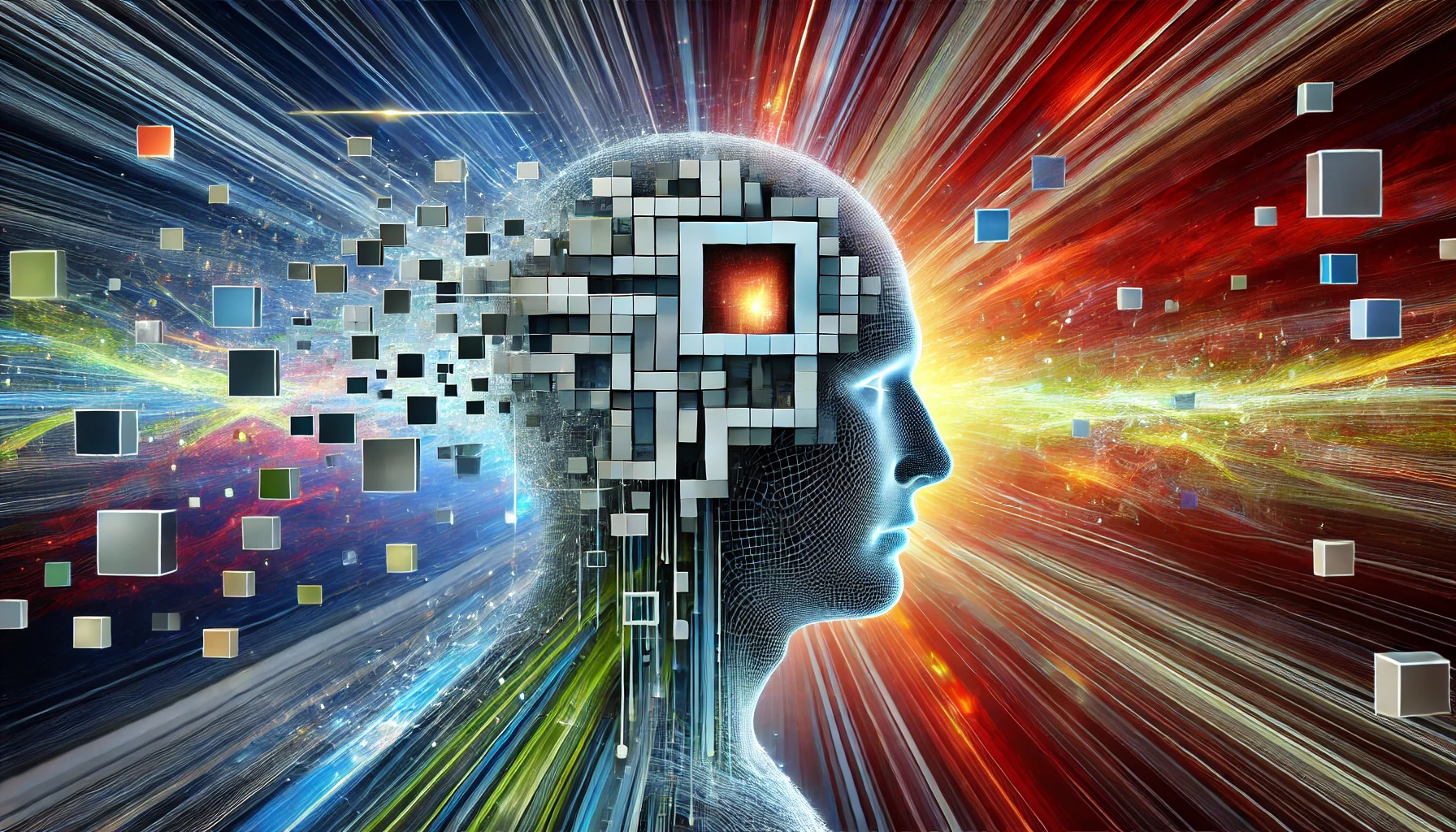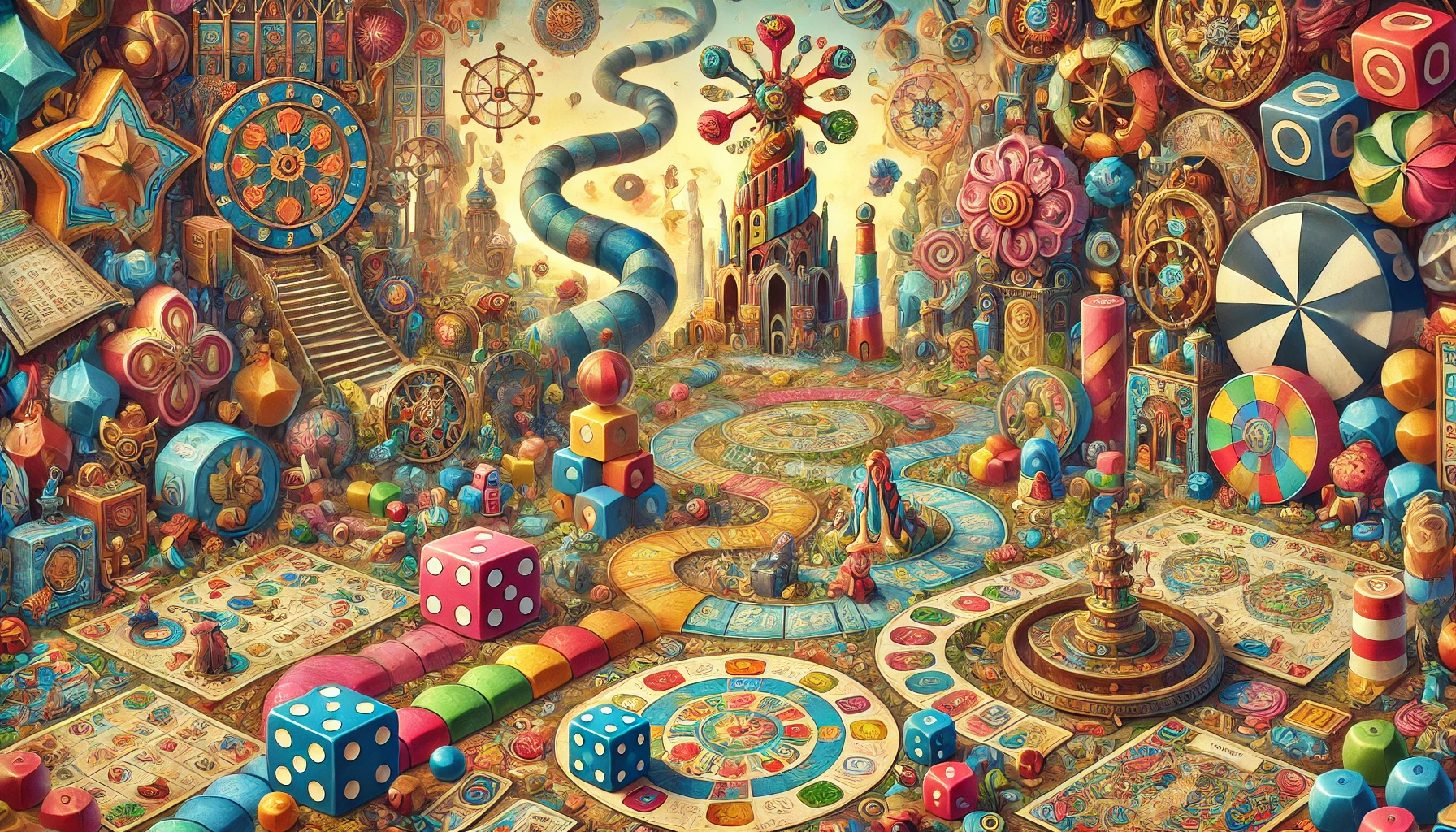皆さんは相手に何かを伝える際に、どのようなロジックで説明をしますか?
私はプロジェクトで主にPMを担当しているのですが、仕事柄お客様や社内のメンバーに説明する機会が多く、ありがたい事に説明が分かりやすいとの声をいただく事もあります。
この記事では、物事を説明をする上で私が意識している事をお伝えできればと思います。
元々私もエンジニアだったという経緯もありますので、皆さんのお役に立つヒントもあるかもしれません。
そもそも「説明する」とは
物事を「説明する」という事は、自分の頭の中にある情報を相手の頭の中にコピーするという行為ですので、私はいかにして必要な情報の漏れがなく、そして効率よくコピーを行えるかという事を意識しています。
コピーに際して出来るだけ齟齬が生じず、相手が説明を咀嚼するための負荷を減らし、安心して情報を受け取ってもらうためには、説明の順序や伝え方の選定が重要となってきます。
説明の順序
まず説明の順序としては、情報の大枠から詳細へと説明を進めます。
大枠の説明から進めると、相手は「こういう事を言おうと思ってるのね」と受入れの準備が始まります。頭の中に情報を受け入れるための箱を作ってくれるイメージです。
その後に中程度の情報、またその後に詳細な情報と、徐々に粒度の細かい情報を伝えます。
そうする事で先ほど用意してもらった大枠の箱の中に、パーツを埋め込むかのようにスムーズに情報を構成してもらう事が出来ます。
例をひとつあげましょう。例えば「美味しいラーメン屋さんを後輩にオススメしたい」とします。
まず「美味しいラーメン屋があってね。オススメしたいんだよ」と話の目的を伝えます。相手の頭の中には「美味しいラーメン屋を教えてもらう」という受け入れの箱が出来ます。
決して「俺って辛いもの好きじゃん?」から始めてはいけません。どのような箱を用意していいかも分からないですし、用意されたとして「先輩の好みについて」という箱が限界です。
その上で「千葉県の勝浦市というところにあるお店なんだけど、」と続けると、大枠の箱の中に「千葉県の勝浦市にあるラーメン屋」という中くらいの箱が出来ます。もしかすると脳内では勝浦市にまで行ってくれるかもしれません。
これで相手は「千葉県の勝浦市」以外の地域の事を考える負荷と、誤解の可能性が無くなりました。
続けて「勝浦市には勝浦タンタンメンというご当地ラーメンがあるんだけど、◯◯という店の勝浦タンタンメンが最高なんだよ。漁港の近くにあってね。ガッツリ辛くて俺の好みにピッタリなんだ」などと詳細な説明を行い、先ほどの箱の中に情報を整理しながら入れてもらいます。
もしかすると後輩は辛いものが苦手かもしれないので、詳細でその旨は教えてあげた方が親切ですね。
このようにするとこちらと受け手側との情報構成の統一が出来て、情報のコピーがスムーズに進みます。
そのため、大枠で伝えていた話題から話が大きく変わる際には「話は変わって」や「一方で」などと別の話題に移るという事を明示的に伝え、また別に新たな箱を確保してもらいましょう。
これを怠ると相手が予め準備してくれていた箱に当てはまらず、話を見失られる危険性が高まります。
相手のリテラシーに合わせる
説明の内容や粒度は、相手のリテラシーに応じて調整しましょう。
ここで言うリテラシーとは、話題となっている分野に対するリテラシー(ITリテラシーなど)についてもそうですし、これまでの情報の共有度も含みます。該当のプロジェクトにしばらく関わっている方と今日から参画する方とでは、必要となる説明の開始位置も粒度も異なってきます。
相手のいる場所(情報をどの程度まで理解しているかの立ち位置)を想定して、説明内容が正しく伝わり切るというゴールまで一歩ずつ上がれるように階段を用意するイメージです。一歩ずつ階段を登って先ほどの箱に入れるパーツを拾っていってもらうのです。
リテラシーの高い方は行間を自身で補完できるので要所に踏み台があれば大丈夫ですが、リテラシーが低めの方は細かい段差がないとすぐに転げ落ちてしまいます。
相手の状況に合わせる
相手やプロジェクト自体の状況、どのような情報を求めているのかなども考慮が必要です。
相手の説明を聞こうとする目的が「状況を把握したいのか」「疑問を解決したいのか」「別の人を説得する必要があるのか」などによっても、必要な説明の内容が異なってきます。
プライベートの会話と異なり、限られた時間のビジネスシーンではただ話を流し聞きしたいという方は稀です。
あなたが「説明をする」目的があるのと同様に、相手にも「説明を聞く」目的があるのです。
例えば相手が「別の人を説得する必要がある」場合には、その方に説得材料となるべき理由や数値・裏付けなどを多めに伝えます。次の自分のアクションに繋がる情報を求めているからです。
「このような内容で説得いただくと良いですよ」と直接的に伝えても良いかと思います。
また必要な情報を記載した資料なども用意してあげられるとよりベターです。伝言ゲームによる情報欠落の可能性を防止できます。
重要なものは何か
私はボードゲームが好きで、ゲームマスター(ゲームのルール説明や進行をする人)を担当する事もあります。
その際にはゲームや参加メンバーによっても説明する順序や優先度を変えます。
基本的には説明書に沿ってルールの説明をするのですが、なるべくゲームを楽しんでもらえたらと思うので、導入として世界観を重点的に説明したりするケースもあります。
ボードゲームはシンプルに捉えると「数字の書かれたカードを出す」「コマを進める」などが主になるのですが、それがゲームの世界の何を表す行為なのかを知ることによって、ゲームの満足感が全く変わってきます。
満足感を尺度に考えた際には、ルール以上に世界観の共有が重要だったりもするのです。
おわりに
頑張って説明をした際に、受け手の方から「説明が分かりやすかった」など言ってもらえるとやはり嬉しいものです。
もし参考になる方法があればぜひ利用していただき、皆さまもぜひ楽しい説明ライフをお送りください。