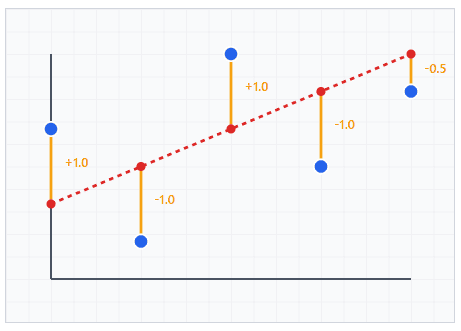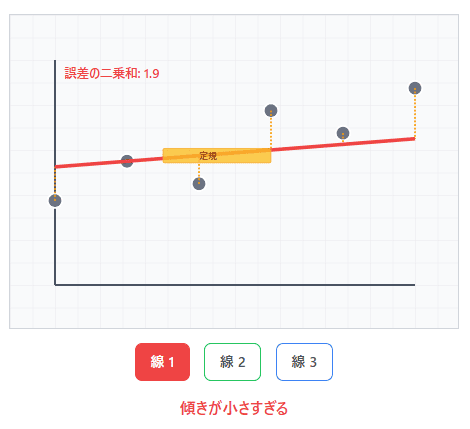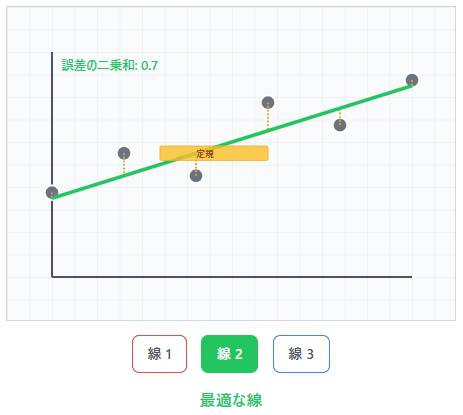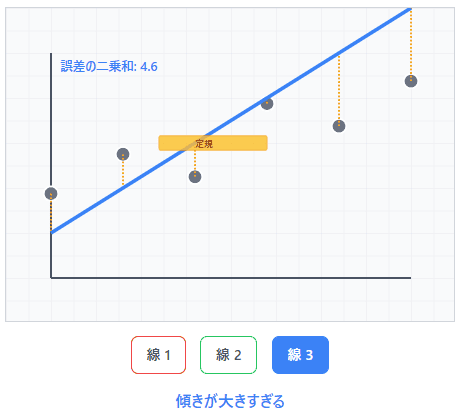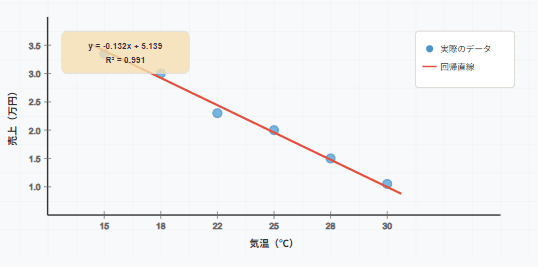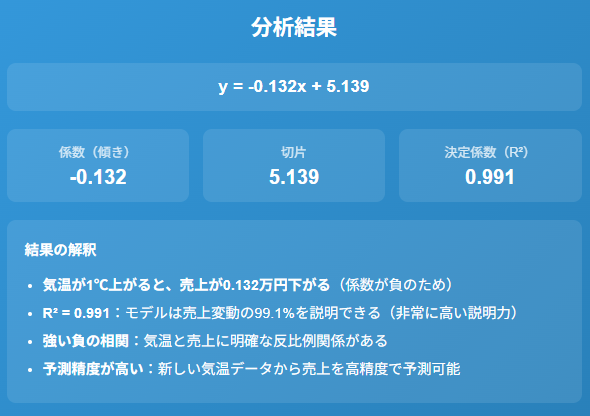はじめに
「近似曲線」「最小二乗法」「回帰分析」...統計学やデータサイエンスでよく聞く言葉ですが、実際のところ何をしているか理解できていますか?
今回は、数学が苦手な方でも理解できるよう、身近な例を使って分かりやすくまとめてみました。難しい数式は最小限に抑え、「なぜそうなるのか」の理解を重視しています。
記事内には、同じことばの定義が何度か登場したり、似たようなデータの説明を繰り返したりしています。その状況で理解できるようにしたためです。
近似曲線とは「データの中にある物語を見つけること」
身近な例 → カフェの売上分析
あなたがカフェを経営しているとします。毎日の気温と売上をグラフにしたところ、こんな感じになりました。
点をプロットすると、バラバラに見えますが、よく見ると「気温が高くなるほど売上が下がる」という傾向が見えてきます。これが データの中にある物語 です。
近似曲線は、この物語を「線」で表現したものなのです。
最小二乗法 - 「一番いい線」を見つける方法
なぜ「二乗」なのか?
データの点と引いた線との距離を「誤差」と呼びます。最小二乗法は、この誤差を最小にする線を見つける方法です。
なぜ「二乗」するのでしょうか?
-
プラスとマイナスが相殺されないため
- 単純に足し算すると、+2と-2が相殺されてしまいます
- 二乗すると、+4と+4になり、誤差の大きさが正しく評価できます
-
大きな誤差をより重視するため
- 誤差2は二乗すると4
- 誤差4は二乗すると16
- 大きな誤差の方が、より強くペナルティを受けます
直感的な理解
想像してみてください。あなたが定規を持って、散らばった点の上に線を引こうとしています。どの角度で引けば、すべての点から「平均的に一番近い」線になるでしょうか?
最小二乗法は、この「一番近い」を数学的に定義し、自動的に見つけてくれる方法なのです。
回帰分析 - 関係性を数値で表現する
回帰分析とは
回帰分析は、「X が Y に与える影響を定量的に測る」手法です。
先ほどのカフェの例で言うと・・
- X(説明変数): 気温
- Y(目的変数): 売上
- 関係: 気温が1℃上がると、売上が約0.1万円下がる
回帰分析で分かること
傾き(回帰係数): 関係の強さ
「気温が1℃上がると売上が0.1万円下がる」
切片: 基準値
「気温が0℃のとき、売上は4万円」
決定係数(R²): 説明力
「気温の変化で売上変動の85%を説明できる」
実際の解釈例
# 実際に計算した回帰分析の結果
係数: -0.132 # 気温が1℃上がると売上が0.132万円下がる
切片: 5.139 # 気温0℃のとき売上5.139万円(※外挿のため参考値)
R²: 0.991 # 99.1%の変動を説明可能
この結果から言えること
- 「猛暑日は売上が落ちる」という仮説が数値で証明された
- 気温予報を見れば、高い精度で売上を予測できる
- ただし、解釈可能範囲は測定データの範囲(15-30℃)に限定される
- 気温0℃での売上は外挿値のため、実際の予測には使用しない
注意: サンプル数が6点と少ないため、R²が過大評価されている可能性があります。現場では最低 30〜50 点を推奨。
【種類別】 どの線を選ぶか
1. 直線(線形回帰)
こんなときに使う!
- 関係が単純で分かりやすい
- 「○○が増えると△△も増える」という関係
例: 広告費と売上、勉強時間と成績
2. 非線形回帰
変数間の関係が直線では表現できない場合に使用します。
対数・指数回帰
こんなときに使う!
- 急激な成長や減衰を示すデータ
- 「最初は急激、後で緩やか」な関係
例: 人口増加、学習効果、放射性崩壊
多項式回帰
こんなときに使う!
- 上に凸、下に凸の関係がある
- 「最適な値がある」という関係
- 注意:次数を上げるほど柔軟だが過学習リスクが増加
例: 価格と売上(高すぎても安すぎても売れない)
【実践】Pythonで簡単実装
基本的な線形回帰
線形回帰を実装する前に、まずデータの準備から始めましょう。今回はカフェの例で使用した気温と売上のデータを使います。
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
# データの準備
# 説明変数(X): 気温データ - reshape(-1, 1)で縦ベクトルに変換
# scikit-learnは2次元配列を期待するため、1次元データを2次元に変換が必要
temperature = np.array([15, 18, 22, 25, 28, 30]).reshape(-1, 1)
# 目的変数(Y): 売上データ - 1次元配列のままでOK
sales = np.array([3.2, 2.8, 2.1, 1.8, 1.5, 1.2])
print("データの確認:")
print(f"気温データの形状: {temperature.shape}") # (6, 1)
print(f"売上データの形状: {sales.shape}") # (6,)
print(f"データ点数: {len(temperature)}個")
なぜreshape(-1, 1)が必要?
- scikit-learnの仕様:説明変数は2次元配列(行×列)で渡す必要がある
-
-1は「自動計算」の意味で、この場合6行1列になる - 複数の説明変数がある場合は自然に2次元になるが、1変数の場合は明示的に変換が必要
次に、実際に回帰分析を実行します。
# 回帰分析の実行
# 1. モデルの作成
model = LinearRegression()
# 2. モデルの学習(データからパラメータを推定)
model.fit(temperature, sales)
print("学習完了!モデルが気温と売上の関係を学習しました")
fit()で何が起きている?
- 最小二乗法により、データに最もよく合う直線の傾きと切片を計算
- scikit-learnのLinearRegressionは正規方程式(通常解)で最小二乗解を直接計算
- 学習後、model.coef_(係数)とmodel.intercept_(切片)にパラメータが保存される
学習結果を確認してみましょう。
# 結果の解釈
print("\n=== 回帰分析の結果 ===")
print(f"係数(傾き): {model.coef_[0]:.3f}") # 傾き
print(f"切片: {model.intercept_:.3f}") # 切片
print(f"決定係数(R²): {model.score(temperature, sales):.3f}") # R²
print("\n=== 結果の意味 ===")
print(f"• 気温が1℃上がると、売上が{abs(model.coef_[0]):.3f}万円下がる(係数が負のため)")
print(f"• 気温0℃のときの理論上の売上は{model.intercept_:.3f}万円")
print(f"• モデルは売上変動の{model.score(temperature, sales)*100:.1f}%を説明できる")
- 各指標の解釈 -
- 係数(傾き): Xが1単位変化したときのYの変化量
- 切片: X=0のときのYの値(ただし外挿値なので解釈に注意)
- 決定係数(R²): -∞~1の値で、1に近いほどモデルの説明力が高い(悪いモデルでは0未満になることもある)
最後に、学習したモデルを使って予測を行います。
# 予測(データ範囲内での予測推奨)
new_temp = 27 # 測定範囲内(15-30℃)での予測
# predict()メソッドは2次元配列を期待するため[[]]で囲む
predicted_sales = model.predict([[new_temp]])
print(f"\n=== 予測結果 ===")
print(f"気温{new_temp}℃のとき、予想売上: {predicted_sales[0]:.2f}万円")
# 予測の信頼性チェック
data_range = f"{temperature.min()}℃ ~ {temperature.max()}℃"
print(f"※この予測はデータ範囲内({data_range})なので信頼性が高いです")
# 複数の気温での予測例
test_temps = [[20], [24], [29]]
predictions = model.predict(test_temps)
print(f"\n=== 複数予測の例 ===")
for temp, pred in zip([20, 24, 29], predictions):
print(f"気温{temp}℃ → 予想売上{pred:.2f}万円")
予測時の注意点
- データの範囲外(外挿)での予測は精度が大きく下がる可能性がある
- この例では15-30℃の範囲内での予測を推奨
- 実務では新しいデータでの検証も重要
可視化
データと回帰結果を視覚的に確認することで、モデルの妥当性を判断できます。
# グラフ描画の設定
plt.figure(figsize=(10, 6)) # 図のサイズを指定(幅10インチ、高さ6インチ)
# 実際のデータポイントを散布図で表示
plt.scatter(temperature, sales,
color='blue', # 点の色
label='実際のデータ', # 凡例用のラベル
s=100, # 点のサイズ
alpha=0.7) # 透明度
# 回帰直線を描画(滑らかな線を描くため連続値で描画)
x_smooth = np.linspace(temperature.min(), temperature.max(), 100).reshape(-1, 1)
y_smooth = model.predict(x_smooth)
plt.plot(x_smooth, y_smooth,
color='red', # 線の色
label='回帰直線', # 凡例用のラベル
linewidth=2) # 線の太さ
# グラフの詳細設定
plt.xlabel('気温(℃)', fontsize=12)
plt.ylabel('売上(万円)', fontsize=12)
plt.title('カフェの売上と気温の関係', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.legend(fontsize=11) # 凡例を表示
plt.grid(True, alpha=0.3) # 薄いグリッドを表示
plt.tight_layout() # レイアウトを自動調整
# 追加情報をテキストで表示
textstr = f'y = {model.coef_[0]:.3f}x + {model.intercept_:.3f}\nR² = {model.score(temperature, sales):.3f}'
plt.text(0.05, 0.95, textstr,
transform=plt.gca().transAxes, # 座標系を図の相対位置に設定
fontsize=10,
verticalalignment='top',
bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='wheat', alpha=0.5))
plt.show()
実際にこのコードを実行したら・・
-可視化のポイント-
- 散布図 : 実際のデータの分布を確認
- 回帰直線 : モデルが学習した関係を可視化
- R²の確認 : 直線がデータにどの程度合っているかを数値で確認
- 外れ値の発見 : グラフで異常な点がないかチェック
この可視化により、以下のことが分かります。
- データが概ね直線関係にあるか
- 外れ値(大きく外れた点)があるか
- 等分散性(誤差が一定か)が保たれているか
- モデルが適切にフィットしているか
-良いモデルの特徴-
- データ点が回帰直線の周りに均等に分布
- 特定の範囲で誤差が大きくなっていない
- R²が高い(ただし適切なしきい値は分野や目的に依存:物理実験では0.95以上、社会科学では0.3でも有用な場合がある)
注意! 統計的検定について
- scikit-learnは係数の統計的有意性(p値など)を提供しません
- より詳細な統計分析が必要な場合は
statsmodelsライブラリを使用することを推奨します - データの範囲外(外挿)での予測は精度が大きく下がる可能性がある
- この例では15-30℃の範囲内での予測を推奨
- 実務では新しいデータでの検証も重要
【注意点】データとの向き合い方
1. 相関関係と因果関係の違い
<相関関係>
一緒に変動する
<因果関係>
片方が原因で片方が結果
例:「アイスクリームの売上と熱中症患者数は相関がある」
- 相関関係 : ✓ どちらも気温と関係がある
- 因果関係 : ✗ アイスが熱中症の原因ではない
2. 外れ値の影響
1つの極端な値が、線全体を大きく歪める可能性があります。
<検出方法>
- Z-score法: 平均から標準偏差の3倍以上離れた値
- IQR法: 四分位範囲の1.5倍を超える値
- 散布図での視覚的確認
<対策>
- データを可視化して確認
- 外れ値の原因を調査
- 必要に応じて除外や調整
- ロバスト回帰(RANSAC等)の使用を検討
3. 過学習に注意!!
複雑な曲線ほど、訓練データにはよく合いますが、新しいデータでは予測が外れやすくなります。
<バランスが重要>
- シンプルすぎる:重要な関係を見逃す
- 複雑すぎる:ノイズまで学習してしまう
<対策>
- 交差検証による汎化性能の確認
- 正則化(Ridge, Lasso回帰)の適用
- AIC/BICによるモデル比較
【評価指標】「良い線」かどうかの判断
1. 決定係数(R²)
意味 : データの変動をどの程度説明できるか
範囲 : −∞〜1(0 未満は“平均だけで予測”より悪い状況)
注意 : 多変量回帰や非線形回帰では解釈が変わる場合があります
from sklearn.metrics import r2_score
r2 = r2_score(sales, model.predict(temperature))
print(f"決定係数: {r2:.3f}")
※単純比較なら R²、複数モデルなら adjusted R² / AIC / BIC で総合判断
2. モデル比較指標
AIC(赤池情報量規準)
- モデルの複雑さを考慮した評価指標
- 小さいほど良いモデル
調整済み決定係数(Adjusted R²)
- 変数の数を考慮したR²
- 多変量回帰でのモデル比較に有効
2. 平均二乗誤差(MSE)
意味 : 予測値と実際の値の差の大きさ
特徴 : 小さいほど良い
from sklearn.metrics import mean_squared_error
mse = mean_squared_error(sales, model.predict(temperature))
print(f"平均二乗誤差: {mse:.3f}")
3. 平均絶対誤差(MAE)
意味 : 予測値と実際の値の差の絶対値の平均
特徴 : 解釈しやすい
from sklearn.metrics import mean_absolute_error
mae = mean_absolute_error(sales, model.predict(temperature))
print(f"平均絶対誤差: {mae:.3f}")
4. 交差検証による汎化性能の確認
意味: モデルが新しいデータに対してどの程度予測できるかを評価
特徴: 過学習を防ぎ、モデルの汎化性能を客観的に測定
from sklearn.model_selection import cross_val_score
# 5分割交差検証
cv_scores = cross_val_score(model, temperature, sales, cv=5, scoring='r2')
print(f"交差検証スコア: {cv_scores.mean():.3f} (+/- {cv_scores.std() * 2:.3f})")
実用的な活用例
ビジネス場面
<売上予測>
- 過去の売上データから将来を予測
- 季節性、トレンドを考慮
<価格設定>
- 価格と売上の関係を分析
- 利益を最大化する価格を決定
<在庫管理>
- 需要予測による適切な在庫量の決定
個人的な活用
<健康管理>
- 運動量と体重の関係を分析
- 睡眠時間と体調の関係を把握
<投資判断>
- 経済指標と株価の関係を分析
- リスクとリターンの関係を理解
<学習効率>
- 勉強時間と成績の関係を分析
- 効率的な学習方法を見つける
まとめ
近似曲線・最小二乗法・回帰分析は、一見複雑に見えますが、本質は「データの中にある関係性を見つけて、将来を予測する」ことです。思った以上に身近でシンプルで面白いと思いませんか?
重要なポイント
- 前提条件の確認 - 線形性・独立性・等分散性・正規性
- データの可視化から始める - まずグラフで関係を確認
- 適切なモデルを選ぶ - 直線か曲線か、複雑さのバランス
- 汎化性能を検証 - 交差検証で過学習を防ぐ
- 結果を解釈する - 数値の意味を理解し、実務に活用
- 限界を理解する - データの範囲内での予測、相関≠因果
非エンジニアであっても、現代のツールを使えば、計算は自動でできます。重要なのは、結果を正しく解釈し、意思決定に活用する ことです。
身の回りのデータを使って、ぜひ実践してみてください。きっと新しい発見があるはずです!
この記事は、統計学の基礎知識がない方でも理解できるよう、実用性を重視して書きました。より高度な理論については、専門書籍や論文を参照してください。