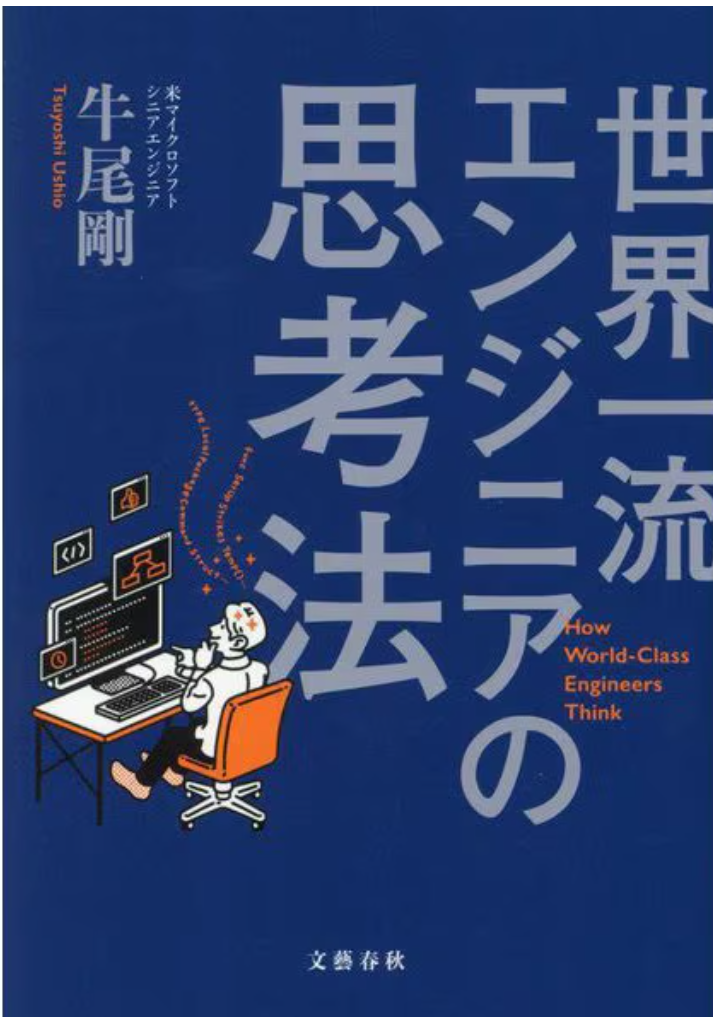以前、同僚から『世界一流エンジニアの思考法』という本を勧められました。購入後、長い間本棚に眠らせてしまっていたのですが、最近ようやく読み始めました。最初にページをめくると、「試行錯誤は『悪』?」、「生産性って一体何?」といった衝撃的な言葉が飛び込んできて、驚きました。思わず「どうしてもっと早く読まなかったんだろう?」と自分を反省しています。
今回は、この本を読んだ感想をまとめてみたいと思います。
「はじめに」部分の紹介
著者の牛尾剛さんは、アメリカのマイクロソフト社でAzure Functionsチームのソフトウェアエンジニアとして活躍されています。彼自身、かつて「ガチの三流エンジニア」を自称していましたが、子どもの頃からパソコンが大好きで、シャープのポケコンやMZ-2500をいじりながら、ゲームのコードを写して遊ぶなど、エンジニアリングへの情熱を育んできた人物です。
日本での最初の職場では、技術職を希望していたものの、5年間は営業職に従事していました。しかし、40代でマイクロソフトに転職し、そこで出会ったのは、圧倒的に優れたエンジニアたちでした。彼らは一体どのような思考法(マインドセット)を持っているのか?なぜ彼らは楽しみながらも、次々と圧倒的な成果を上げることができるのか?
第1章世界一流のエンジニアは何が違うのだろう?
・試行錯誤は『悪』である
試行錯誤は、思いつきでさまざまなパターンを試しながら正解を探す方法です。しかし、このアプローチは時間がかかり、新しい知識を得にくい場合があるそうです。試行錯誤そのものの否定ではありませんでしたが、効率的に問題を解決するためには、まず仮説を立てから検証することの大事さがわかりました。
・頭が良くても「理解」には時間がかかる
表面的な理解にとどまらず、物事の背後にある仕組みや構造をしっかりと理解することが重要だということです。例えば、コードを読む際には、その意図やアーキテクチャの理解に時間をかけるべきです。このアプローチは特に基礎的な部分の練習において大切です。
第2章 アメリカで見つけたマインドセット
・「Be Lazy」(怠惰であれ)というマインドセット
「Be Lazy」というマインドセットは、より少ない時間で価値を最大化するという考え方です。この章を読んで私が今後の仕事で意識したいことは、無駄な作業や時間を省き、重要なことに集中することで、労力を最小限に抑えながら成果を最大化していくことになります。
・優先順位の高いものに集中する
海外のメンバーの多くは、最初に1つのタスクを選んで集中し、終わったら次に進むという方法を取ります。これにより、重要なタスクを効率よく完了させることができます。
**2-8法則(パレートの法則)**を活用し、20%の仕事で80%の成果を出すことが効率的なので、限られた時間で最大のインパクトを生む仕事に注力していきたいと思いました。
・「準備」、「持ち帰り」をやめてその場で解決する
日本の会議では、事前の資料準備や会後の議事録整理、さらには宿題の検討など、会議以外にも多くの作業が発生します。しかし、牛尾さんの紹介によると、海外のエンジニアたちは会議の場で完結させることに注力しています。
会議の中で決定を下し、「準備」や「持ち帰り」の作業を減らすことで、時間削減に繋げていきたいと本を読んで思いました。会議中に議論し、問題をその場で解決することで、後からの対応や再調整を避けることができるからです。
第3章 脳に余裕を生む情報整理・記憶術
この章で最も印象に残ったことは、「なぜ同僚たちは記憶力が良いのだろう?」という問いです。仕事ができる人は大抵、記憶力が良いと考えていますが、記憶力を高めるためにはどうすれば良いかわかりませんでした。
牛尾さんによると、記憶力を向上させるためのコツとして以下のような方法があります。
・自分がやったことを、他の人に分かりやすく説明できるように時間をかけて整理する
その手段の一つとして「ブログを書く」ことが有効だとされています。私もこの方法が有効的だと感じています。普段の仕事で学んだことや研修で得た技術など、インプットした情報をブログという形でアウトプットすることによって、記憶がより定着しやすくなったと経験したからです。
また、「後で人に説明する」と意識するだけでも、集中力や記憶力の向上に大きな効果があると思います。このように、アウトプットを意識的に行うことで、記憶力を高めることができるのです。
第4章 コミュニケーションの極意
本章を読んだ後、最も印象に残った点は「コミュニケーションの効率化」についてです。
他人に質問する際、背景や結果まで詳しく説明することがよくありますが、あまりにも情報量が多すぎると、相手は全てを把握することが難しくなります。どんなに情報が豊富でも、相手にとっては消化不良になる可能性があるため、最初から全てを説明するのではなく、必要な情報を絞り込むことが重要だと感じました。
情報量を最小限に抑えることで、相手が理解しやすく、効率的にコミュニケーションを取ることができると考えます。その上で、簡単なことでもきちんと説明することが大切です。
第5章 生産性を高めるチームビルディング
本章では、牛尾さんが「サーバントリーダーシップ」の概念を紹介しました。
上司はKPIを示し、チームがどのように達成するかを主体的に考え、意識を決定します。社員一人一人がステークホルダーとなり、かなりの権限を持っています。これに対して、マネージャー職はメンバーが幸せに働ける環境を提供できるかどうかに非常に関心を持っています。私が以前外資系で働いていた際に、月に一度上司と1対1で面談を行い、仕事の満足度やキャリアアップについて常に相談に乗ってもらい、支援を受けました。すごく助かったので「サーバントリーダーシップ」が良いスタイルだと考えています。
第6章 仕事と人生の質を高める生活習慣術
・タイムボックス制から身体づくりまで
・生産性を上げるためには学習が重要です。だからこそ、私は仕事の合間に自分のやりたいトピックを勉強したり、試したりしています。
タイムボックス制を活用して学習時間を確保します。長時間の残業を続けることでパフォーマンスが低下し、深夜まで働くことが推奨される時代ではないと感じています。
毎日勉強の時間を確保することで、仕事面の効率にも良い影響を与えるでしょうと感じました。
第7章 AI時代をどう生き残るか?
2023年、ChatGPT-4のリリースにより、世界が衝撃を受けました。特にエンジニアである私は、どのような仕事ならAIにとってかわられないかを常に考えています。
正確な答えは誰にも分かりません。しかし、「専門性」を追求することが、私たちができる最も強い手段ではないでしょうか?
専門性を高める準備をしていけば、時代の変化の中で私たちの強力な武器となるでしょう。
また、最近AIツールを頻繁に利用していますが、簡単な文書をAIに投げるとすぐ回答が返ってきます。使っていくうちに気づいたことがあります。それは、AIツールを使えば使うほど、自分の思考量が減少していくことです。
独自思考能力が失ってしまったら自分の価値がなくなりますので、AIに頼りすぎるず、独自の思考を保ち続けることが大事だと思いました。
終わり
"There are a thousand hamlets in a thousand people's eyes"(千の人々の目に千のハムレットがある)
異なる人々がそれぞれの視点からこの本を解釈できます。何が正しいでしょうか?何が間違っているでしょうか?
その判断は誰が下すべきでしょうか?「ルールだから正しい」「トップ企業でみんながそうしているから正しい」とは限りません。
私が思うに、自分に一番相応しいものを選ぶことが最も大切です。隣の芝が青く見えやすいですが、結局自分自身に何が最適なのかをしっかりと考えるべきでしょう。現在の私にとっては、以下のポイントが大切だと感じています。
・自分の幸せは自分でコントロールできる
・生きている限り、勉強をし続ける
最後、Let's enjoy life to the fullest!