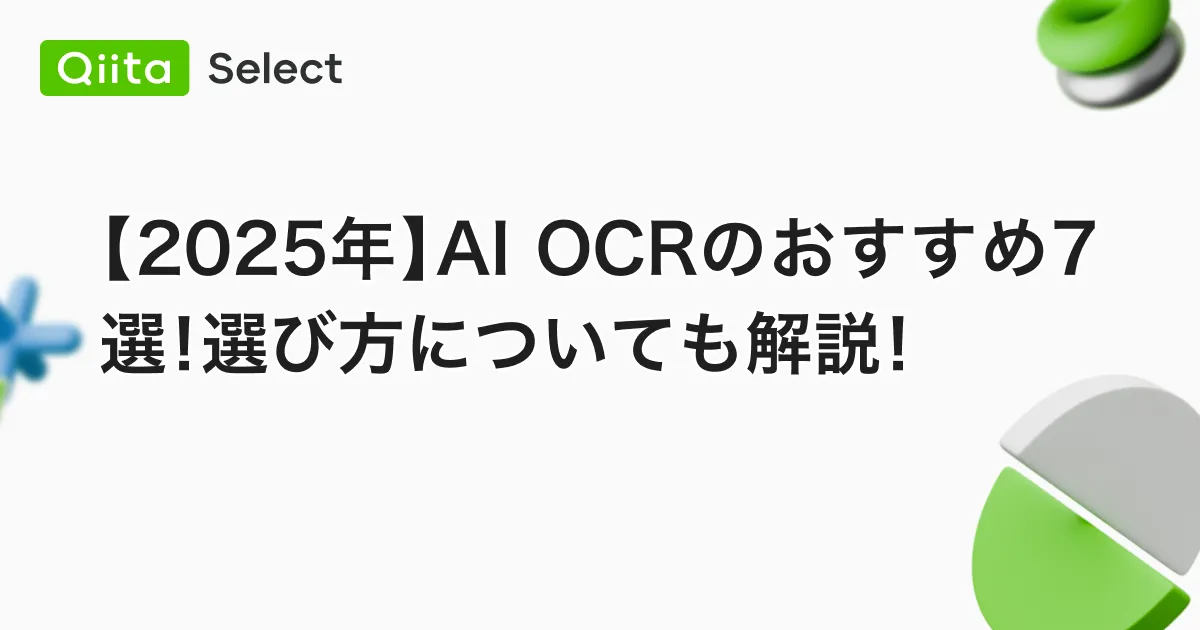近年、DX推進の加速に伴い、紙文書のデジタル化は多くの企業にとって急務となっています。独立行政法人 中小企業基盤整備機構による2023年の調査では、DXをすでに実施している、もしくは検討中と回答した企業の中でも「文書の電子化・ペーパレス化」が64.4%となっており、文書の電子化が進んでいることが分かります。(参照:独立行政法人 中小企業基盤整備機構)
しかし、従来のOCR(光学的文字認識)技術では、認識精度や処理速度に課題が残る場合が多く、導入・運用コストも決して低いとは言えません。そこで注目されているのが、深層学習技術を活用したAI OCR(人工知能を取り入れた光学的文字認識)です。AI OCRは深層学習技術を活用することで、従来のOCRでは困難だった手書き文字や複雑なレイアウトの文書でも高い認識精度を実現します。また、AIによる自動学習機能により、継続的な精度向上が可能となり、様々な文書に対応できる柔軟性も持ち合わせています。
本記事ではエンジニアの皆さまに向けて、AI OCRの技術的な深層から実用的な活用までを徹底解説します。アーキテクチャ、API、カスタマイズといった技術的側面はもちろん、具体的なユースケース、性能評価、導入・運用における注意点まで、エンジニアがAI OCRを理解し、活用するための情報を網羅的に提供します。
AI OCRとは?従来のOCRとの違い
AI OCRは、画像やPDFに含まれる文字情報を自動的に解析し、デジタルデータとして抽出する技術 です。従来のOCRでは、あらかじめ決められたフォーマットに依存するため、特定のレイアウトの書類しか正確に認識できませんでした。
一方、AI OCRでは機械学習やディープラーニングを活用し、異なるフォーマットの帳票や手書き文字の高精度認識が可能です。これにより、請求書や契約書などフォーマットが統一されていない文書でも自動で処理できるようになり、企業の業務効率化を大幅に向上させられます。
AI OCRの3つの特徴
1. 非定型データへの対応
従来のOCRは特定のレイアウトに依存していましたが、AI OCRは機械学習とディープラーニングにより、非定型文書にも対応可能です。多様な文書レイアウトを学習し、文脈や文字配置を理解することで、情報を柔軟に抽出します。そのため、請求書や契約書など、フォーマットが統一されていない文書のデジタル化を効率的に進められます。
2. 手書き文字の認識
AI OCRは高度な画像処理技術と文字認識モデルを活用し、手書き文字の認識精度を飛躍的に向上させました。様々な筆跡や文字形状を学習して文脈や文字のつながりを考慮するため、曖昧な文字や崩れた文字でも正確に認識できます。アンケート用紙や申込書など、手書き文書のデジタル化が容易になります。
3. API連携による業務効率化
AI OCRは、API連携を通じて既存の業務システムやRPAとシームレスに連携できます。データ入力作業の自動化やワークフローの効率化を実現し、請求書データを会計システムに自動入力したり、顧客情報をCRMシステムに自動登録したりすることが可能になります。
4. AIエージェントとの統合
AI OCRは単体での利用だけでなく、AIエージェントやChatGPTと組み合わせることで、より高度なデータ処理や意思決定支援を可能にします。
近年では、文書解析やデータ分析を伴う業務においてAI OCRの活用が進んでおり、コスト削減や業務の高速化が期待されています。特に、大量の文書を扱う金融、医療、行政、製造業などの分野では、AI OCRが不可欠なツールとなっています。
AI OCRの選び方:5つのチェックポイント
AI OCRを選ぶ際には、以下の5つの視点を考慮すると良いでしょう。
- 認識精度と対応フォーマット
- 手書き文字・非定型帳票の対応力
- API・システム連携のしやすさ
- 導入・運用コスト
- セキュリティ対策
1. 認識精度と対応フォーマット
認識精度は業務効率に直結するため、事前にデモ版で確認が必須です。特に、自社で扱う文書フォーマットへの対応力をチェックしましょう。精度が低いと修正作業が増え、業務効率を著しく低下させる可能性があります。多岐にわたる文書種別に対応可能か、事前に確認してください。
2. 手書き文字・非定型帳票の対応力
手書き文書や非定型帳票を扱う企業は必ず確認する必要があります。契約書やアンケートなど、手書き文書のデータ化をスムーズに行うためには、高い認識率が不可欠です。精度の確認は、実際の業務に近いサンプルでのテストが推奨されます。
3. API・システム連携のしやすさ
既存システムがある場合、API連携が容易かどうか、RPAツールとの連携が可能かどうかを確認しましょう。スムーズな連携はデータ入力の自動化を促進し、業務効率を大幅に向上させます。連携の柔軟性やサポート体制も重要な判断基準です。
4. 導入・運用コスト
コストはクラウド型とオンプレミス型で異なります。自社の予算や利用規模に合わせて、最適なコスト体系を選びましょう。無料トライアル期間を利用して、コストパフォーマンスを見極めることも選択肢として良いでしょう。
5. セキュリティ対策
特に機密文書を扱うAI OCRでは、セキュリティ対策が重要です。クラウドの暗号化やアクセス制御の有無を確認し、自社のセキュリティポリシーに合致するかをチェックしましょう。データ漏洩リスクを最小限に抑えるために、セキュリティ体制が強固なサービスを選定することが重要です。
AI OCRの比較
1. AnyForm OCR

出典:AnyForm OCR
AnyForm OCRは、法人向けソフトウェアの開発・販売などを手がける株式会社ハンモックが開発した、高精度なAI OCRソリューションです。高い文字認識精度と使いやすさを両立しています。
特徴
AnyForm OCRの最大の特徴は、99.97%という極めて高い文字認識精度です。特許技術「WOCR」を搭載しており、人手が必要となる確認作業を大幅に削減することが可能です。また、ユーザーフレンドリーな設計により、IT専門家でなくても容易に利用できる点も魅力となっています。自社開発のAI OCRエンジン「手書き(第3)エンジン」が標準搭載されており、インターネット環境なしで、手書きの日本語の文字を認識します。
さらに、自動計算機能による帳票自動振分を備えており、多様な業務形態に柔軟に対応できます。製造業や小売業など、異なる業種の文書フォーマットにも適応可能です。
AnyForm OCRの導入事例として、タキゲン製造株式会社の例が挙げられます。同社は、AnyForm OCRの導入により、年間5,000時間もの入力作業時間を削減することに成功しました。高精度な文字認識により、入力ミスも大幅に減少し、出荷トラブルの解消にもつながっています。
料金
詳細は公式サイトでご確認ください。
https://www.hammock.jp/anyform/
2. DEEP READ

出典:DEEP READ
概要
DEEP READは、EduLab株式会社が提供するAI OCRサービスです。特に手書き文字のデジタル化に優れた性能を持ち、独自の研究開発を基にした技術を活用しています。
特徴
DEEP READの主な特徴は、ディープラーニング技術を活用した高精度な文字認識です。作業時間は最大70%削減、読み取り制度は約98%、コスト削減率は約93%を誇ります。また、認識精度は99%以上を実現。特に手書き文字の認識に強みを持ち、金融業界、医療機関、教育機関など幅広い業界で利用されています。
DEEP READはクラウド型およびオンプレミス型の両方で提供されており、高いセキュリティと柔軟なサーバ構築をサポートしています。そのため、企業の規模やセキュリティ要件に応じた導入が可能です。また、英語や中国語(簡体字)など10種類以上の言語にも対応しているため、それらの言語を使用する企業にとっては良い選択肢となるでしょう。
料金
- クラウド:50,000円〜/月
- オンプレ:400,000円〜/月
無料トライアルあり。詳細は公式サイトでご確認ください。
https://aismiley.co.jp/product/edulab_deepread/
3. AI-OCRらくスルー
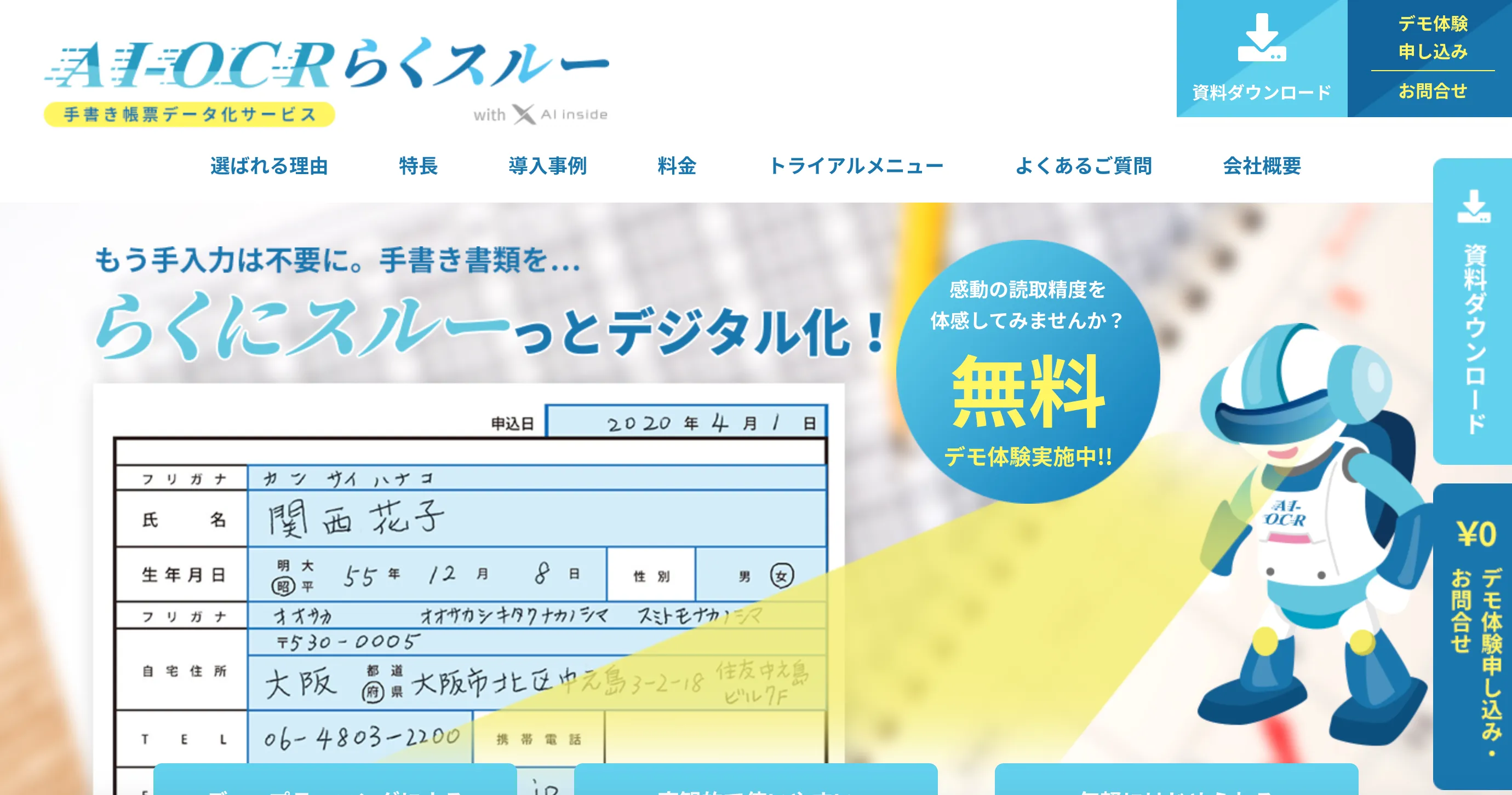
出典:AI-OCRらくスルー
概要
AI-OCRらくスルーは、関西ビジネスインフォメーション株式会社が提供するAI OCRソリューションです。AIに不慣れな方でも直感的に使いやすい利用画面を提供しています。初期費用無料で、最も低額なプランで月30,000円から利用できるため、コストパフォーマンスに優れたサービスと言えるでしょう。
特徴
AI-OCRらくスルーの最大の特徴は、その名前が示す通り、「らくに」導入・運用できる点です。専門的な知識がなくても、直感的な操作で高精度なOCR処理を行えます。手書き文字と活字の両方に対応しており、請求書、納品書、発注書など、様々な業務文書の処理に適しています。また、AI学習機能により、使用頻度が高まるほど認識精度が向上する仕組みを採用しています。
さらに、RPAツールとの連携も可能です。OCR処理後のデータを自動的に基幹システムに入力するなど、より広範囲な業務自動化を実現することができます。
料金
- LIGHT:30,000円/月
- STANDARD:99,800円/月
- PREMIUM:200,000円/月
初期費用は無料。
詳しくは公式サイトでご確認ください。
https://www.kbinfo.co.jp/aiocr/
4. SmartRead

出典:SmartRead
概要
SmartReadは、 最先端の人工知能の研究や、開発と関連ソリューションサービスを提供する、株式会社 Cogent Labsが提供するAI OCRサービスです。高度な画像処理技術とAI技術を組み合わせることで、高精度な文字認識を実現しています。
特徴
SmartReadの主な特徴は、その高い認識精度です。手書き・活字どちらでも対応可能です。また「都道府県」から「県」を選んで丸をつける場合には「県」と出力されたり、文字が読み取り範囲からはみ出してしまっていても、認識することが可能です。歪みや汚れがある文書でも、高精度な認識が可能です。
また、複数の異なるテンプレートがある場合、AIが自動で振り分けをしてくれます。最大500種類まで振り分けられるため、いくつかのテンプレートを使用して仕訳を行っている企業にとって、作業時間の短縮に役立ちます。
ドキュメント処理自動化ソリューションについて、詳細はこちらをご覧ください。
https://solution.toppan.co.jp/toppan-edge/service/smartread.html
料金
- スモールプラン:360,000円/年(月額30,000円相当)
- スタンダードプラン:960,000円/年(月額80,000円相当)
- エンタープライズプラン:2,400,000円/年(月額200,000円相当)
上記はクラウド版の場合。オンプレミス版は要問い合わせ。 詳細は公式ページでご確認ください。
https://www.smartread.jp/price
5. DynaEye 11

出典:DynaEye 11
概要
DynaEye 11は、株式会社PFUが提供する高性能OCRソフトウェアです。長年の開発実績を持つPFUが、最新のAI技術を取り入れて進化させた製品です。手書き文字も99.2%の認識率、導入実績累計7,900社以上、作業時間は79%削減という実績があります。
特徴
DynaEye 11は、特に、日本語特有の文字や表現に対する認識能力に優れており、癖が強かったり枠外にはみ出した記入であったりしても、高精度に認識します。そのため、日本企業の業務文書処理に適しています。
このソフトウェアは、手書き文字と活字の両方に対応しており、請求書、納品書、自由記入のアンケートなど、様々な種類の文書を処理することができます。DynaEye 11は、AIによる学習機能も備えており、使用頻度が高まるほど認識精度が向上します。「レイアウト学習」機能によって、自動検索された一を修正・保存します。
さらに、ユーザーによる辞書登録機能も用意されており、業界特有の用語や固有名詞にも柔軟に対応できます。セキュリティ面では、オンプレミス型での導入が可能であり、機密性の高い文書を扱う企業にも対応しています。
料金
- DynaEye 11 Entry Lite:504,000円/年(初年度)、84,000円/年(2年目以降)
- DynaEye 11 Entry AI-OCR:1,008,000円/年(初年度)、168,000円/年(2年目以降)
その他、繁忙期の処理枚数増加や業務の適用拡大があっても安心の、使い放題プランもあり。 詳細は公式ページでご確認ください。
https://www.pfu.ricoh.com/dynaeye/product/dynaeye11/entry/price.html
6. ProTech AI OCR

概要
ProTech AI OCRは、株式会社ショーケースが提供するAI OCRソリューションです。特に、eKYC(電子的本人確認)プロセスに特化した機能を持つのが特徴です。
特徴
ProTech AI OCRの主な特徴は、高度なAI技術を活用した精密な文字認識能力と、eKYCプロセスに特化した機能セットです。特に、身分証明書や公的書類の認識・検証に強みを持っています。
このサービスは、手書き文字と活字の両方に対応しており、さらに、画像の歪みや照明条件の変化にも強い認識能力を持っています。これにより、スマートフォンで撮影した画像からでも高精度な文字認識が可能です。また、自動での書類判定ができるため、書類の仕分け作業が不要になります。
また、このサービスはAPI形式で提供されており、既存のシステムやアプリケーションに容易に組み込むことができます。これにより、企業は自社のサービスにシームレスにeKYC機能を統合することが可能です。
料金
要お問い合わせ 公式サイトにてご確認ください
https://ekyc.showcase-tv.com/ai-ocr/
7. DX Suite

出典:DX Suite
概要
DX Suiteは、AI inside株式会社が提供するAI OCR市場で大きなシェアを誇るサービスです。活字だけでなく手書き文字も高精度に読み取り、紙帳票をデータ化することで、企業や自治体の業務効率化と生産性向上に貢献しています。
特徴
あらゆる帳票を高精度に読み取り、定型・非定型のフォーマットを問わずテキストデータを自動抽出することができます。また、日本語、英語、中国語、タイ語、ベトナム語に対応しているため、グローバル展開を行う企業にも適しています。
帳票の自動仕分け機能(オプション)によって、複数種類の文書を一括アップロードしても自動で分類できます。また、簡単で分かりやすいUIで提供されているため、慣れていない人でも簡単に操作できます。RPA製品をはじめとした様々なシステムとのAPI連携も可能なため、さらなる業務効率化にも役立ちます。
料金
- DX Suite Lite:30,000円〜/月
- DX Suite Standard:100,000〜/月
- DX Suite Pro:200,000〜/月
初期費用はプランによって異なります。詳細は公式ページでご確認ください。
まとめ
AI OCRは、従来のOCR技術では認識が難しかった 非定型帳票や手書き文字 にも対応し、近年では AIエージェントや大規模言語モデル(LLM)との連携 によって、より高度なデータ処理が可能になっています。
AI OCRの選定においては、 認識精度、対応フォーマット、システム連携、コストと運用負担 の4つの要素が鍵となります。業界ごとに求められる機能は異なるため、導入前にデモ版を試したり、API連携の可否を確認することが重要です。
本記事では、おすすめのAI OCRツールとして AnyForm OCR、DEEP READ、AI OCRらくスルー、SmartRead、DynaEye 11、ProTech AI OCR、DX Suite の7つを紹介しました。それぞれのツールは 対応フォーマットや導入形態(クラウド型・オンプレミス型) に特徴があるため、自社の業務に適したツールを選ぶことがポイントとなります。
近年では、AI OCRの進化により、企業の データ入力の負担が軽減 され、RPAやAIエージェントとの連携による業務自動化 も加速しています。今後もOCR技術は発展し、より柔軟なワークフローへの適応が期待されています。
AI OCRの導入を検討している企業や個人は、本記事で紹介したポイントを参考にしながら、自社の業務に適したツールを選定し、業務の最適化に役立ててください。
よくある質問
Q. AI OCRと従来のOCRの違いは何ですか?
AI OCRは、従来のOCR(光学文字認識)技術と比較して、機械学習やディープラーニングを活用した高度な認識機能を備えている点が特徴 です。従来のOCRは、事前に定義されたフォーマットに依存し、決められた位置にある文字しか正しく認識できませんでした。一方、AI OCRは レイアウトが異なる書類や手書き文字も学習しながら適切に認識できる ため、請求書、契約書、伝票などの 非定型帳票 にも対応可能です。また、AI OCRは API連携 により他のシステムと統合しやすく、RPA(Robotic Process Automation)と組み合わせた業務自動化にも活用されています。
Q. AI OCRを導入するメリットは何ですか?
AI OCRを導入することで、紙の文書や画像データをテキスト化する作業を自動化 できます。これにより、手作業でのデータ入力を減らし、作業時間の短縮 や 入力ミスの軽減 が期待できます。また、AI OCRは APIを通じて業務システムと統合できるため、ワークフローの一部として組み込むことが可能 です。例えば、請求書処理システムにAI OCRを組み込むことで、スキャンした請求書から支払情報を自動抽出し、経理業務をスムーズに進めることができます。さらに、手書き文字や非定型帳票の認識にも対応するため、より幅広い文書のデータ化が可能です。