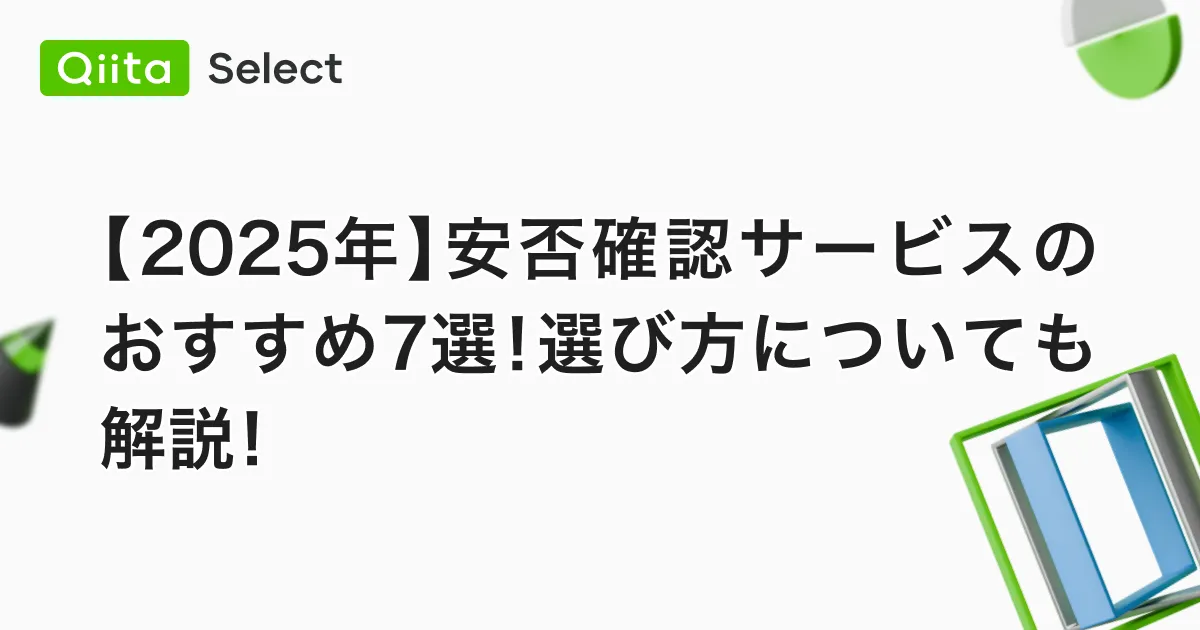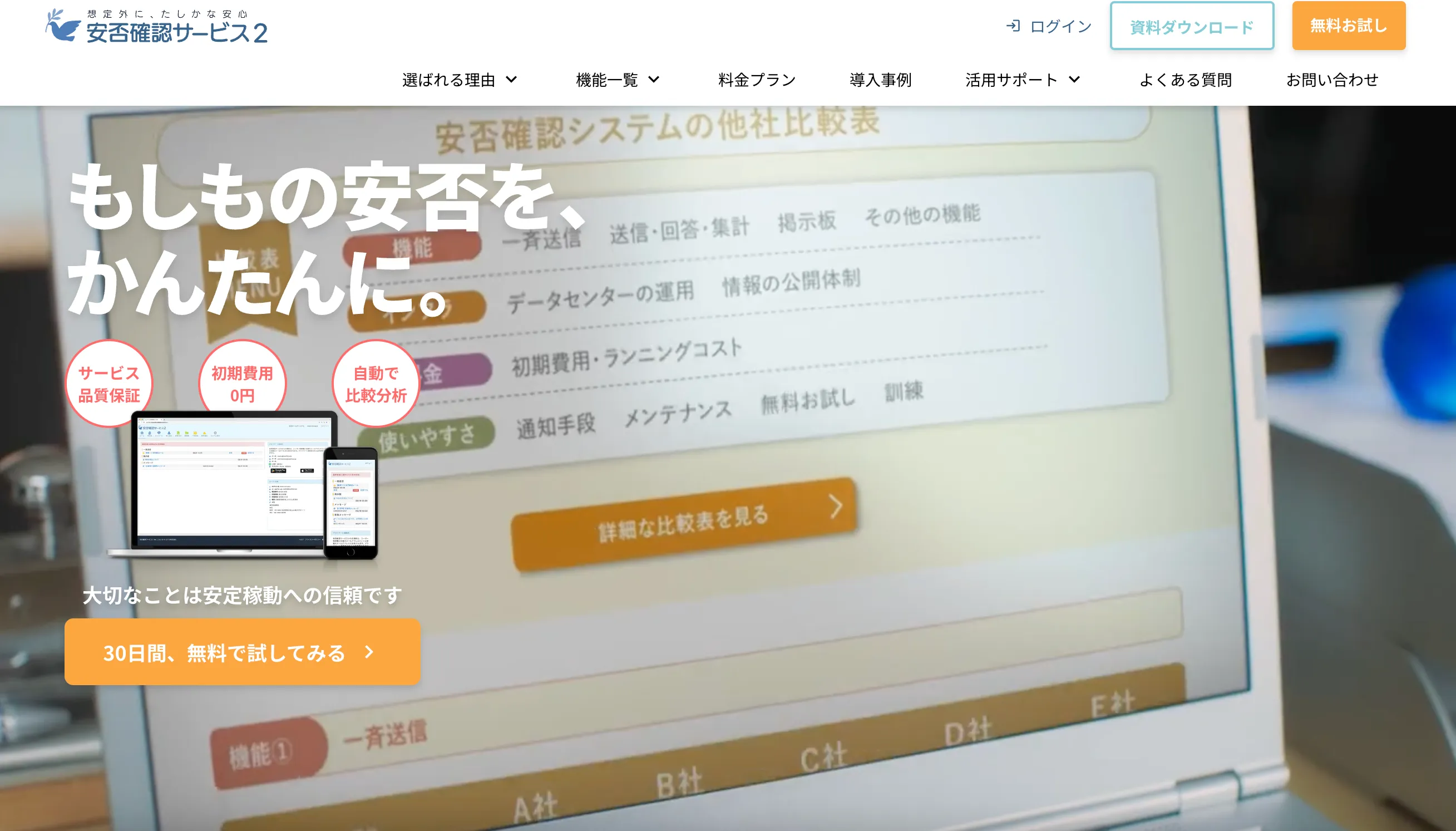安否確認サービスとは
自然災害や突発的な事故が増える現代社会において、安否確認サービスの重要性はますます高まっています。エンジニアやIT業界で働く人々にとっては、リモートワークやグローバルなチームとの連携が日常となっているケースも多いため、自身やチームメンバーの安全を迅速に把握できる状況を作っておくことは重要です。
安否確認サービスは、単なる緊急時の連絡手段にとどまらず、システム開発やプロジェクト管理におけるリスクマネジメントの一環としても活用されつつあります。本記事では、エンジニアが特に利便性を感じる安否確認サービス7つの機能や活用事例、選定のポイントについて詳しくお伝えします。
安否確認サービスの選び方:3つのポイント
1. 機能性
安否確認サービスを選ぶ際には、まずその機能性を確認することが重要です。例えば、リアルタイムでの位置情報の共有、緊急時の一斉通知機能、また、安否確認の履歴管理などが挙げられます。これにより、チーム全体が状況を把握しやすくなるため、迅速な対応が可能となります。また、APIを通じて自社のシステムやツールとの連携ができるサービスを選ぶと、業務フローの中に自然に組み込むことができ利便性が向上します。
2. ユーザビリティ
緊急時に利用することが想定されるため、使いやすさも求められます。インターフェースが直感的で、簡単に安否確認が行えることは、緊急時のストレスを大幅に軽減します。また、スマートフォンアプリが提供されていることも重要なポイントです。ユーザーからのフィードバックを反映した使いやすいデザインを持つサービスを選び、チーム全員が安心して利用できる環境を整えましょう。
3. コストとサポート体制
安否確認サービスには様々な価格帯がありますが、機能や規模に応じて適切なプランを選ぶことが肝要です。特にチームの規模や利用頻度を考慮し、コストパフォーマンスが優れているサービスを選びましょう。万が一のトラブルに備えて、サポート体制が充実しているかどうかも確認が必要です。迅速な対応を期待できるカスタマーサポートがあれば、エンジニアも安心してサービスを利用することができます。
安否確認サービスのおすすめ7選
1. トヨクモ 安否確認サービス2
概要
トヨクモの「安否確認サービス2」は、サービス導入社数4,000以上を誇るクラウド型の安否確認システムで、災害時や緊急時において従業員や関連スタッフの安全を迅速に確認できます。また、毎年、実際の災害を想定した訓練を行っており、安定して稼働すると証明されています。PC、タブレット、スマートフォンなど様々なデバイスに対応している点も魅力です。
料金
- ライト:¥6,800
- プレミア:¥8,800
- ファミリー:¥10,800
詳細は公式ページでご確認ください。
https://www.anpikakunin.com/price
2. 安否コール
 出典:安否コール
出典:安否コール
概要
安否コールは、災害時の迅速な安否確認を可能にするだけでなく、日常的な見守りにも活用できるサービスです。社員100人未満から数万人以上の大企業まで、様々な企業規模への導入実績があります。アンケート質問と回答を無制限に作成できる「アンケート機能」や、「自動安否確認通知」、部署や拠点など組織ごとの状況を一目で把握できる「自動集計機能」など、安否確認に関する様々な機能が搭載されています。
料金
- ビジネス:¥21,500
- ノーマル:¥18,000
- スタート:¥15,000
上記は中規模企業向けの場合。
その他、小規模企業向け、大規模企業向けのプランもあり。
詳細は公式ページでご確認ください。
https://www.anpi-system.net/kinou/#edition
3. エマージェンシーコール
 出典:エマージェンシーコール
出典:エマージェンシーコール
概要
エマージェンシーコールは、災害時のリスク管理を目的に開発されたサービスで、企業や団体だけでなく個人利用者にも対応しています。スマートフォンアプリやメール、LINEや電話音声など、様々な通信手段に対応しています。また、英語対応のため、グローバル企業や海外にメンバーがいるユーザーにも便利です。
料金
お問い合わせ
https://www.infocom-sb.jp/emc/light/
4. Biz安否確認
 出典:Biz安否確認
出典:Biz安否確認
概要
Biz安否確認は、契約数2,300社を突破した安否確認サービスです。指定した震度以上の地震が発生した際には自動で安否確認の連絡が送信されたり、通知への回答がない場合には自動で再送信される機能が備わっています。また通知に対する返信を自動で集計する機能もあるため、管理者の負担を減らすことができます。マルチデバイス対応やGPSの位置情報取得、グループ管理機能など、便利な機能が豊富に用意されています。
料金
詳細は公式ページでご確認ください。
https://www.ntt.com/business/services/application/risk_management/anpi.html
5. ANPiS
 出典:ANPiS
出典:ANPiS
概要
ANPiSは、全国100地点以上での採用実績があり、様々な業種で導入されています。災害リスクに対応するために設計された総合的な安否確認サービスで、個人利用から企業導入まで幅広いニーズをカバーします。月々6,600円からとお手頃な価格からスタートでき、充実した機能を備えていたり、操作が簡単だったりする点が特徴です。
料金
- 利用人数〜100名:¥9,900
- 利用人数〜200名:¥15,400
上記はスタンダードプランの場合。
利用人数やプランに応じて、いくつかの料金体系が用意されています。
詳細は公式ページでご確認ください。
6. セコム安否確認サービス
 出典:セコム安否確認サービス
出典:セコム安否確認サービス
概要
セコム安否確認サービスは、セキュリティ業界のリーディングカンパニーによる信頼性の高い安否確認サービスです。これまで契約社数9,000以上、利用者数は約835万人と、多くの方に利用されています。中小企業から大企業は「セコム安否確認サービス」、そして300人以下の中小規模の企業向けには「セコム安否確認サービス スマート」が用意されており、自社の規模に合わせて選べる点も特徴です。
料金
料金プランや同自アクセス人数などによって、いくつかのプランが用意されています。
詳細は公式ページでご確認ください。
https://www.secom.co.jp/business/saigai/anpi/anpi.html
7. anppii(アンピー)
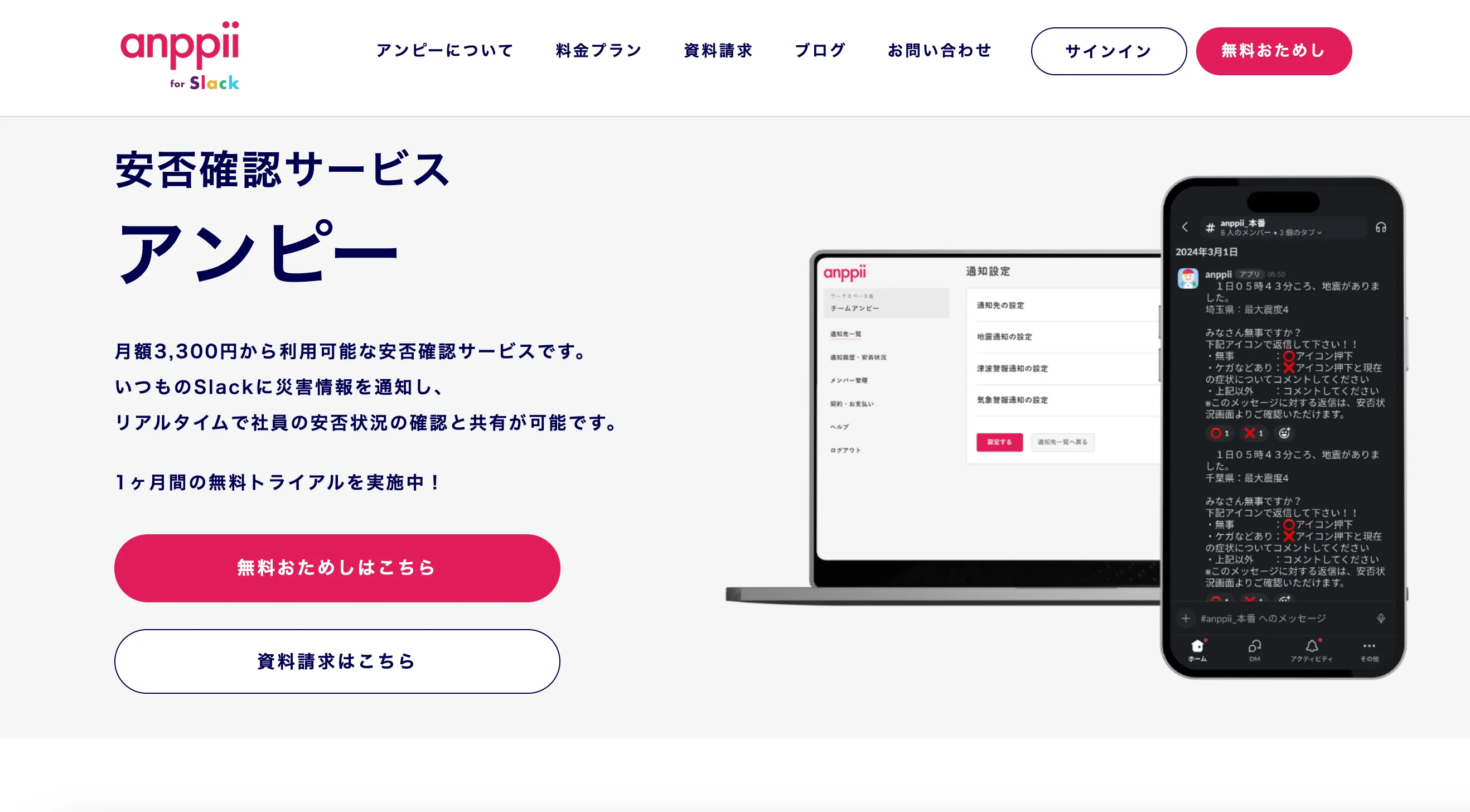 出典:anppii(アンピー)
出典:anppii(アンピー)
概要
anppii(アンピー)は、月額3,300円から利用できる安否確認サービスです。また、ワンクリックでの手動通知による訓練を実施できるため、いざというときに備えることができます。また、気象庁からの災害情報を、Slackと連携していればSlackで自動通知をするため、日頃から利用している場合は迅速に確認・反応できる点も魅力です。
料金
チャンネル数や、月払い/年払いによって変動します。
詳細は公式サイトでご確認ください。
まとめ
災害や緊急時に迅速な安否確認を可能にする「安否確認サービス」は、現代の生活やビジネスにおいて欠かせないツールとなっています。本記事では、安否確認サービスの基本的な仕組みや選び方のポイント、さらには具体的なおすすめ7選について解説しました。
サービスを選ぶ際には「機能性」「ユーザビリティ」「コストとサポート体制」という3つのポイントを重視することが重要です。
安否確認サービスを活用することで、大切な人や組織を守る準備を整え、予期せぬ事態にも安心して対応できる環境を築くことができます。ぜひ本記事を参考に、自分に合ったサービスを見つけてください。
よくある質問
Q. 安否確認サービスはどのように機能しますか?
安否確認サービスは、災害や緊急時に登録したユーザーに自動でメッセージを送信し、安否の回答を収集する仕組みを持っています。サービスを使用することで、事前に登録した連絡先全員に一斉に通知を送信でき、回答結果はリアルタイムで管理画面やダッシュボードに表示されます。一部のサービスでは、位置情報の共有や、回答データをレポート形式でエクスポートする機能も搭載されています。特に企業向けのサービスでは、従業員規模の大きな組織でも効率的に運用できる設計となっています。
Q. 無料で利用できる安否確認サービスはありますか?
はい、多くの安否確認サービスには無料プランが用意されています。無料版では、基本的な安否確認機能や通知送信機能を利用できることが一般的です。ただし、無料プランでは利用人数や通知回数に制限がある場合が多いため、利用目的や規模に応じてプランを検討する必要があります。