毎月の給与処理にかかる工数は、給与計算ソフトを利用すれば大幅に削減できます。継続的に使用するために、選定時には、システムの拡張性やカスタマイズ性、そして他の業務システムとのシームレスな統合が鍵となります。また、データセキュリティやコンプライアンス対応についても見逃せません。本記事では、API連携や勤怠データの自動取込にも触れながら、おすすめの給与計算ソフトを7つご紹介します。
給与計算ソフトとは
給与計算ソフトは、従業員の給与を計算し、支給に関する諸手続きを自動化するためのツールです。従来手作業で行われていた複雑な計算やデータ管理がシンプルになり、業務効率化に寄与します。大企業のほか、中小企業や個人事業主のニーズに応えるソフトも増えています。
最近では、勤怠管理や社会保険の計算、年末調整などの機能が統合されていることが一般的です。また、データの連携機能を持つソフトも増えており、会計ソフトとの連携によりさらなる効率化が期待されています。
自社で必要な機能を把握し、その機能を備えているサービスを選択することが重要です。以下で給与ソフト7つの概要をご紹介します。選定時の参考にしてください。
給与計算ソフトの選び方
給与計算ソフトを選ぶ際には、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、3つのポイントについて解説します。
1. 機能と対応業務の範囲
給与計算ソフトを選ぶ際に最初に考慮すべきは、そのソフトウェアが提供する機能の範囲です。基本的な給与計算機能に加え、勤怠管理、社会保険、年末調整、税金計算などの機能が統合されているかを確認しましょう。特に、中小企業や個人事業主においては、複数の業務を1つのプラットフォームで管理できるかどうかが、業務負担を軽減する鍵を握ります。
また、明細書の自動生成や、マイナンバー管理機能も重要です。これらの機能があると、必要な手続きを簡素化し、計算ミスの防止に役立ちます。
2. 価格と導入形態
ソフトウェアの価格や導入形態も重要です。特に、予算にこだわりのある中小企業や個人事業主にとって、コストは重要な要素です。
クラウド型の場合、初期コストは低く抑えられることが多い上に、インターネット環境があればいつでもどこでもアクセスできる利点があります。一方、インストール型は一度の支払いで永続的に使用できるため、長期的に考えるとコストパフォーマンスが良い場合もあります。自社の運用スタイルや予算に合わせた選択が求められます。
3. システムの互換性とデータ連携
他の業務システムとの互換性やデータ連携機能も確認しましょう。特に会計ソフトや勤怠システムとの連携がスムーズだと、データの一元管理や伝票処理の簡略化に役立ちます。
API連携を重視しているソフトウェアであれば、自社のニーズに応じて柔軟にシステムを拡張できます。また、CSVファイルの出力やインポート機能が搭載されていると、既存のデータとの統合が簡単になります。セキュリティ面も考慮し、データが安全に管理されていることを確認することが大切です。
以上の3つのポイントを踏まえて、自社に最適な給与計算ソフトを選定しましょう。
給与計算ソフトの比較
1. 弥生給与 Next
 出典:弥生給与 Next
出典:弥生給与 Next
弥生給与 Nextは、日本の中小企業・個人事業主向けに会計・給与・販売管理などの業務ソフトを提供する弥生株式会社が提供する、給与計算ソフトです。登録ユーザー数は350万を突破しています。
このソフトを使えば、給与計算・年末調整・勤怠管理・労務管理などを一元管理でき、それぞれをシームレスにつなぐことができます。社会保険や労働保険の計算機能も充実しているため、法令に基づいた正確な計算をサポートします。
料金
- ベーシックライト:¥3,000/月
- ベーシック:¥4,600/月
- ベーシックプラス:¥7,000/月
料金体系は初期費用(0円)+ 基本料金 + 従量課金オプション 詳細は公式ページでご確認ください。
https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/price/
2. スマレジ・タイムカード
 出典:スマレジ・タイムカード
出典:スマレジ・タイムカード
スマレジ・タイムカードは、クラウドベースの給与計算ソフトウェアで、特に勤怠管理機能に優れています。このツールは、従業員の出退勤データをリアルタイムで記録し、給与計算に必要なデータを自動的に取り込みます。
給与計算に加えて、年末調整や賞与計算の機能も備わっているため、煩雑な手続きを大幅に簡素化できます。また、テレワーク環境にも対応しており、多様な勤務形態に適応した使い方ができます。例えば、オンラインでの出退勤や勤怠登録が可能です。スマレジ・タイムカードは、操作がわかりやすく直感的なUIが特徴で、新しいユーザーでもすぐに導入できるのが魅力です。
料金
- スタンダード:¥0/月
- プレミアム:¥2,420/月
- プレミアムクラス:¥4,840 /月
- エンタープライズ:¥7,260/月
詳細は公式ページでご確認ください。
https://timecard.smaregi.jp/price/
3. マネーフォワードクラウド給与
マネーフォワードクラウド給与は、クラウド型の給与計算ソフトで、最新の税制に対応した機能を提供しています。勤怠集計や自動計算、Web明細の発行などが可能です。また、他社サービスとの連携や、銀行との振り込み連携、支給額や控除額の計算も自動で行うため、日々の業務工数を大幅に削減することができます。
また、カスタムの計算式によって、より柔軟な式を作成することができます。残業代や固定残業代を細かく計算したい場合などに便利です。いくつかのシステムとは、API連携やCSV連携が可能です。
料金
- スモールビジネス:¥2,980/月
- ビジネス:¥4,980/月
上記は年額プランの場合。 企業規模によっておすすめのプランが変わります。 詳細は公式ページでご確認ください。
https://biz.moneyforward.com/payroll/price/
4. freee人事労務
 出典:freee人事労務
出典:freee人事労務
freee人事労務は、多機能な人事管理ソフトウェアとして人気があります。給与計算機能に加え、従業員の勤怠管理や入退社管理も行える完全な人事管理機能が搭載されています。給与計算は自動化されており、変更があった場合も迅速に対応が可能。また、マイナンバーや社会保険の管理も行い、法令遵守をサポートします。
会計ソフト「freee」との連携により、経理業務もスムーズに進められます。クラウド型のため、常に最新機能を利用できる点もメリットです。
料金
詳細は公式ページでご確認ください。
https://www.freee.co.jp/hr/pricing/
5. 給与奉行クラウド
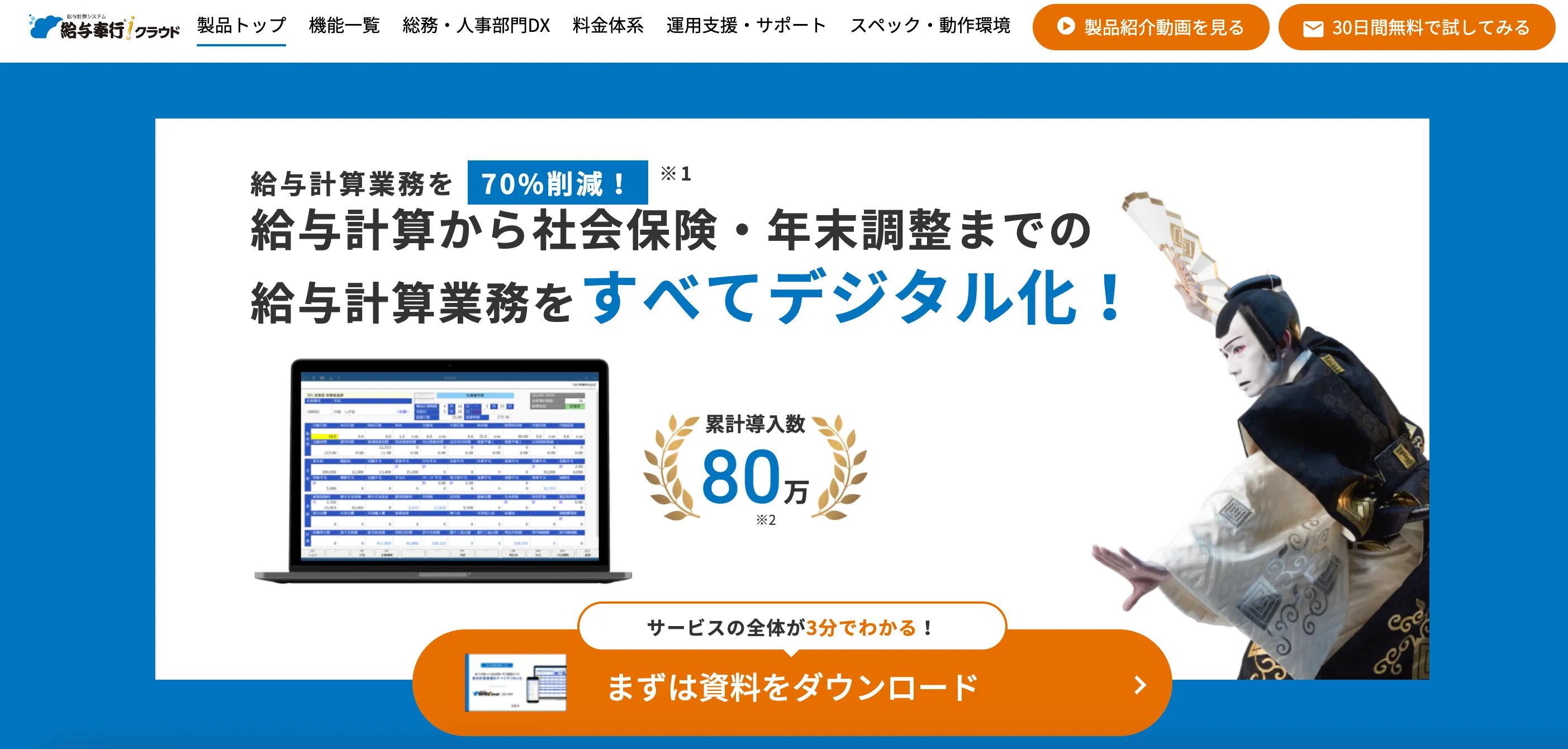 出典:給与奉行クラウド
出典:給与奉行クラウド
給与奉行クラウドは、豊富な機能と高いカスタマイズ性を誇る給与計算ソフトです。業界ごとの特性に応じた設定が可能で、特に製造業やサービス業に強みを持っています。
このソフトでは、複雑な給与計算や厚生年金の算出も自動で行え、給与明細の作成も迅速に行えます。さらに、データの分析機能が充実しており、企業全体の人件費管理を効果的に行うことができます。セキュリティ対策も強化されており、安心してデータ管理が可能です。
料金
従業員規模に応じて、いくつかのプランが用意されています。 詳細は公式ページでご確認ください。
https://www.obc.co.jp/bugyo-cloud/kyuyo/price
6. COMPANY
 出典:COMPANY
出典:COMPANY
COMPANYでは、給与計算に関する複雑な業務を様々な機能で自動化できます。例えば、月例給与や賞与の計算、福利厚生制度、社会保険、年末調整や税計算、退職金や企業年金などの計算機能があります。
会社や職種、社員の区分などで計算ルールは異なりますが、複雑な給与計算もボタンひとつで計算できる点はCOMPANYの強みです。また、多岐にわたる福利厚生制度にも対応しているため、煩雑な業務をシンプルに処理できるようになります。
料金
詳細は公式サイトでご確認ください。
https://www.works-hi.co.jp/products/payroll
まとめ
給与計算ソフトは、業務における給与の計算や管理を効率化するための必須ツールです。選ぶ際には、ニーズに応じて機能や価格を比較することが重要です。今回紹介したソフトは、勤怠管理、社会保険、年末調整といった機能を統合し、業務負担を軽減します。
また、クラウド型やインストール型、さらにはAPI連携の可否といった点も確認すべき要素です。自社のニーズに最適なソフトウェアを選定することで、業務の円滑さが向上し、正確な給与管理が実現します。是非、検討してみてください。
よくある質問
Q. 給与計算ソフトはどのような機能が必要ですか?
給与計算ソフトには、基本的な給与計算機能はもちろん、勤怠管理、社会保険、年末調整などの機能が重要です。これにより、業務の管理が一元化され、手間を減少させることができます。また、明細書の自動生成やマイナンバー管理機能があると、さらなる利便性を提供します。
Q. クラウド型とインストール型のどちらが良いですか?
クラウド型は初期コストが低く、インターネットさえあればどこからでもアクセスが可能です。一方、インストール型は一度の支払いで永続的に利用できるため、どちらが適しているかは自社の運用スタイルや予算に依存します。
Q. 他のシステムとの連携は可能ですか?
多くの給与計算ソフトは、会計ソフトや勤怠システムとの連携機能を備えています。API連携やCSVデータのインポート/エクスポートに対応しているかを確認し、他の業務システムと効果的にデータ連携ができることが望ましいです。
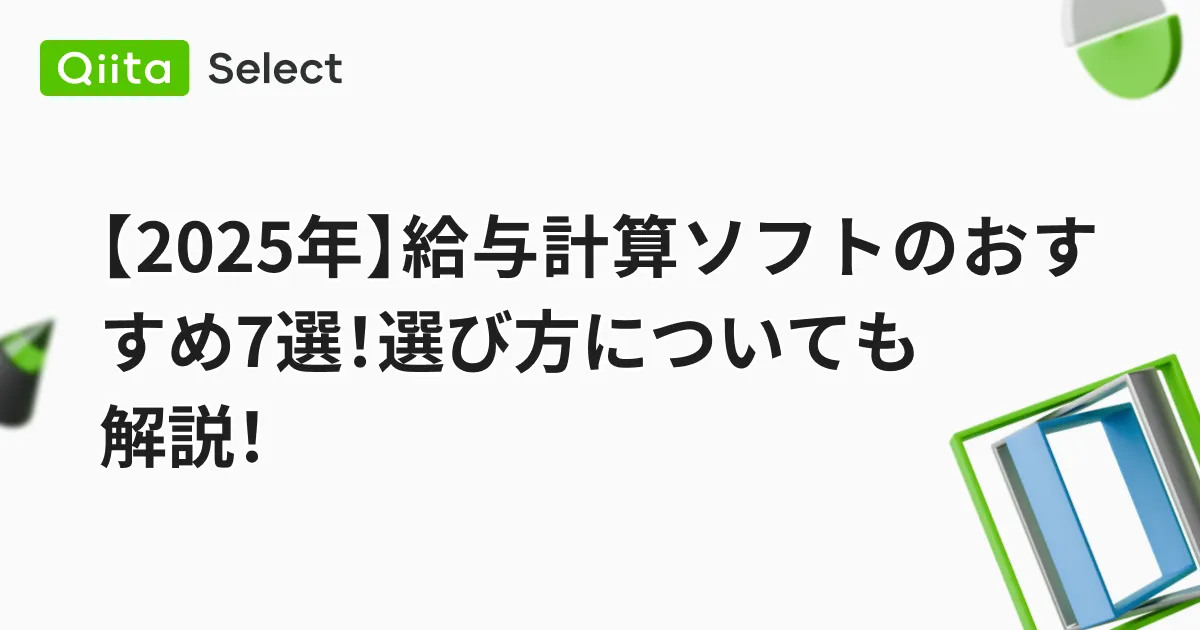
 出典:
出典: