在宅ワークをしていると、長時間の座り作業によって、腰痛や肩こりを感じている方もいるのではないでしょうか?その悩みを解決する方法のひとつが、昇降デスクの活用です。昇降デスクを使うことで座りと立ちを使い分けながら作業でき、体への負担を分散したり、集中力を高めたり、気分転換を図れたりします。
そこで今回は、在宅ワークをする機会の多い方に向けて、昇降デスクとは何か、昇降デスクの選び方、おすすめの昇降デスクをご紹介します。
昇降デスクとは?
昇降デスクとは高さを調整できるデスクのことで、座って作業するだけでなく、立って作業することも可能な設計になっています。最近の働き方の多様化に伴う在宅勤務やフリーランスの増加により、昇降デスクの人気が高まっています。ユーザーは自分の体調や作業内容に応じて最適な作業姿勢を選ぶことができるようになります。
昇降デスクには主に手動式と電動式の2種類があります。手動式の場合、ハンドルやレバーを使って高さを調整し、電動式の場合はボタンひとつで簡単に高さを変更できます。電動式は特にスムーズでストレスの少ない調整が可能なため、利用者の間で人気があります。
昇降デスクを使うメリット
昇降デスクは、健康面や作業効率向上に寄与します。長時間の座り作業は腰痛や肩こりを引き起こす可能性がありますが、昇降デスクを使用して座ったり立ったりを交互に行えば、体への負担を軽減できます。自分の体調に応じてスタイルを選び、快適に作業できる環境を整えられる点も利点です。デスクの高さを簡単に調整できるため、個々の作業スタイルに応じたカスタマイズが可能です。
また、集中力や生産性の向上も期待できます。立って作業すると血流が促進され、エネルギーレベルが増加するとされています。結果として、メンタルもリフレッシュされ、仕事に対するモチベーションの向上にもつながります。
昇降デスクの選び方
1. 高さ調整の範囲とメカニズム
昇降デスクを選ぶ際の最も重要なポイントの一つは、高さ調整の範囲とそのメカニズムです。デスクの高さは、ユーザーの身長や作業スタイルに合わせて調整する必要があります。一般的に、デスクの高さは現在72cmが推奨されています(参照:一般社団法人 日本オフィス家具協会)。特に立ち作業の場合は身長によって最適な高さが変わりますが、110cmまで調整できると、快適に利用できる人の幅が広がります。
また昇降デスクには、手動式と電動式があります。手動式はハンドクランクやレバーを使用し、価格が比較的安いのが特徴です。一方、電動式はボタン一つでスムーズに高さ調整が可能です。自分の利用シーンや好みに合わせて選びましょう。
2. 耐荷重と安定性
昇降デスクを選ぶ際には、耐荷重と安定性も重要な考慮ポイントです。デスクの耐荷重は、パソコン、モニター、書類、その他の作業道具を含めた全体の重さを考慮して選びましょう。
安定性も重要です。デスクを立って使用する際には、高さを調整した状態で揺れたり、ガタついたりしないことが求められます。安定性を確認するためには、デスクの脚部の設計や素材をチェックすることが大切です。特に重い装備を置く予定がある場合、製品の説明やレビューを参考にし、収束が良く安定したデスクを選ぶことをお勧めします。
3. デザインと機能性
昇降デスクを選ぶ際には、デザインと機能性も無視できません。デスクのスタイルや色は、使用する環境に調和する重要な要素で、特に自宅やオフィスで使う場合、自分のインテリアにマッチするデザインを選ぶと良いでしょう。昨今はモダンな外観やシンプルなラインのデザイン、カラーバリエーションなど、多くの選択肢があります。
また、昇降デスクには、配線管理システムや収納スペースが設けられている場合があります。これにより、ケーブルや周辺機器を整理しやすく、作業環境をすっきり保ちやすくなります。加えて、一部のデスクにはUSBポートやワイヤレス充電機能が付いているものもあり、利便性に寄与します。自分の作業スタイルや使用環境に合わせたデザインと機能を選ぶことが、快適な作業環境を実現する鍵となります。
おすすめの昇降デスクをご紹介
以下で、おすすめの昇降デスクをご紹介します。色やサイズなどのバリエーションが豊富な場合もありますので、ご自身でご確認ください。
Flexispot EF1
Flexispot EF1は、コストパフォーマンスが高く、入門としてもおすすめの昇降デスクです。高さは69.5cmから112cmまで調整でき、立ち・座りいずれの場合でも最適な作業環境を保てます。耐荷重は70kgで、ディスプレイなどの重いものも安心して置くことができます。
また、電動昇降のため、重いものが乗っていても楽に高さを調整できます。複数の高さをあらかじめセットできる「高さ記憶ボタン」があり、立ち・座りいずれの場合でも、自身に快適な高さに設定できます。
Amazonで見るFlexispot E7H
Flexispot E7Hは、多くの機能を備えていることに加え、安定性の向上を実現するための大型フットパッド、剛性・安定性に優れているデュアルクロスビーム、SPCCスチールの採用や強化された脚フレームという高品質な素材を備えた、優れた安定性が魅力の昇降デスクです。
多くの機能は、具体的には、電動昇降機能、ロック機能、複数の高さをあらかじめセットできるメモリ機能、充電可能なUSB端子などが挙げられます。また、デスク周りを整理しやすいように、ケーブルトレイやマグネット付きケーブルカバーが備えられています。
Amazonで見る 楽天市場で見る山善 電動昇降デスク スタンダードモデル
山善では、工作機械・産業機器・機械工具・住設・家庭用機器など、様々な商品を取り扱っています。電動昇降デスク スタンダードモデルは、企画・開発の全てを日本で行っており、厳しい基準を設け、徹底された品質管理のもとで製造されています。色、サイズ、フォルムなど、バリエーションが豊富なため、自分に合うデスクを選べます。
昇降は静かで安定しています。障害物にぶつかった際にセンサーが感知して動きを止める衝撃検知センサー、高さを登録できるメモリー機能なども搭載されています。天板の裏にコードをまとめられるトレイがついており、見た目をスッキリできる点も魅力です。
Amazonで見る 楽天市場で見る山善 電動昇降デスク ハイエンドモデル
山善 電動昇降デスク ハイエンドモデルでは、日本人の身長に合わせた高さ設計がされていたり、スタンダードモデルと比較して昇降スピードが124%アップしているなどの特徴があります。
また、スタンダードモデル同様に、昇降は静かで安定しており、衝撃検知センサーやメモリー機能、天板裏にコードをまとめるトレイが用意されています。天板の表面にはメラミン加工が施されており、傷や汚れ、水や熱に強く、お手入れも簡単です。
Amazonで見る 楽天市場で見るCOFO Desk Premium
COFO Desk Premiumは、最上級を目指したワークデスクです。昇降範囲は63cm〜128cmと広く、小柄な方から背の高い方まで使えます。耐荷重は125kgで、モニターをおいても安心。障害物探知機能や、スマホの充電などに対応するUSB-Aポートや高さを記憶するメモリー機能などがついており、簡単に操作できる機能パネルも付いています。
オプションで引き出しやケーブルトレイなどを付けることができ、デスク周りをスッキリと片付けたい方におすすめです。天板には無垢材が使用され、高級感があります。ウレタン塗装で表面を保護する加工が施されており、汚れをさっと拭き取れます。
公式サイトで見るKANADEMONO THE TABLE
 出典:KANADEMONO
出典:KANADEMONO
KANADEMONO THE TABLEは、デザインも機能性も優れた昇降デスクです。脚にはデンマークのメーカーLINAK社の電動昇降脚が使用されており、北欧インテリアならではの魅力があります。
天板は63〜128cmの幅で調整が可能。世界三大銘木と称されるウォルナットが使用されており、落ち着きのある高級感があります。様々な形のトレイやティッシュボックスなどのオプションで、使い勝手の良いデスク環境を作り出せます。
公式サイトで見るまとめ
在宅ワークにおいて、昇降デスクの導入は腰痛や肩こりを軽減し、作業効率を向上させる効果があります。昇降デスクは、座ったり立ったりの作業スタイルを選べることで、身体への負担を分散し、集中力を高めることが可能です。選ぶ際には、高さ調整の範囲やメカニズム、耐荷重や安定性、デザインや機能性などが重要なポイントとなります。快適な作業環境を整えるためには、自分のライフスタイルに合った昇降デスクを選ぶことが大切です。
よくある質問
Q. 昇降デスクはどのくらいの高さ調整が可能ですか?
昇降デスクの高さ調整範囲はモデルによって異なりますが、一般的には約60cmから120cmまで調整できるものが多いです。自分の身長に合わせたデスクの高さを選ぶことが重要です。
Q. 電動式と手動式の昇降デスクはどちらが良いですか?
電動式はボタン一つで簡単に高さを調整できるため、特に便利で人気があります。対して手動式は価格が比較的安く、電源も必要ないため、コストを抑えたい方には良い選択となります。
Q. 昇降デスクはどのようなケーブル管理ができますか?
多くの昇降デスクには、ケーブルを整理するためのトレイや穴が設けられています。これにより、デスク周りをすっきり保つことができ、効率的に作業が行えます。
Q. 昇降デスクでの作業は本当に健康に良いの?
昇降デスクを使うことで、座りっぱなしの時間を減らし、立って作業することで血流が良くなり、身体の負担を軽減できます。これにより、腰痛や肩こりの軽減、集中力や生産性の向上が期待できるため、健康面でもメリットがあります。
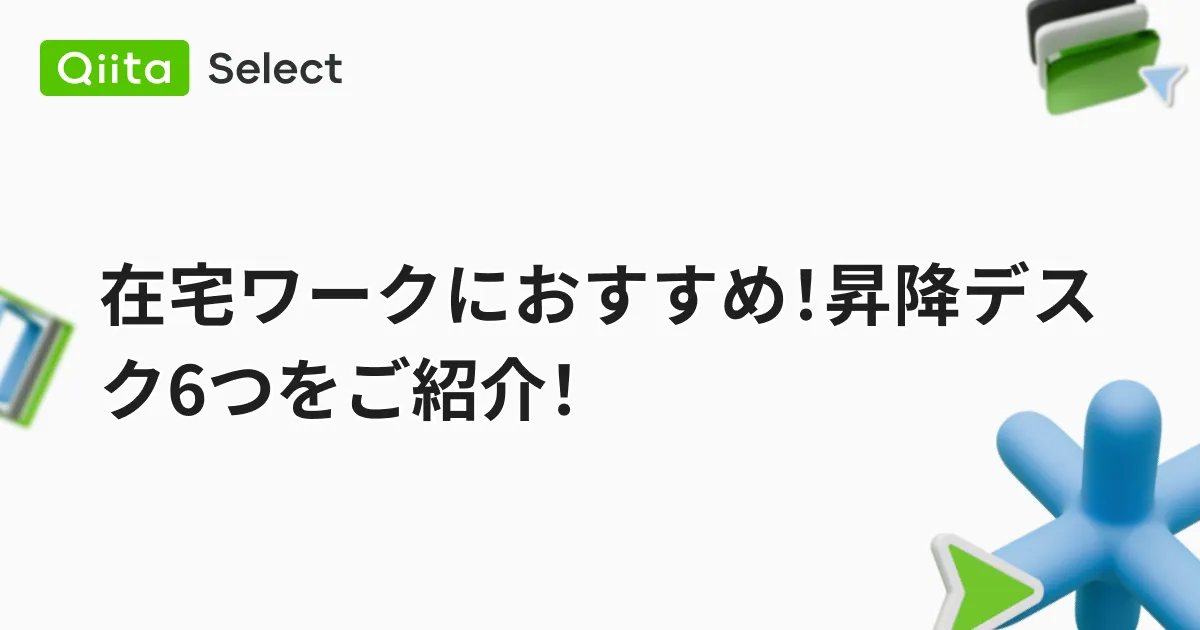
 出典:
出典: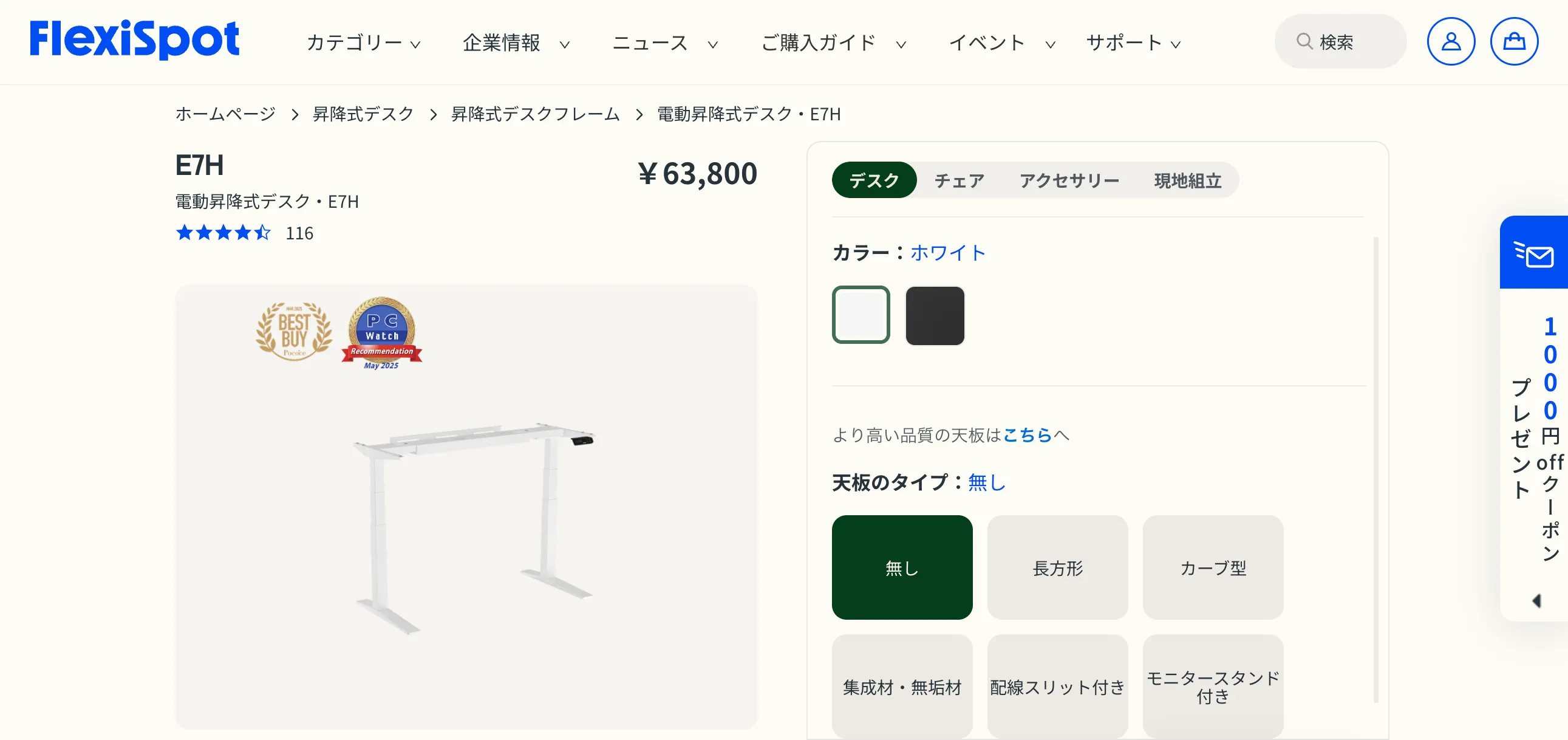 出典:
出典: 出典:
出典: 出典:
出典: 出典:
出典: