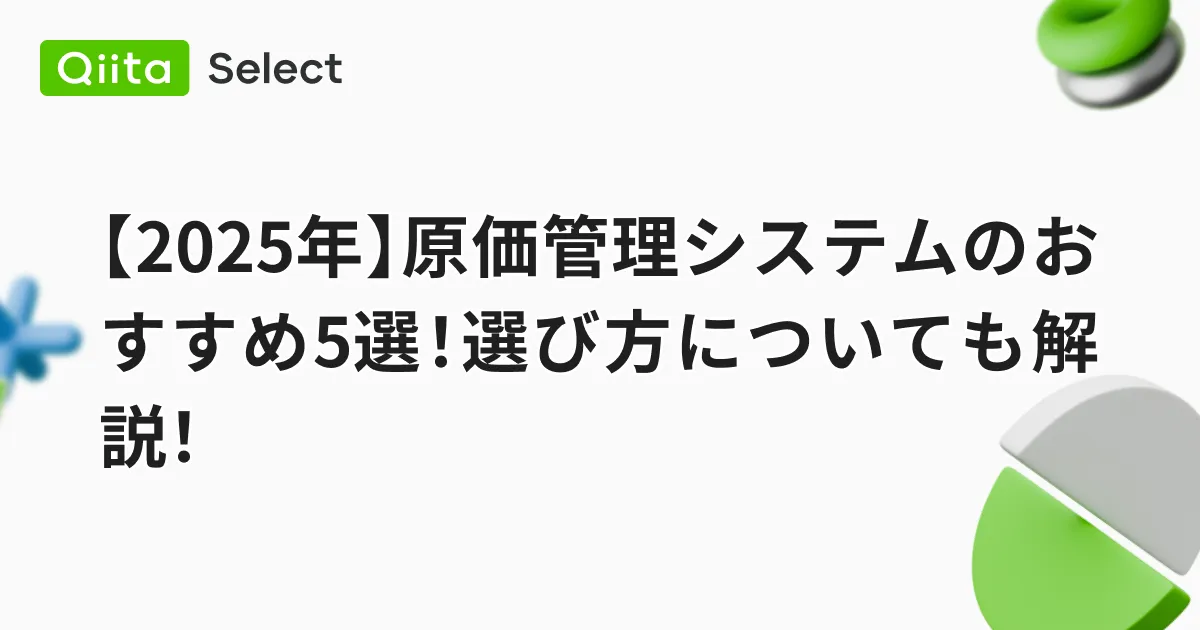原価管理システムとは、企業が製品やサービスの原価を正確に把握し、コスト削減や収益性の向上を図るためのツールです。具体的には、原価計算、予算と実績の比較、差異分析、損益計算、原価シミュレーションなどの機能を備えています。
従来、エクセルなどを利用して行われていた原価管理は、データの分散や入力ミス、集計の手間など多くの課題がありました。原価管理システムを導入すれば、これらの業務を自動化し、データの一元管理やリアルタイムな情報共有が可能になり、迅速な経営判断や的確なコストコントロールにつながります。
導入や選定においてはシステムの拡張性やAPIの活用も重要なため、エンジニアの視点が欠かせません。今回は、原価管理システムを選ぶ際のポイントと、おすすめのサービスをご紹介します。選定時の参考にしてください。
原価管理システムの選び方
1. 自社の業種や業務プロセスに適合した機能性
原価管理システムは、製造業、建設業、飲食業など、業種ごとに求められる機能が異なります。例えば、製造業では材料費や労務費の詳細な管理が必要とされる一方、建設業ではプロジェクトごとのコスト管理や進捗管理が重視されます。
そのため、システムが自社の業種特有の業務プロセスに対応しているかを確認しましょう。また、将来的な事業拡大や業務変更にも柔軟に対応できる拡張性も考慮すると良いです。具体的な導入事例やユーザーの声を参考に、自社のニーズに最適なシステムを選びましょう。
2. 既存システムとの連携性と操作性
原価管理システムは、販売管理、在庫管理、会計システムなど、他の基幹システムとのデータ連携がスムーズであることが求められます。システム間の連携が円滑でないとデータの二重入力や情報の不整合が発生し、業務効率の低下を招く可能性があります。
また、ユーザーインターフェースが直感的で操作しやすいことも重要です。現場のスタッフが日常的に使用するツールであるため、操作性が悪いと定着率が下がり、システム導入の効果が半減してしまいます。トライアル期間を設けて実際に操作感を確認することや、ベンダーからのサポート体制をチェックすることが推奨されます。
3. 導入コストとランニングコストのバランス
システム導入に際しては、初期費用だけでなく、保守費用やアップデート費用などのランニングコストも考慮しましょう。クラウド型のシステムは初期投資を抑えられる反面、月額費用が発生します。一方、オンプレミス型は初期費用が高額になるものの、長期的にはコストを抑えられる場合もあります。
自社の予算やITインフラ、運用体制を踏まえ、総合的なコストパフォーマンスを評価しましょう。システムのカスタマイズ性や将来的な拡張性も長期的な視点でのコストに影響を与えるため、慎重な検討が必要です。
原価管理システムのおすすめ7選
以下に、原価管理システムおすすめ7選を紹介します。
それぞれの特徴や機能を詳しく解説します。
1. mcframe 7 PCM

概要
mcframe 7 PCMは、製造業を中心とした企業向けの原価管理システムです。製造部門、営業部門、事業部門など、各担当者の利用用途に応じて、シミュレーションによる原価目標を設定し、PDCAサイクルを実現します。
特徴
- 高度なコストマネジメント:詳細な原価計算機能を備え、製品別やプロジェクト別のコスト分析が可能です。
- シミュレーション機能:原価目標の設定や達成度の確認をシミュレーションで行い、戦略的な意思決定をサポートします。
- 部門別の最適化:製造、営業、事業部門など、各部門のニーズに対応した機能を提供します。
料金
詳細は公式サイトよりお問い合わせください。
公式サイト:https://www.mcframe.com/product/7/pcm
2. アラジンオフィス
 出典:アラジンオフィス
出典:アラジンオフィス
概要
アラジンオフィスは、在庫管理・販売管理・生産管理を統合的にサポートするシステムです。多様な業種・業態に対応し、企業の業務効率化を支援します。
特徴
- 豊富な機能と柔軟性:販売管理、在庫管理、生産管理など、企業のニーズに合わせた多彩な機能を標準搭載しています。
- 業種別パッケージ:卸・商社、小売、製造・加工など、業種特有の業務フローに対応したパッケージを提供します。
- 外部システム連携:会計システムやECサイト、倉庫管理システムなど、他のシステムとの連携が可能で、業務全体の効率化を図れます。
料金
詳細は公式サイトよりお問い合わせください。
公式サイト:https://aladdin-office.com/ex/project/
3. ProSee

出典:ProSee
概要
ProSeeは、製造業向けの原価管理システムで、製品別の原価計算や在庫管理、製造プロセスの分析機能を提供します。生産現場のデータを一元管理し、経営判断をサポートします。
特徴
- 詳細な原価計算:材料費、労務費、経費など、各コスト要素を正確に計算し、製品別の採算性を分析します。
- 在庫管理機能:原材料や製品の在庫状況を把握し、適正在庫の維持を支援します。
料金
詳細は公式サイトよりお問い合わせください。
公式サイト:https://prosee.info/
4. 楽楽販売
 出典:楽々販売
出典:楽々販売
概要
楽楽販売は、株式会社ラクスが提供するクラウド型の販売管理システムです。見積もり、受注、発注、請求、売上、原価管理など、販売業務全般を一元管理し、業務の効率化とミスの削減をサポートします。累計導入社数は5,000社を超え、多様な業種・業態で活用されています。
特徴
- 自社仕様にカスタマイズ可能:項目や入力画面、操作メニューを自社の業務フローに合わせて柔軟にカスタマイズできます。
- 帳票の自動作成と送信:見積書や請求書などの帳票を簡単に作成し、メール添付や自動送信ができます。複数の帳票フォーマットを登録でき、業務に応じた柔軟な対応が可能です。
- 外部システムとの連携:CSV形式のデータの一括取り込み・出力や、API連携による自動データ取り込みにも対応しています。
- リアルタイムな情報共有:クラウド上であらゆる情報をリアルタイムに共有でき、属人化や伝達漏れを削減します。チーム全体でのスムーズな業務遂行が可能となります。
- 電子帳簿保存法への対応: 電子帳簿保存法に対応しており、原本管理コストの削減やペーパーレス化を実現します。法令遵守と業務効率化を同時に達成できます。
料金
- 初期費用: 150,000円(税抜)
- 月額費用: 70,000円~(税抜)※利用ユーザー数やデータベース作成数に応じて変動します。
詳細は公式サイトでご確認ください。
公式サイト: https://www.rakurakuhanbai.jp/
5. マネーフォワード クラウド個別原価

概要
マネーフォワード クラウド個別原価は、株式会社マネーフォワードが提供するクラウド型の個別原価管理システムです。システム開発やIT業、士業やプロジェクト型ビジネスに特化し、工数入力、費用データ収集、配賦、個別原価計算、プロジェクト原価の可視化を支援します。
特徴
- 自動化された間接費配賦:プロジェクト工数や労働時間など、自社の運用に合わせた配賦基準を設定し、自動で配賦比率を算出して間接費の配賦計算を行います。配賦ルールの変更にも柔軟に対応できます。
- プロジェクト原価のリアルタイム可視化:クラウド上で最新の原価情報を閲覧可能です。経営判断をサポートする正確なデータを迅速に共有できます。
- 多様なサービスとの連携:マネーフォワード クラウドシリーズや他の周辺サービスと連携し、個別原価管理をさらに効率化します。業務フローの最適化と内部統制の強化が図れます。
料金
利用するユーザー数により料金が変動します。
詳細な料金については、公式サイトからお問い合わせください。
公式サイト: https://biz.moneyforward.com/project-cost/
まとめ
原価管理システムは、企業が製品やサービスの原価を正確に把握し、コスト削減や収益性の向上を図るための重要なツールです。本記事では、2025年におすすめの原価管理システムを5つご紹介しました。
システム選定の際は、自社の業種や業務プロセスに適合した機能性、既存システムとの連携性と操作性、導入コストとランニングコストのバランスを考慮することが重要です。適切な原価管理システムを導入することで、業務の効率化と正確なコスト管理が期待でき、企業の競争力強化につながるでしょう。
よくある質問
Q. 原価管理システムはどのような業種に適していますか?
原価管理システムは、製造業、建設業、飲食業など、幅広い業種で活用されています。製造業では材料費や労務費の詳細な管理に役立ち、建設業ではプロジェクトごとの収支や進捗を管理する機能が重宝されています。また、飲食業ではメニューごとの原価計算や在庫管理に対応したシステムが選ばれる傾向があります。業種に特化したシステムを選ぶことで、より効果的に活用できます。
Q. クラウド型とオンプレミス型のどちらを選ぶべきですか?
クラウド型は初期投資が抑えられ、場所を選ばずアクセスできる点が利点です。一方、オンプレミス型は初期費用が高額になるものの、長期的にはランニングコストを抑えられる場合があります。選択は、自社のIT環境、予算、業務プロセスに応じて慎重に行うことが大切です。また、クラウド型は定期的なアップデートや法改正への対応が容易なため、迅速な対応が求められる企業に適しています。
Q. 無料の原価管理システムでも十分に対応可能ですか?
無料の原価管理システムは、基本的な原価計算や予算管理を行うには十分な場合があります。ただし、業種特有の機能や複雑な業務プロセスへの対応が必要な場合、有料のシステムを検討する方が適切です。無料版を試してみて、自社のニーズに合うかどうか確認し、不足がある場合は有料システムへの移行を検討すると良いでしょう。